進学指導重点校とは?
東京における進学指導重点校とは2001年に東京都教育委員会が高校生の進学実績を向上させる目的で指定した、都立高校の取り組みです。このプログラムにより、特定の高校が、特に大学進学に向けた強化指導を行うことを目指して選定されました。
進学指導重点校が誕生した背景
進学指導重点校は、1990年代以降の教育環境の変化を背景に誕生しました。
当時、都立高校は大学進学実績の低迷や都立離れが進行しており、公教育の質の向上が課題となっていました。また、生徒・保護者のニーズの多様化に伴い、学校選択制の導入や各校の特色化が進められ、難関大学進学を目指す層への専門的な教育プログラムが求められるようになりました。
さらに2000年代には、中高一貫教育の制度化や教育基本法改正など、教育改革の流れが本格化。この状況を受けて東京都は、一部の都立高校を「旗艦校」として重点的に強化する進学指導重点校制度を導入しました。
この制度では、高度な教育カリキュラムや特別講座、個別指導などを実施。これにより、公教育全体の質の向上と都立高校の魅力回復を目指したのです。
進学指導重点校の選定・更新基準
- 〔基準1〕現役受験生(高校3年生)の共通テスト試験結果
①5教科7科目で受験する者の在籍者に占める割合が、おおむね6割以上
②難関国立大学等に合格可能な得点水準(おおむね8割)以上の者の受験者に占める割合が、おおむね1割以上 - 〔基準2〕難関国立大学等(東京大学・京都大学・東京工業大学・一橋大学・国公立大学医学部医学科)の現役合格者数 15人
【2024年最新】進学指導重点校・進学指導特別推進校・進学指導推進校一覧
進学指導重点校(7校)
2001年に最初の4校(日比谷・西・戸山・八王子東)が進学指導重点校に選定され、2003年に3校(国立・青山・立川)が追加で選定されました。その後幾度かの更新タイミングがありましたが、この2024年現在もこの7校が進学指導重点校として都内トップクラスの大学合格実績を誇っています。
上記7校すべてが進学指導重点校となった2003年、難関大学(東京大学・京都大学・一橋大学・東京工業大学・国公立大学医学部医学科)への現役合格実績は上記7校”合計”で101名でした。それから20数年経った現在(2024年)、都立高校トップの合格実績を誇る日比谷高校だけで難関大学への現役合格101名をたたき出しています。
その他、戸山高校(46名)、国立高校(38名)、西高校(35名)、青山高校(22名)、立川高校(19名)、八王子東高校(16名)となっており、日比谷高校を加えた全7校で277人と難関国公立大学への合格実績は20年で2.7倍成長しています。

進学指導特別推進校(7校)
東京都立高等学校改革の一環として東京都教育委員会が2007年にまず5校(小山台、駒場、新宿、町田、国分寺)が指定され、その後2013年に国際、2018年に小松川が追加指定されました。教員を公募し、やる気と指導力のある教員を配置したり、平時の補習や夏休みや冬休みなど長期休業中の講習の充実など、進学指導の充実を図り進学実績の向上に重点をおいています。進学指導重点校に次ぐものであり、主な取り組みに大差はありません。
進学指導推進校(15校)
進学指導推進校とは、進学指導特別推進校と同じく東京都立高等学校改革の一環として東京都教育委員会が2007年より指定した、進学指導の充実を図り進学実績の向上に重点をおく都立高等学校のことです。地域ニーズや地域バランスも加味し、進学指導特別推進校に次ぐ進学校15校(2024年時点)が指定されています。
- 三田高校(港区)
- 豊多摩高校(杉並区)
- 竹早高校(文京区)
- 北園高校(板橋区)
- 墨田川高校(墨田区)
- 城東高校(江東区)
- 武蔵野北高校(武蔵野市)
- 小金井北高校(小金井市)
- 江北高校(足立区)
- 江戸川高校(江戸川区)
- 日野台高校(日野市)
- 調布北高校(調布市)
- 多摩科学技術高校(小金井市)
- 上野高校(台東区)
- 昭和高校(昭島市)
🏫 高校生活をより充実させるために、今から学びの準備を
校風や特色を調べながら「この学校に入りたい」と思ったら、勉強のペースづくりを始めるチャンス。
以下の学習サービスを活用すれば、授業理解・内申対策・基礎力アップを自宅で進めることができます。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】![]()
👉 【費用重視】月額1,815円~効率的に予習・復習できる動画教材なら スタサプ ![]()
👉 【難関対策】難関校志望者にも信頼される通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【内申UP】内申・定期テスト対策を家庭でサポート 家庭教師のノーバス ![]()
👉 【体験無料】実際の教師による安心サポートなら 家庭教師ファースト ![]()
👉 【東大の力】日比谷・西・国立など難関都立を目指すなら現役東大生の家庭教師数最大規模【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
進学指導重点校、進学指導特別推進校、進学指導推進校の違いは?
進学指導重点校に関しては前述のとおり、選定基準が存在しています。進学指導特別推進校と進学指導推進校は、明確な基準は確認できず、
進学指導特別推進校は、「都立高校における進学指導重点校等の指定について」にて公表されている基準を引用すると、
進学指導重点校に次ぐ大学合格実績をあげる学校の中から、各学校の取組状況等を総合的に勘案し、現在指定している7校を継続して指定する。
とのことで、2024年時点では7校が指定されています。また、進学指導推進校は、
進学指導特別推進校に次ぐ大学合格実績をあげる学校の中から、地域ニーズ・地域バランスや学校の取組状況等を総合的に勘案し、現在の指定校13校を継続して指定する。また、新たに、上野高校及び昭和高校を指定する。
とのことで、令和5年度から新たに上野高校、昭和高校の2校が追加され、合計15校が指定されています。
進学指導重点高校の特徴と利点と課題
進学指導重点高校の最大の特徴は、高い進学実績とそれを支える特別なカリキュラムにあります。多くの学校では、通常の授業に加えて、放課後や休日を利用した補習授業が行われ、さらに外部講師を招いた特別講座や合宿なども実施されています。また、生徒一人ひとりに対する進路指導が充実しており、個別の進学相談や模擬試験対策がきめ細かく行われます。これにより、生徒は自分の志望校に応じた学習計画を立てやすく、学習意欲を高めることができます。
さらに、進学指導重点高校では、学習環境が整っているため、学びへのモチベーションが高い生徒同士が切磋琢磨することができます。このような環境は、生徒にとって大きな刺激となり、自律的な学びの姿勢を育む助けとなります。結果として、多くの卒業生が高い学力と強い競争心を持って大学生活に臨むことができるのです。
一方で、進学指導重点高校にはいくつかの課題もあります。第一に、過度な競争が生徒に与える精神的・身体的負担です。進学実績を重視するあまり、生徒は長時間の勉強を強いられることが多く、疲弊してしまうケースも少なくありません。特に、受験のプレッシャーや過度のストレスが原因で、精神的な不調を訴える生徒が増えている点は見逃せません。
第二に、入試偏重の教育が問題視されています。進学指導重点高校では、大学受験に直結する学力向上が最優先されるため、多様な才能や個性を育てる教育が疎かになることがあります。この結果、創造性やコミュニケーション能力など、社会に出てから必要とされる力が十分に育まれないという指摘もあります。
また、進学指導重点高校に指定されていない地域や学校との格差も問題です。進学指導重点高校が設置されていない地域では、同等の教育機会が得られない場合があり、これが地域間の教育格差を広げる要因となっています。
進学指導重点高校の将来の展望
進学指導重点高校の今後の展望として、教育の多様化とICT(情報通信技術)の活用が期待されています。教育現場では、従来の一律的なカリキュラムから脱却し、生徒一人ひとりの個性やニーズに応じた教育が求められるようになってきています。そのため、進学指導重点高校でも、大学進学だけでなく、グローバル人材の育成や地域社会での活躍を見据えた教育プログラムの充実が課題となっています。
また、教育の質を高めるためには、学力のみならず、生徒のメンタルケアや個別指導の強化も必要です。現代の社会が求める人材は、学力だけでなく、多様な視点を持ち、他者と協働できる柔軟性を持った人材です。進学指導重点高校も、そのような人材育成を目指し、新たな教育の在り方を模索していく必要があります。
進学指導重点高校は、大学進学という日本の教育における一つの目標において重要な役割を果たしていますが、その一方で、多様な才能を育てるための改革も必要です。今後は、生徒一人ひとりが自分の可能性を最大限に発揮できるような教育環境を整えることが求められます。読者の皆さんは、「どのような教育が真に必要なのか?」と考える機会を持っていただければ幸いです。
💻 自分に合った勉強スタイルを見つけよう
塾・通信教育・家庭教師など、学び方はさまざま。
それぞれの特徴を知って、自分に合う方法を選ぶことが成績アップの近道です。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】
![]()
👉 【難関対策】難関校対策に定評のある通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【1対1】マンツーマンの個別指導で弱点克服 1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】 ![]()
👉 【東大の力】東大生講師から学べるオンライン指導 【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
👉 【内申UP】対面で安心して教わりたい人は 家庭教師のノーバス ![]()
難関校を目指すなら、自宅にも”本物の教材”を
「この高校に入りたい」――そう思ったとき、気になるのはやはり“受験への準備”。
自分のペースで本格的な受験対策がしたい中学生や、塾に通わずに質の高い学習を進めたいご家庭におすすめなのが【Z会の通信教育】です。
難関校対策に対応したハイレベルな教材と、記述力を伸ばす添削指導。
通信教育でありながら、学習習慣から答案力までしっかり鍛える仕組みが整っています。
本気で上位校を目指すなら、Z会という選択があります。
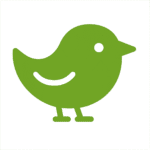 トリトリ
トリトリ部活も文化祭もひと段落。これからは志望校合格に向かってラストスパートをかける時期が来たよ!
秋は、学力を伸ばす絶好のタイミング。
Z会の通信教育〈高校受験コース〉なら、考えて「紙に書く」学びを通して、難関高校合格レベルへと実力を高められます。
苦手やレベルに合わせた個別プログラムで、定期テスト対策から入試対策までしっかりサポート。
今なら『英語Writingワーク』(学年別)と『自主学習の継続を後押しする保護者のサポートBOOK』をプレゼント中!
忙しい秋だからこそ、親子で「これからの学び」を見直すチャンスです。
\ 資料請求で2つの特典をプレゼント! /

