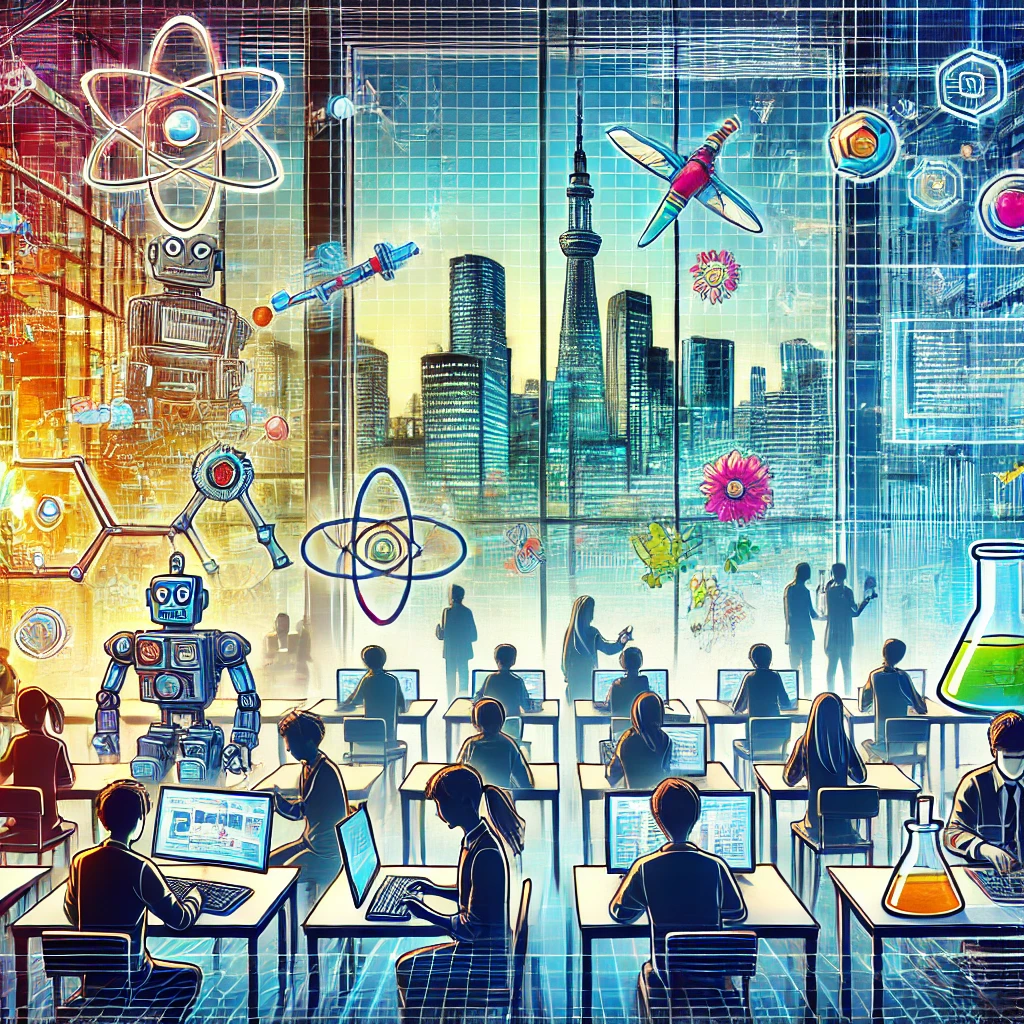Society 5.0時代を迎え、科学技術の発展はますます加速しています。人工知能(AI)やビッグデータ、IoTなどの先端技術が社会を変革する中、次世代の科学技術人材の育成は国家的な課題となっています。
東京都は、この課題に応えるため、体系的な理数教育プログラムを展開しています。スーパーサイエンスハイスクール(SSH)8校を頂点に、理数研究校24校、東京サイエンスハイスクール3校、そしてSIP拠点校8校など、重層的な教育支援体制を構築。「とことん研究に打ち込みたい」「医師を目指したい」「プログラミングを学びたい」など、生徒一人一人の興味や目標に応じた学習機会を提供しています。
本稿では、東京都が展開する理数教育の全体像と各プログラムの特徴を紹介します。未来の科学技術を支える人材育成の現場で、今、何が行われているのか――。理系進学を考える中学生や保護者の方々に、その選択肢の豊かさをお伝えします。
1. スーパーサイエンスハイスクール(SSH)- 理数教育の最高峰
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)とは?
文部科学省が指定する理数教育の最高峰プログラム。都内では8校が指定を受け、先進的な科学技術教育を展開しています。国際的に活躍できる科学技術人材の育成を目指し、独自のカリキュラム開発に取り組んでいます。
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けている高校は、大学の研究室での実験、企業との連携プロジェクト、海外の高校生との交流、科学コンテストへの参加、専門家による特別講義など他の高校では経験できない充実したプログラムを受けることができます。
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けている都立高校
- 日比谷高校:令和4年度~令和8年度(基礎枠・第4期)
- 小石川中等教育学校:令和4年度~令和8年度(基礎枠・第4期)
- 科学技術高校:令和3年度~令和7年度(基礎枠・第3期)
- 富士高校・附属中学校:令和3年度~令和7年度(基礎枠・第1期)
- 戸山高校:令和6年度~令和7年度(基礎枠・経過措置)
- 立川高校:令和5年度~令和9年度(基礎枠・第2期)
- 多摩科学技術高校:令和4年度~令和8年度(基礎枠・第3期)※科学技術人材育成重点枠(令和5年度~令和8年度)
- 国分寺高校:令和6年度~令和10年度(文理融合基礎枠・第1期)
🏫 高校生活をより充実させるために、今から学びの準備を
校風や特色を調べながら「この学校に入りたい」と思ったら、勉強のペースづくりを始めるチャンス。
以下の学習サービスを活用すれば、授業理解・内申対策・基礎力アップを自宅で進めることができます。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】![]()
👉 【費用重視】月額1,815円~効率的に予習・復習できる動画教材なら スタサプ ![]()
👉 【難関対策】難関校志望者にも信頼される通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【内申UP】内申・定期テスト対策を家庭でサポート 家庭教師のノーバス ![]()
👉 【体験無料】実際の教師による安心サポートなら 家庭教師ファースト ![]()
👉 【東大の力】日比谷・西・国立など難関都立を目指すなら現役東大生の家庭教師数最大規模【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の成果
令和5年度のSSH生徒研究発表会では、都立科学技術高校がポスター発表賞を、都立多摩科学技術高校が生徒投票賞を受賞するなど、着実な成果を上げています。
2. 東京サイエンスハイスクール:TSH – Society 5.0時代の人材育成
東京サイエンスハイスクール:TSHとは?
東京都は、Society 5.0時代に向けた革新的な理数教育を展開するため、独自の「東京サイエンスハイスクール」制度を設けています。この制度の特徴は、教科「情報」を軸とした理数教科間の連携と、教科「外国語」を活用した国際的な発信力の育成にあります。従来の教科の枠を超えた新たな教育実践システムを構築することで、変化の激しい現代社会で活躍できる人材の育成を目指しています。
プログラムの実施にあたっては、大学やNPO法人、企業との組織的な連携を通じて、実社会との接点を持った研究開発を推進しています。また、開発された教育実践システムは他の高等学校へと広げていく取り組みも行っており、東京都全体の教育レベルの向上を図っています。
プログラムの質を保証するため、学校教育の専門家や学識経験者で構成される運営指導委員会を設置し、第三者の視点から事業の評価を行っています。生徒たちは、Tokyoサイエンスフェアや「科学の甲子園東京都大会」、研究発表会などに参加することで、科学的探究心を育てています。
さらに、このプログラムは文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)への発展を視野に入れており、より高度な理数教育の実現に向けた準備を進めています。教科横断的な学びと実践的な活動を通じて、次世代の科学技術を担う人材を育成するとともに、その成果を広く共有することで、東京都全体の教育力向上に貢献しています。
東京サイエンスハイスクール:TSHの指定を受けている都立高校
3. 理数研究校 – 裾野を広げる24校体制
理数研究校とは?
東京都は、理数教育の更なる充実を目指し、24校を理数研究校として指定しています。このプログラムは、理数分野に興味を持つ生徒の裾野を広げるとともに、特に優れた才能を持つ生徒を見出し、その能力を伸ばすことを目的としています。
理数研究校では、三つの柱を中心とした特色ある教育活動を展開しています。第一の柱は研究活動の充実です。大学院生など専門知識を持つ指導者からの助言を受けながら、生徒たちは科学的な探究活動に取り組んでいます。また、理数教育の先進校との交流を通じて、生徒の視野を広げ、科学的に探究する能力と態度の育成を図っています。
第二の柱は、様々な科学コンテストへの参加です。東京都が主催する研究発表会や科学の甲子園東京都大会への出場を通じて、生徒たちは他校の仲間たちと切磋琢磨しながら成長を遂げています。このような競争的な環境は、生徒たちの学習意欲を高め、より高度な課題に挑戦する原動力となっています。
第三の柱として、フィールドワークや観察活動を重視しています。教室での学習にとどまらず、実際のフィールドでの観察や実験を通じて、生徒たちは理科や数学の実践的な理解を深めています。これらの課外活動は、理数分野への興味・関心をさらに高め、生徒の能力を多面的に伸ばす機会となっています。
このように、理数研究校は体系的なプログラムを通じて、次世代の科学技術を担う人材の育成に取り組んでいます。教室での学習と実践的な活動を組み合わせることで、生徒たちの科学的思考力と探究心を育てています。
理数研究校の指定を受けている都立高校(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
進学指導重点校
進学指導特別推進校
進学指導推進校
竹早高校、調布北高校、北園高校、日野台高校、小金井北高校、武蔵野北高校
その他高校
六本木高校、八潮高校、本所高校、小笠原高校、三鷹中等教育学校、狛江高校、田園調布高校、目黒高校、石神井高校、大泉高校、成瀬高校、府中東高校、立川国際中等教育学校
4. SIP(Scientific Inquiry Program)- 探究活動の拠点作り
SIP(Scientific Inquiry Programとは?
SIP拠点校は、理数分野に興味を持つ生徒たちの探究活動を支援する東京都の特色ある教育プログラムです。生徒個々の意欲向上と進路実現を支援するとともに、その教育ノウハウを都内の他の高等学校にも広く共有することで、東京都全体の理数教育の質の向上を目指しています。
プログラムは五つの重点的な取り組みで構成されています。第一に、大学教授等を招いた講演会や講義を実施し、生徒たちの課題発見・解決能力を育成しています。第二に、研究室や企業への訪問、フィールドワークなどの実地研修を行い、実践的な学びの機会を提供しています。
第三の特徴は、大学生や大学院生による継続的な課題研究指導です。専門知識を持つ若手研究者からの指導により、生徒たちの研究活動をより深化させています。さらに、都教育委員会主催の研究成果発表会や情報交換会での発表を通じて、生徒たちは他校との交流を深めています。
最後に、Tokyoサイエンスフェアや科学の甲子園東京都大会などへの参加を推進し、競技的な場面での経験を通じて学習意欲の向上を図っています。これらの包括的なプログラムにより、生徒たちの科学的探究心を育てるとともに、東京都全体の理数教育の発展に貢献しています。
SIP(Scientific Inquiry Program)の指定を受けている都立高校
- 青井高校:令和5年度~令和6年度 (第Ⅱ期)
- 浅草高校:令和5年度~令和6年度 (第Ⅱ期)
- 荻窪高校:令和5年度~令和6年度 (第Ⅱ期)
- 南平高校:令和5年度~令和6年度 (第Ⅱ期)
- 大森高校:令和6年度~令和7年度 (第Ⅲ期)
- 農芸高校:令和6年度~令和7年度 (第Ⅲ期)
- 若葉総合高校:令和6年度~令和7年度 (第Ⅲ期)
- 羽村高校:令和6年度~令和7年度 (第Ⅲ期)
5. チーム・メディカル – 医学部進学に特化したプログラム
チーム・メディカルとは?
チーム・メディカルは、医学部進学を目指す生徒たちのために都立戸山高校が実施する特別プログラムです。医師を志す生徒同士が互いに切磋琢磨し支え合う環境の中で、3年間一貫した育成プログラムを展開しています。単なる医学部合格のための受験対策にとどまらず、将来医師として社会貢献できる人材の育成を目指しています。
プログラムの特徴
医療への深い理解と使命感を育むため、以下のような特色ある活動を実施しています。
専門的な学習機会の提供
- 最先端医療に関する講演会
- 医学部教授による模擬授業
- 小論文指導、面接指導
- 医療に関する課題研究
実践的な体験活動
- 医学部キャンパス見学
- 病院での実地研修
- 現役医師との交流
- 医療現場の体験実習
学習成果
生徒たちからは、「人の命を救うことの責任の重さを実感した」「医師として信頼を得るためには、常に向上心を持ち続ける必要がある」といった感想が寄せられており、医療人としての倫理観や使命感の醸成につながっています。
プログラムを支える基盤
都立戸山高校は、明治21年(1888年)創立の伝統校で、進学指導重点校として、またスーパーサイエンスハイスクール(SSH)として高度な理数教育を展開してきました。この教育基盤の上に、チーム・メディカルは医療人材育成という特色あるプログラムを構築しています。
このように、チーム・メディカルは、高い志を持って医学を志す生徒たちを、知識・技能・人間性の面から総合的に支援する特色あるプログラムとして機能しています。

6.理数系の学科がある都立高校(立川高校・多摩科学技術高校・科学技術高校)
東京都には、理数系教育に力を入れた特色ある高校があります。その中でも特に注目すべきなのが、創造理数科を設置する2校と、理系専門高校2校です。
創造理数科を設置しているのは、立川高校と科学技術高校です。立川高校は多摩地区の進学指導重点校として知られ、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定も受けています。創造理数科では、理数に特化した専門的なカリキュラムを展開し、課題研究や探究活動を重視した教育を行っています。同じく創造理数科を持つ科学技術高校は、理工系の専門高校としても知られ、充実した実験・実習設備を活かした高度な理数教育を実施しています。
理系専門高校としては、都立科学技術高等学校と都立多摩科学技術高等学校の2校があります。科学技術高校では、情報科学科、物質工学科、環境化学科、機械システム工学科、電気電子工学科を設置し、専門的な実験・実習施設を完備しています。多摩科学技術高校も同様に、情報科学科、機械科、電気科、化学科を設け、実践的な技術教育を展開しています。両校ともSSH指定校として、先端的な理数教育にも取り組んでいます。
これらの学校では、充実した実験・実習環境を活かした特色ある教育活動を展開するとともに、大学や企業との連携も積極的に行っています。進路実現に向けては、理工系大学への進学指導や専門的な資格取得支援も充実しています。

💻 自分に合った勉強スタイルを見つけよう
塾・通信教育・家庭教師など、学び方はさまざま。
それぞれの特徴を知って、自分に合う方法を選ぶことが成績アップの近道です。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】
![]()
👉 【難関対策】難関校対策に定評のある通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【1対1】マンツーマンの個別指導で弱点克服 1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】 ![]()
👉 【東大の力】東大生講師から学べるオンライン指導 【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
👉 【内申UP】対面で安心して教わりたい人は 家庭教師のノーバス ![]()
東京都の理数教育システム – 多層的な人材育成の取り組み
東京都の理数教育システムは、生徒一人一人の興味や能力に応じた多層的な教育プログラムを展開しています。この体系的な取り組みは、文部科学省指定のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)を頂点としながら、各プログラムが互いに補完し合う重層的な構造を持っています。
SSHに指定された8校では、大学や研究機関との連携、海外研修、高度な課題研究など、最先端の理数教育が実践されています。一方、24校に及ぶ理数研究校では、大学院生による指導や科学コンテストへの参加を通じて、理数分野への興味を広く育んでいます。さらに、Society 5.0時代に向けた人材育成を目指す東京サイエンスハイスクールや、医学部進学を支援するチーム・メディカルなど、社会のニーズに対応した特色あるプログラムも用意されています。
このシステムの特徴は、生徒の興味や目標に応じた選択肢の豊富さにあります。「とことん研究に打ち込みたい」生徒はSSH校へ、「幅広く理系を学びたい」生徒は理数研究校へ、「IT・プログラミングに関心がある」生徒は東京サイエンスハイスクールへ、「医師を目指している」生徒は戸山高校のチーム・メディカルへ、といった具合に、それぞれの志向に合わせた進路選択が可能です。
また、SIP(Scientific Inquiry Program)拠点校では、探究活動の機会提供と継続的な指導を通じて、生徒の科学的思考力を育成しています。理数系専門学科を持つ高校では、創造理数科や専門学科で実践的な理数教育を展開し、将来の科学技術を担う人材の育成に力を入れています。
このような重層的な教育支援体制は、日本の科学技術の未来を支える人材育成の基盤として極めて重要な役割を果たしています。各プログラムが相互に刺激し合い、高め合うことで、東京都の理数教育は着実な発展を遂げています。様々な取り組みの成果は、生徒の研究発表会での受賞や、科学コンテストでの活躍となって表れており、プログラムの有効性を実証しています。
今後も、急速に変化する社会のニーズに応えながら、これらのプログラムはさらなる進化を遂げていくことでしょう。東京都の理数教育システムは、未来の科学技術イノベーションを担う人材の育成に向けて、着実に歩みを進めています。
難関校を目指すなら、自宅学習にも“本物の教材”を
「この高校に入りたい」――そう思ったとき、気になるのはやはり“受験への準備”。
自分のペースで本格的な受験対策がしたい中学生や、塾に通わずに質の高い学習を進めたいご家庭におすすめなのが【Z会の通信教育】です。
難関校対策に対応したハイレベルな教材と、記述力を伸ばす添削指導。
通信教育でありながら、学習習慣から答案力までしっかり鍛える仕組みが整っています。
本気で上位校を目指すなら、Z会という選択があります。
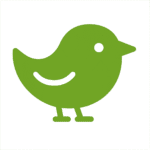 トリトリ
トリトリ部活も文化祭もひと段落。これからは志望校合格に向かってラストスパートをかける時期が来たよ!
秋は、学力を伸ばす絶好のタイミング。
Z会の通信教育〈高校受験コース〉なら、考えて「紙に書く」学びを通して、難関高校合格レベルへと実力を高められます。
苦手やレベルに合わせた個別プログラムで、定期テスト対策から入試対策までしっかりサポート。
今なら『英語Writingワーク』(学年別)と『自主学習の継続を後押しする保護者のサポートBOOK』をプレゼント中!
忙しい秋だからこそ、親子で「これからの学び」を見直すチャンスです。
\ 資料請求で2つの特典をプレゼント! /