「都立高校御三家」とは、東京都にある都立高校の中で特に進学実績、教育内容、伝統などにおいてトップクラスとされる3つの高校のことを指します。現代では、一般に「日比谷高校」「西高校」「国立高校」が該当します。これらの高校は長い歴史と厳しい入学選抜を経て、多くの優秀な生徒を輩出してきました。
「都立中高一貫校御三家」としてよく挙げられるのは、「小石川中等教育学校」「武蔵高等学校・附属中学校」「両国高等学校・附属中学校」の3校です。これらの学校は中学・高校の6年間を一貫した教育プログラムで運営しており、都内の公立中高一貫校の中でも特に高い進学実績を誇ります。
【都立高校御三家①】 東京都立日比谷高等学校
日比谷高校の創立経緯
都立日比谷高校は、1878年に旧東京府立第一中学校として設立されました。明治時代の教育改革の一環として、西洋の教育制度を参考にし、近代国家建設を担う人材を育成する目的で設立されました。日本の政治や経済のリーダーを輩出するためのエリート教育機関として、長年にわたって高い教育水準を維持しています。
日比谷高校の教育理念・スクールミッション
「自律的人格」「学習と教養」「責任と協調」「心身の健康」「文化と平和」を教育目標に、自主自律、文武 両道の精神を貫くとともに、学問の本質に触れる楽しさや知的好奇心を喚起する様々な取組を行い、21世紀 を逞しく切り拓くグローバル・リーダーとして活躍する人材を育成する
(日比谷高校学校案内より引用)
「自主自律」「知性と品性の融合」自主性や自立心を重んじ、生徒自身が自らの判断で行動し、自己の成長を追求することを奨励しています。また、学問と人間性の調和を図り、知識と品格を兼ね備えた人物の育成を目指しています。
日比谷高校の立地とアクセス
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-16-1 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、または「赤坂見附駅」からも徒歩圏内。 |
日比谷高校は、永田町という日本の政治の中心地に位置し、国会議事堂や首相官邸が近くにあります。この立地は、教育においても政治や社会についての関心を高める一助となっています。また、周囲にはビジネス街が広がり、都会的な環境の中で学びを深めることができる点が特徴です。
日比谷高校の行事や校風
自由で自主性を重んじる校風が特徴です。学業だけでなく、生徒が個々の興味や関心に基づいて自主的に活動できる環境が整っており、部活動や委員会活動も盛んです。
「星陵祭(文化祭)」「体育大会(体育祭)」「修学旅行」「臨海教室」など、さまざま行事が毎年開催されます。特に「星陵祭」は都内有数の盛り上がりを見せ、多くの来場者が訪れます。生徒たちは自主的に行事を企画・運営するため、学校行事を通じてリーダーシップや協力の精神を養うことができます。
歴史的に名高い人物を多数輩出しており、政治家、経済人、文化人など、日本社会におけるリーダーを育成してきた伝統があります。
日比谷高校の進学実績
都立日比谷高校は、日本の公立高校の中でも特に優れた大学進学実績を誇る教育機関です。2020年から2024年の現役生の合格実績を見ると、その卓越した教育成果が明らかです。
最難関とされる東京一工医(東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学、国公立医学部)には毎年100名以上の現役生が合格しています。2024年度には東京大学に52名、国公立大学医学部に28名が合格するなど、特筆すべき成果を上げています。
私立大学においても、早慶上理医(早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、私立医学部)に484名、GMARCH(学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)に181名が合格しており、幅広い進路選択を実現しています。
特筆すべきは、現役合格者の90%以上がGMARCH以上の難関大学に合格しているという点です。これは、生徒の高い学習意欲と教師陣の質の高い指導の結果と言えるでしょう。日比谷高校では、専門性の高い教師による充実した授業に加え、早期からの進路指導や個別サポートなど、きめ細かな進学指導体制が整っています。
こうした実績は、日比谷高校が日本の教育界において卓越した地位を占めていることを示しています。

【都立高校御三家②】 東京都立西高等学校
西高校の創立経緯
都立西高校は、 1937年に東京府立第十中学校として創設されました。戦後の学制改革に伴い、現在の東京都立西高等学校となり、その後は進学校としての地位を確立していきました。伝統を重んじながらも、常に新しい時代に適応するための教育を行っています。
西高校の教育理念・スクールミッション
【教育目標】心身ともに健全で、平和的・文化的な社会の向上発展に貢献し得る有為な人材を育てる。
【教育方針】国際社会で活躍できる器の大きな人間の育成
⇒「文武二道」「自主自律」「授業で勝負」
(西高校学校案内より引用)
文武両道を掲げ、豊かな教養と実践力を兼ね備えた生徒の育成を目指しています。質の高い授業を中心とした学習指導に加えて、キャリア教育や特別活動、国際交流にも力を入れており、生徒が多様な経験を通じて自らの成長を実感できる環境が整っています。また、卒業生による支援体制や特別な講座を通じて、学校外の学習機会も提供されている点が特徴的です。
西高校の立地とアクセス
| 住所 | 東京都杉並区宮前4-21-32 |
| 最寄り駅 | 京王井の頭線「久我山駅」から徒歩約15分、またはバスを利用。 |
杉並区の閑静な住宅街に位置し、自然環境に恵まれています。近くには善福寺川緑地公園があり、自然に囲まれた落ち着いた環境で学業に励むことができます。都会の喧騒を離れ、集中して学習できる環境が整っています。
西高校の行事や校風
体育祭、文化祭(記念祭)、合唱祭、修学旅行など行事が盛んです。特に「記念祭」は生徒主体のイベントであり、学校全体が一体となって企画から運営までを行います。
西高の行事は、自主性を重んじる校風に基づいており、生徒がリーダーシップや協力の精神を学ぶ場となっています。自由闊達な雰囲気があり、生徒の自主性や個性を尊重する校風です。生徒たちは、学問だけでなく、部活動や社会活動にも積極的に参加し、自らの意見を発信する機会を多く持っています。
また西高は、学問以外にも文化・スポーツ活動が盛んな学校として知られており、多彩な部活動が活発です。生徒同士が切磋琢磨し合う環境が整っています。
西高校の進学実績
都立西高校は、全国有数の進学校として知られ、難関大学への高い合格実績を誇っています。2020年から2024年の現役生の大学合格実績を見ると、その教育の質の高さが明確に表れています。
最難関と言われる東京一工医(東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学、国公立医学部)には、毎年30~50名の現役生が合格しています。2024年度には、東京大学に6名、京都大学に10名、一橋大学に9名が合格するなど、優れた成果を上げています。
私立大学においても、早慶上理医(早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、私立医学部)に203名、GMARCHに200名が合格しており、幅広い進路選択を実現しています。
特筆すべきは、現役合格者の77%以上がGMARCH以上の難関大学に合格しているという点です。また、延べ合格者数の約25%が東京一工医と旧帝大、早慶医に合格しており、日本トップクラスの大学への進学実績が顕著です。
西高校の特徴として、他の都立進学校に比べて京都大学への合格者が多い傾向が見られます。また、個別の進路指導や特別補習、頻繁な模試実施など、充実した受験サポート体制が整っていることも、この高い合格実績につながっていると言えるでしょう。

【都立高校御三家③】 東京都立国立高等学校
国立高校の創立経緯
1941年に東京府立第十九中学校として設立され、戦後に東京都立国立高等学校となりました。設立当初から、東京都郊外の閑静な住宅街に位置し、自然環境に恵まれた中で教育活動を行ってきました。特に学問に対する高い志と自由な校風で知られています。
国立高校の教育理念・スクールミッション
Critical Thinking(物事の本質を問い続け、粘り強く考える思考法)、
Creative Thinking(自らもつ知識同士や他者とのつながりによる新たな発想)、
Collaboration(互いに補完し、発展させるための協働)
を3つの柱として、多様な見方・考え方を学ぶことで、課題発見・解決力、創造性を持つ人材を育成します。
(国立高校学校案内より引用)
生徒は学業だけでなく、部活動や行事にも積極的に取り組み、全人格の成長を目指しています。代表的な行事には日本一の文化祭と言われる「国高祭」や「第九演奏会」があり、生徒主体で運営されています。
さらに、「理数研究校」や「英語教育研究推進校」として、理数や英語教育の強化も進められ、グローバル人材の育成に力を入れています。国立高校は、変化の激しい時代を生き抜くための「賢さ」「強さ」「優しさ」を兼ね備えた人材育成を目指し、今後も進化し続ける学校です。
国立高校の立地とアクセス
| 住所 | 東京都国立市中1-1-1 |
| 最寄り駅 | JR中央線「国立駅」から徒歩約15分。またはバスを利用。 |
国立駅から徒歩圏内の閑静な住宅街に位置し、落ち着いた環境で学ぶことができます。周辺には国立大学や文化施設も多く、文教地区として知られています。緑豊かな自然環境もあり、集中して学業に取り組むことができます。
国立高校の行事や校風
「文化祭」や「体育祭」、「第九演奏会」など、年間を通じて生徒が主体的に運営する行事が豊富です。特に「国高祭」は、地域住民や保護者も多数参加する大規模な文化祭として知られ、日本一の文化祭と評されることもあります。国立高校の文化の高さが感じられるイベントです。
また自由で自主性を重んじる校風が特徴です。生徒は自由に自らの興味を追求できる環境が整っており、授業だけでなく、課外活動や部活動に積極的に取り組む姿勢が見られます。
周囲の自然環境に恵まれ、落ち着いた学習環境が整っています。また、自由闊達な学風の中で、生徒が自己実現を目指すことができる教育が行われています。
国立高校の進学実績
都立国立高校は全国屈指の進学校としてしられ、生徒は「国高祭」という日本一とも称される文化祭に全力で取り組みながらも、国内最難関大学への高い進学実績を誇っています。2020年から2024年の現役生の大学合格実績を見ると、その教育の質の高さが明確に表れています。
最難関とされる東京一工医(東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学、国公立医学部)には、例年50人前後の現役生が合格しています。2024年度には、東京大学に11名、一橋大学に15名が合格するなど、優れた成果を上げています。特に、文系大学最高峰である一橋大学は国立高校と最寄り駅が同じJR国立駅であるためか、例年多くの合格者を輩出しています。
私立大学においても、早慶上理医(早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、私立医学部)に163名、GMARCHに223名が合格しており、幅広い進路選択を実現しています。
特筆すべきは、現役合格者の81%以上がGMARCH以上の難関大学に合格しているという点です。また、延べ合格者数の約24%が東京一工医と旧帝大、早慶医に合格しており、日本最難関の大学への進学実績が顕著です。
国立高校の特徴として、「授業を大切にする」方針のもと、土曜授業や長期休業中の集中講習、個別添削指導など、充実した学習支援体制が整っています。さらに、自習室の開放や卒業生による学習支援、大学や研究機関と連携した探究学習など、多面的な教育アプローチが高い合格実績につながっていると言えるでしょう。
このように、「都立高校御三家」とされる各校は、それぞれ独自の歴史と伝統を持ちながらも、進学実績や教育の質で共通して高い評価を得ています。

🏫 高校生活をより充実させるために、今から学びの準備を
校風や特色を調べながら「この学校に入りたい」と思ったら、勉強のペースづくりを始めるチャンス。
以下の学習サービスを活用すれば、授業理解・内申対策・基礎力アップを自宅で進めることができます。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】![]()
👉 【費用重視】月額1,815円~効率的に予習・復習できる動画教材なら スタサプ ![]()
👉 【難関対策】難関校志望者にも信頼される通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【内申UP】内申・定期テスト対策を家庭でサポート 家庭教師のノーバス ![]()
👉 【体験無料】実際の教師による安心サポートなら 家庭教師ファースト ![]()
👉 【東大の力】日比谷・西・国立など難関都立を目指すなら現役東大生の家庭教師数最大規模【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
都立中高一貫(附属)の御三家は?
【都立中御三家①】都立小石川中等教育学校
東京都立小石川中等教育学校は、東京都文京区に位置する完全中高一貫校です。1918年に東京府立第五中学校として創立され、1950年に東京都立小石川高等学校と改称、2006年に中等教育学校として再編されました。理化学教育に重点を置き、大正リベラリズムの影響を受けた自由でアカデミックな校風が特徴であり、初代校長である伊藤長七が掲げた「立志・開拓・創作」という三つの校是に基づいた教育方針が現在も続いています。これは、生徒たちが自ら志を立て、道を切り開き、新しい文化を創造することを奨励する理念です。
特に理化学教育においては、物理・化学・生物・地学の各分野にわたる高度な実験設備を備え、授業の約7割を実験や実習に当てる独自の教育方針を採用しています。授業では、学校独自の教材やプリントが中心に使われ、白衣や実験用ゴーグルが必要とされるほど、実験を重視したカリキュラムが組まれています。この実験に基づく学びを通じて、生徒たちは科学的な考察力を磨き、自主的に課題を探求する姿勢を身につけていきます。また、優れた研究成果を挙げた生徒には「伊藤長七賞」が授与されるなど、学問に対する高い意識が学校全体に浸透しています。
文系・理系を問わず、全ての生徒がバランスの取れた教養を身につけることを目指す「小石川教養主義」も学校の特徴です。特に後期課程では、全国的に履修機会が減少している地学を必修科目として設定するなど、幅広い教養を重視しています。また、6年次には生徒の希望に応じた「特別講座」が開講されており、実験に特化した「生命科学基礎実習」や「アジア論概説」など、多岐にわたる選択科目が提供されます。
行事においても、生徒の自主性が重んじられています。芸能祭、体育祭、創作展の三大行事は、9月に集中的に行われ、特に創作展では生徒が自ら企画・運営し、演劇や展示を行います。この期間中は授業が一切行われず、生徒たちは完全に行事に没頭することができるため、強い自主性とリーダーシップが育まれます。生徒自治会も積極的に学校運営に関与しており、予算や運営に関する最終決定は生徒総会で行われます。
また、小石川中等教育学校では、国際的な視野を広げるための教育も行われています。英語教育においては、ネイティブ教員による授業やレコード教材を活用した学習が行われ、生徒は総合的な語学力を養っています。さらに、3年次にはオーストラリアへの語学研修が実施され、現地でのホームステイを通じて異文化に触れる機会が提供されています。
こうした自由でアカデミックな環境の中で、生徒たちは自主性を尊重されながら、理化学や人文科学の幅広い教養を身につけ、創造的で実践的な学びを追求しています。都立中高一貫校の中でも最難関校の一つとして、毎年多くの受験生からの高い人気を誇り、これからも次世代を担う人材を育成していくことでしょう。

【都立中御三家②】都立武蔵高等学校・附属中学校
東京都立武蔵高等学校・附属中学校は、東京都武蔵野市に位置する完全中高一貫校です。前身は1940年に設立された府立第十三高等女学校であり、東京多摩地域における伝統的な公立校の一つとして発展してきました。2008年度から附属中学校が併設され、中高一貫教育体制に移行。2021年度からは高校からの生徒募集を停止し、完全な中高一貫校となっています。校風は「自主自律」と「文武両道」を重んじ、生徒の自主性を育む自由な環境が特徴です。特に高校では制服がなく、生徒たちは自己管理のもとで自由な学校生活を送っています。
教育面では、中学1年次から習熟度別や少人数授業が導入されており、個々の生徒の理解度や学力に応じた学習が展開されています。また、独自科目「地球学」では、社会科学と自然科学を横断する学びを提供し、地球規模で物事を考える力を育むことを目指しています。地球学の学びは、中学3年次の中間発表と高校2年次の最終発表へとつながり、生徒は大学レベルの研究に取り組む機会を得ます。近年では持続可能な開発目標(SDGs)への関心が高まり、これに関連したテーマでの研究が進められています。
武蔵高校では行事も盛んで、三大行事として6月に行われる音楽祭、9月の体育祭と文化祭があります。音楽祭は、学校伝統の行事として生徒たちがクラスごとに合唱を披露し、音楽系部活動の発表も行われます。中高合同で開催される音楽祭は、生徒の自主運営で進行し、クラスごとの衣装やパフォーマンスに工夫が凝らされる点が魅力です。また、体育祭では5つの団に分かれて団体競技が繰り広げられ、競技の他にも大きな団旗のデザインが競われます。文化祭はクラスや部活動が展示や発表を行い、多くの来場者を迎える行事で、準備期間は夏休み明けから始まり、クラスごとの企画に生徒たちは熱心に取り組みます。
文化祭の運営は、生徒主体の文化祭実行委員会(通称「文実」)が担い、企画や予算管理、会場設営など多岐にわたる業務を行います。文実は企画班、会場班、会計班、食品班などの班に分かれ、それぞれが役割を果たしながら文化祭を成功に導きます。コロナ禍以前と以後で運営方法が若干異なるものの、基本的な自主運営の方針は変わらず、各班が協力しながら文化祭を作り上げています。
武蔵高校の教育目標は「豊かな知性と感性」「健康な体と心」「向上進取の精神」であり、学問だけでなく、生徒の精神的・身体的な成長も重視しています。部活動も活発で、体育系や文化系のクラブ活動が幅広く展開されています。特に中高合同で活動する吹奏楽部や室内楽部、合唱部は、音楽祭や文化祭でその成果を披露する機会が多く、生徒たちの音楽的な才能が育まれています。
校舎は、広々としたキャンパスに緑が多く、学びの環境としても恵まれています。また、制服は附属中学でのみ採用されており、国連ブルーを基調としたデザインが特徴です。女子生徒はスラックスを着用することも認められており、制服においても生徒の自主性が尊重されています。
東京都立武蔵高等学校・附属中学校は、自由な校風のもとで生徒の自主性と学問への探求心を育む場として、多摩地域の公立校の中でも高い評価を受けています

【都立中御三家③】都立両国高等学校・附属中学校
東京都立両国高等学校・附属中学校は、東京都墨田区江東橋に位置する完全中高一貫校です。1901年に東京府第一中学校の分校として創立され、翌年「東京府立第三中学校」として独立しました。その後、1950年に「東京都立両国高等学校」と改称され、2006年には附属中学校を設置して中高一貫校に移行しました。2022年には高校からの生徒募集を停止し、完全な中高一貫教育体制を確立しています。
校風は創立当初から「自律自修」という校訓に基づき、厳格な規律を重んじる一方で、生徒の自主性を尊重しています。この精神は初代校長の八田三喜が提唱し、現在まで受け継がれています。特に1950年代から1960年代にかけては、東京大学への合格者を多数輩出し、学区内でトップクラスの進学校として評価されました。越境通学者も多く、広い地域から生徒が集まりました。中高一貫校化に伴い、より効率的な教育体制が整えられ、「予備校不要」を掲げた充実した受験指導が行われています。
両国高等学校・附属中学校は、学問に対する深い探求心を育む教育方針が特徴です。特に国語教育に力を入れており、芥川龍之介や堀辰雄といった文芸界の著名人を輩出しています。中学1年から作文や論文の執筆が求められ、中学3年では高校レベルの評論文の読解にも挑戦します。この「書かせる教育」は、文章力や批判的思考力を高めるものとして生徒に浸透しており、出版活動も活発です。生徒会が発行する『365日』や、教員による学術誌『三高教室』はその代表的な成果です。
語学教育にも力を入れており、中学3年と高校3年では「実践英語」が必修となっています。特に中学生による英語劇は、両国祭の目玉の一つであり、英語学芸大会でも高い評価を受けています。生徒たちは語学力だけでなく、国際的な視野も広げていきます。
また、「勉強の両国」として受験指導にも定評があり、補習や長期休業中の講習が充実しているほか、成績上位者の張り出しや学習状況の調査など、生徒の学習意欲を高める工夫がなされています。2005年からは土曜授業が復活し、効率的な学習環境が整っています。
行事としては、9月に行われる両国祭があり、中高合同での文化祭は大いに盛り上がります。中学生による英語ミュージカルや、クラスごとの演劇、展示が行われ、外部投票による表彰も実施されます。また、体育祭では赤・青・黄の三軍に分かれて競技が行われ、応援合戦も見どころです。合唱コンクールも大きなイベントで、「ティアラこうとう」で行われるこのイベントではクラス対抗で競い合います。
校舎は築44年を超え、都立高校の中でも古い部類に入りますが、設備改善が進められ、2024年度には個別のエアコンが導入されるなど、快適な学習環境の整備が進んでいます。こうした環境の中で、両国高等学校・附属中学校は、生徒たちに充実した学びの場を提供し続けています。

都立中学御三家も高校御三家に負けず劣らず素晴らしい学校
総じて、都立中学御三家は、それぞれが独自の教育方針と魅力を持ち、学力だけでなく、個々の生徒の個性や自主性を育む教育を行っています。
- 理数系の強化を重視し、難関大学合格実績では日比谷に比肩する小石川
- 「実践英語」「考える国語」など言語能力の育成に特色のある両国
- 独自科目「地球学」と自由な校風のもとで探求型学習を行う武蔵
と、これにより、卒業生は学問的な成果だけでなく、社会に出てもリーダーシップや問題解決力を発揮できる人材へと成長しています。
トップ校を目指すあなたに。自宅でできる“本格的な勉強”があります
「この高校に入りたい」――そう思ったとき、気になるのはやはり“受験への準備”。
自分のペースで本格的な受験対策がしたい中学生や、塾に通わずに質の高い学習を進めたいご家庭におすすめなのが【Z会の通信教育】です。
難関校対策に対応したハイレベルな教材と、記述力を伸ばす添削指導。
通信教育でありながら、学習習慣から答案力までしっかり鍛える仕組みが整っています。
本気で上位校を目指すなら、Z会という選択があります。
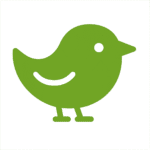 トリトリ
トリトリ部活も文化祭もひと段落。これからは志望校合格に向かってラストスパートをかける時期が来たよ!
秋は、学力を伸ばす絶好のタイミング。
Z会の通信教育〈高校受験コース〉なら、考えて「紙に書く」学びを通して、難関高校合格レベルへと実力を高められます。
苦手やレベルに合わせた個別プログラムで、定期テスト対策から入試対策までしっかりサポート。
今なら『英語Writingワーク』(学年別)と『自主学習の継続を後押しする保護者のサポートBOOK』をプレゼント中!
忙しい秋だからこそ、親子で「これからの学び」を見直すチャンスです。
\ 資料請求で2つの特典をプレゼント! /

