都立西高校の2025年度大学合格実績は、最難関大学への回帰と明確な「選択と集中」が特徴となっています。現役合格者の約77%が難関大学に集中し、特に最難関国公立大学と早慶の回復が顕著です。
東京一科医は前年比+10人の45人、早慶は合計139人と前年比+32人の大幅増を記録しました。一方でGMARCH内では明治大学が95人と突出する「明治一強」状態となり、中央大学など他校は軒並み減少しています。また関東主要国公立大学が23人、地方国公立大学が12人と健闘し、進学先の多様化も進行しています。
全体として国公立合格率37.1%、難関私立合格率47.7%という高水準を維持し、難関大学への高い合格力を示した進学実績といえます。特に「最上位層」と「明治大学」への集中という二極化傾向が鮮明となり、上位校への効果的な進学指導の成果が表れています。
入試に向けて、過去問に取り組む時期が近づいてきましたね。都立高校入試の「共通問題」と「西高校」の過去問を用意しました。
2019年~2025年(昨年度)の全教科の問題を掲載し、すべての問題にわかりやすい解説つき。
各教科の出題傾向と対策、公立高校合格のめやす、選抜のしくみ、入試情勢など、受験に役立つ情報が1冊にまとめられています。
👉【2026年度入試対応】西高校の過去問はこちら
👉【2026年度入試対応】都立高校共通問題の過去問はこちら
【2025年度】都立西高校の最難関国公立大学(東京一科+国公立医学部)合格者分析
【2025年度】最難関国公立大学(東京一科+国公立医学部)合格者数と現役合格者前年比
| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 10人 | (+4人) | 9人 | 19人 |
| 京都大学 | 13人 | (+3人) | 7人 | 20人 |
| 一橋大学 | 11人 | (+2人) | 3人 | 14人 |
| 東京科学大学 (旧東京工業大学) | 8人 | (+4人) | 1人 | 9人 |
| 国公立大学医学部 | 3人 | (▲3人) | 10人 | 13人 |
| 合計(医学部重複除く) | 45人 | (+10人) | 30人 | 74人 |
【2025年度】最難関国公立大学(東京一科+国公立医学部)合格者の大学別分析
東京大学
現役合格者が前年比+4人と大幅に増加し、10人になりました。浪人合格者も9人と堅調で、合計19人の合格者を出しています。現役合格者数が浪人を上回ったのは注目すべき点です。
京都大学
合計20人と最難関大学の中で最多の合格者数を誇ります。現役13人(前年比+3人)と着実に伸びており、現役合格の強さが目立ちます。
一橋大学
現役合格者が11人(前年比+2人)と増加傾向にあり、浪人3人を大きく上回っています。社会科学系最難関大学への現役合格実績が安定しています。
東京科学大学(旧東京工業大学)
現役合格者が8人(前年比+4人)と2倍に増加しており、理系教育の成果が顕著に表れています。浪人は1人のみで、現役での合格に強みがあります。
国公立大学医学部
唯一現役合格者が減少(前年比-3人)している一方、浪人合格者が10人と多いのが特徴です。医学部については浪人してでも志望を貫く傾向が見られます。
全体的な傾向・特徴
- 現役合格強化の成果: 医学部を除く全大学で現役合格者が増加(計+13人)しており、学校の進学指導の成果が表れています。
- 東大・東京科学大学の伸び: 特に東大と東京科学大学(旧東工大)での現役合格者が各4人増と顕著に伸びており、文理両方で最上位層の底上げが進んでいます。
- 医学部と他学部の対照的傾向: 医学部では浪人合格者が現役の3倍以上と、他大学とは逆の傾向を示しています。医学部進学には浪人を視野に入れた長期的戦略が依然として重要であることを示唆しています。
- 現役と浪人の比率: 現役45人対浪人30人(比率約3:2)と、現役合格の割合が高まっています。特に一橋大学や東京科学大学では現役合格者が浪人を大きく上回っています。
- 総合力の向上: 前年比+10人の増加は、都立西高校の進学実績が全体的に向上していることを示しており、特に「現役での合格」という点で躍進していると言えます。
都立西高校の最難関国公立大学(東京一科+国公立医学部)の現役合格者数推移|2020年~2025年


大学別傾向
東京大学
- 変動の激しさ: 2022年の16人(5.1%)をピークに大きく変動。2024年に最低の6人(1.9%)まで落ち込むも、2025年は10人(3.3%)と回復傾向。
- 復調の兆し: 2024年から2025年にかけて実数・比率ともに約1.7倍に増加しており、V字回復の兆しが見られる。
京都大学
- 着実な成長: 2020年の4人(1.3%)から大きく成長し、2025年は13人(4.3%)と高水準を維持。
- 安定した強さ: 2022年以降、東大を上回る実績を継続しており、西高の京大対策の強さが際立つ。
一橋大学
- 安定した実績: 6年間を通じて比較的安定した合格者数を維持。2021〜2023年は13〜15人の高水準。
- 回復傾向: 2024年に9人(2.9%)まで落ち込むも、2025年には11人(3.6%)と回復し、社会科学系への強みを維持。
東京科学大学(旧東京工業大学)
- V字回復: 2024年の4人(1.3%)から2025年は8人(2.6%)と倍増し、過去最高の比率を達成。
- 理系強化: 比率で見ると2020年の0.9%から2025年の2.6%と約3倍に成長しており、理系教育の充実が顕著。
国公立医学部
- 不安定な推移: 最も変動が大きい分野で、2023年の7人(2.2%)をピークに2025年は3人(1.0%)と低調。
- 課題分野: 2025年は他大学が回復傾向にある中で唯一低迷しており、医学部対策が課題と言える。
全体的な傾向と特徴
- サイクル性: 2022年をピーク(54人・17.2%)とした波があり、2024年に底(35人・11.1%)を打った後、2025年は回復期(45人・14.9%)に入っている。
- 2025年の回復: 2024年の現役合格者総数35人から2025年は45人へと約30%増加。特に東大、京大、東京科学大学の回復が顕著。
- 卒業生数減少下での健闘: 卒業生数が2020年の318人から2025年は302人と減少する中、合格比率は2020年の11.9%から2025年は14.9%へと向上。
- 理系の躍進: 特に東京科学大学の成長が目立ち、理系最難関大学への合格実績が向上。京大も理系学部の合格者を含め好調。
- 医学部の課題: 唯一2025年に回復が見られない分野であり、医学部進学指導に課題がある可能性。
- 2025年の評価: 2024年の低迷から見事に立ち直り、2021年水準(47人・14.9%)に近い実績(45人・14.9%)を達成。特に東大・京大・東京科学大学の三大学で合計31人の現役合格者を出したのは特筆すべき。
- 進学指導の成果: 2024年からの回復は、進学指導の見直しや強化の成果が表れた可能性が高く、今後も継続的な向上が期待できる。
🧠 難関都立を目指す中高生に人気の家庭教師サービス
難関大学へ多くの合格者を輩出するこの高校に合格するには、日々の学習内容に加えて、入試レベルに合わせた指導が不可欠です。東大・早慶などの現役大学生講師による【訪問授業】or【オンライン個別指導】で、志望校対策を強化してみませんか?
👉
現役東大生の家庭教師数最大規模【オンライン東大家庭教師友の会】
![]()
👉 現役東大生の家庭教師数最大規模の【東大家庭教師友の会】
![]()
【2025年度】都立西高校の旧帝大(東大・京大除く)+TOCKY合格者数分析
【2025年度】旧帝大(東大・京大除く)合格者数と現役合格者前年比
| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 11人 | (+3人) | 8人 | 19人 |
| 東北大学 | 6人(医1) | (▲2人) | 5人 | 11人 |
| 名古屋大学 | 1人 | (▲1人) | 0人 | 1人 |
| 大阪大学 | 1人 | (▲2人) | 0人 | 1人 |
| 九州大学 | 3人(医1) | (+3人) | 0人 | 3人 |
| 合計 | 22人 | (+1人) | 13人 | 35人 |
【2025年度】TOCKY合格者数と現役合格者前年比
| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |
|---|---|---|---|---|
| 筑波大学(T) | 3人 | (▲2人) | 2人 | 5人 |
| お茶の水女子大学(O) | 1人 | (▲3人) | 1人 | 2人 |
| 千葉大学(C) | 3人 | (+1人) | 3人 | 6人 |
| 神戸大学(K) | 0人 | ー | 0人 | 0人 |
| 横浜国立大学(Y) | 5人 | (▲2人) | 3人 | 8人 |
| 合計 | 12人 | (▲6人) | 9人 | 21人 |
【2025年度】難関国公立(旧帝大・TOCKY)合格者の大学別分析
旧帝大(東大・京大除く)
大学別傾向
- 北海道大学: 現役11人(前年比+3人)、浪人8人と最多の合計19人を誇る。現役合格者が大幅に増加し、地方旧帝大で圧倒的な存在感。
- 東北大学: 現役6人(前年比△2人)、浪人5人の計11人。減少傾向にあるものの、安定した合格実績を維持。
- 九州大学: 現役3人(前年比+3人)と大幅増加。前年0人から一気に3人へと躍進し、九州地方進学の新たな選択肢に。
- 名古屋大学・大阪大学: どちらも現役1人(前年比△1人、△2人)と低迷。特に大阪大学は前年から2人減と苦戦。
全体的特徴
- 堅調な実績: 現役22人(前年比+1人)と微増。最難関校の回復と連動した堅調さが見られる。
- 2大学への集中: 北海道大学・東北大学で合計30人と全体の約86%を占め、「北東」に集中。
- 現浪比率: 現役22人対浪人13人(比率約5:3)と現役優位の傾向。
TOCKY大学の分析
大学別傾向
- 横浜国立大学(Y): 合計8人と最多の合格者数を誇るが、現役は前年比△2人と減少。現役5人・浪人3人とバランスが取れている。
- 千葉大学(C): 唯一現役合格者が増加(+1人)した大学。現役3人・浪人3人と同数で、全体で6人の安定した実績。
- 筑波大学(T): 前年比△2人と大幅減少したものの、現役3人・浪人2人の計5人の合格者を確保。
- お茶の水女子大学(O): 現役合格者が前年比△3人と大きく減少し、女子難関大学への進学に課題。
- 神戸大学(K): 現役・浪人ともに0人と厳しい結果。地理的要因も影響していると考えられる。
全体的特徴
- 全体的な低迷: 現役12人(前年比△6人)と大幅に減少。先に見た最難関大学とは対照的な結果。
- 現浪比率: 現役12人対浪人9人(比率約4:3)と比較的バランスが取れている。
- YCTの優位性: 横浜国立・千葉・筑波の3大学で合計19人と大半を占める。
旧帝大+TOCKYの総合的な考察
- 地域的な特性: 北海道大学・東北大学への強さと、関西圏(神戸・大阪)への弱さが際立つ。
- TOCKY低迷と旧帝大堅調の対比: TOCKYが全体的に低迷する一方で、旧帝大は堅調であり、難易度の高い大学への挑戦姿勢がうかがえる。
- 現役合格の二極化: 最難関・旧帝大では回復傾向、TOCKYでは減少傾向と異なる動きを示している。西高の進学指導が最難関大学に重点を置いている可能性。
- 北海道大学の突出: 北海道大学への合格者数は東大・京大と遜色ない水準であり、同校の特色ある進路選択を反映。
- 地方国立大学への分散: 九州大学の躍進に見られるように、進学先の選択肢が多様化している兆候も。
都立西高校は2025年度、最難関大学と旧帝大で回復傾向を示す一方、TOCKY大学では苦戦している現状が浮き彫りになりました。
都立西高校の難関国公立大学(旧帝大+TOCKY)の現役合格者数推移|2020年~2025年



旧帝大(東大・京大除く)への現役合格者の推移
全体傾向
- U字型の回復傾向: 2020年27人(8.5%)→2023年13人(4.2%)と減少後、2025年22人(7.3%)と回復。
- 医学部合格者: 2025年は2人と回復傾向。
- 最難関大学との対照的動き: 2022-23年に最難関大学が好調だった時期に旧帝大は低迷、2024-25年は逆に回復する相反する動き。
大学別推移
- 北海道大学: 非常に安定した強さを誇り、2025年は11人(3.6%)で6年間の最高値を更新。
- 東北大学: 変動はあるものの、2020年9人→2025年6人と比較的安定。
- 大阪大学: 2020年6人(1.9%)と好調だったが、徐々に減少し2025年は1人(0.3%)と低迷。
- 九州大学: 年度による変動が大きく、2022年0人から2025年は3人(1.0%)と回復。
- 名古屋大学: 合格者がほとんどない状態が続き、2024年2人(0.3%)が最高値。
TOCKY(筑波・お茶・千葉・神戸・横国)の経年推移
全体傾向
- 長期的な減少傾向: 2020年の23人(7.2%)から2025年は12人(3.8%)と約半減。
- 医学部合格者: 医学部合格者も2022年の2人をピークに2025年は0人に。
- 時系列変動: 2020→2023年は20人台で推移していたが、2024年から18人、2025年は12人と急落。
大学別推移
- 横浜国立大学: 2020年11人、2021年12人と非常に強かったが、2022年以降は一桁に落ち込み。2025年は5人(1.7%)と2020年の半分以下に。
- 筑波大学: 2022年9人(2.9%)をピークに大幅減少。2025年は3人(1.0%)と低調。
- 千葉大学: 2023年8人(2.6%)をピークに減少し、2025年は3人(1.0%)まで落ち込み。
- お茶の水女子大学: 2020年から2024年まで3〜4人で安定していたが、2025年は1人(0.3%)に急減。
- 神戸大学: 6年間一貫して0人と実績なし。
総合分析と特筆すべき傾向
- 旧帝大とTOCKYの二極化
- 2025年は旧帝大22人(7.3%)対TOCKY12人(3.8%)と、明確な二極化が進行。
- 2020年は旧帝大27人(8.5%)、TOCKY23人(7.2%)と拮抗していた状況から大きく変化。
- 北海道大学への集中
- 2025年は北海道大学だけで11人と、TOCKY5大学の合計12人とほぼ同数。
- 西高生の北大志向が顕著に表れている。
- 卒業生数減少下でのTOCKY苦戦
- 卒業生数の減少(318人→302人)を考慮しても、TOCKYの現役合格率は7.2%→3.8%と大幅減少。
- 一方、旧帝大は8.5%→7.3%と微減に留まっている。
- 地理的傾向の明確化
- 関東圏のTOCKY大学よりも北海道・東北の旧帝大への進学傾向が強まる。
- 関西圏の大阪大学・神戸大学への進学は極めて少数。
- 旧帝大の底堅さ
- 2023年を底に着実に回復し、2025年は2021年水準まで戻す。
- 特に北海道大学は2020年からほぼ一貫して合格実績を伸ばす。
- 進学指導の変化
- TOCKYから最難関・旧帝大へと進学指導の重点がシフトしている可能性。
- 特に2025年は最難関校と旧帝大の回復が顕著な一方、TOCKYは大幅減。
- 全体の長期的推移:
- グラフの折れ線(現役に占める比率)を見ると、2020年15.7%から2025年11.1%と下降傾向。
- 特にピークの2020年から2025年までで約30%の低下が見られる。
西高の進学実績は、全体としては減少傾向にあるものの、最難関・旧帝大への合格を重視する方向性へと変化しており、特に北海道大学への強さが際立っています。TOCKY大学への現役合格者減少は進学指導の優先順位変更を反映していると考えられます。
🏫 高校生活をより充実させるために、今から学びの準備を
校風や特色を調べながら「この学校に入りたい」と思ったら、勉強のペースづくりを始めるチャンス。
以下の学習サービスを活用すれば、授業理解・内申対策・基礎力アップを自宅で進めることができます。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】![]()
👉 【費用重視】月額1,815円~効率的に予習・復習できる動画教材なら スタサプ ![]()
👉 【難関対策】難関校志望者にも信頼される通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【内申UP】内申・定期テスト対策を家庭でサポート 家庭教師のノーバス ![]()
👉 【体験無料】実際の教師による安心サポートなら 家庭教師ファースト ![]()
👉 【東大の力】日比谷・西・国立など難関都立を目指すなら現役東大生の家庭教師数最大規模【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
【2025年度】都立西高校の関東主要国公立大学合格者分析
【2025年度】関東主要国公立大学合格者数と現役合格者前年比
| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城大学 | 0人 | – | 0人 | 0人 |
| 宇都宮大学 | 0人 | – | 0人 | 0人 |
| 群馬大学 | 0人 | – | 0人 | 0人 |
| 埼玉大学 | 0人 | (▲1人) | 0人 | 0人 |
| 東京科学大学 (旧東京医科歯科大学) | 0人 | – | 0人 | 0人 |
| 東京藝術大学 | 0人 | – | 1人 | 1人 |
| 電気通信大学 | 0人 | (▲4人) | 0人 | 0人 |
| 東京外国語大学 | 5人 | (▲2人) | 0人 | 5人 |
| 東京学芸大学 | 1人 | (▲2人) | 1人 | 2人 |
| 東京農工大学 | 9人 | (▲1人) | 4人 | 13人 |
| 東京海洋大学 | 0人 | – | 0人 | 0人 |
| 東京都立大学 | 8人 | (+3人) | 1人 | 9人 |
| 横浜市立大学 | 0人 | – | 0人 | 0人 |
| 関東主要国公立大学_合計 | 23人 | (▲7人) | 7人 | 30人 |
大学別の傾向
東京農工大学
- 圧倒的な存在感: 現役9人(前年比△1人)、浪人4人の計13人と、関東圏主要大学の中で最多。
- 理系進学の中核: 東工大(東京科学大学)に次ぐ理系国公立大学として重要な位置づけ。
東京都立大学
- 唯一の増加: 現役8人(前年比+3人)と唯一の増加傾向。地元都立大学として存在感を増している。
- 安定した実績: 浪人は1人と少なく、現役中心の実績。
東京外国語大学
- 語学特化の伝統: 現役5人(前年比△2人)と一定の実績を維持。
- 現役のみの実績: 浪人合格者がおらず、語学系は現役志向。
電気通信大学
- 急激な落ち込み: 現役0人(前年比△4人)と大幅に減少。理系特化型大学としての魅力が低下している可能性。
東京学芸大学
- 教員養成系の低調: 現役1人(前年比△2人)と減少。教員志望者の減少か、別ルートでの進学を示唆。
その他の国公立大学
- 実績皆無: 茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、東京海洋大学、横浜市立大学は現役・浪人とも0人。
- 医歯系も低調: 東京科学大学(旧東京医科歯科大学)も0人。医学部志望者は他大学に集中。
全体的な傾向と特徴
- 大幅な減少: 現役23人(前年比△7人)と大きく減少。最難関・旧帝大が回復する中、関東圏主要大学は逆に減少。
- 「農都外」への集中: 東京農工大・都立大・外国語大の3校で現役22人(全体の約96%)を占め、進学先の極端な偏りが見られる。
- 実学志向の顕著化: 農工大(農学・工学)や都立大(幅広い実学系学部)など、明確な専門性を持つ大学への進学が中心。
- 地域的な偏り: 埼玉大学、茨城大学、宇都宮大学など東京以外の関東圏大学への進学はほぼ皆無。東京一極集中の傾向。
- 都立大学の特異な伸び: 唯一前年比増加の都立大学は、都立高校からの進学ルートとして存在感を増している。地元志向の高まりも示唆。
- 最難関・旧帝大シフト: 最難関大学や旧帝大への合格者が回復する一方で関東圏主要大学が減少していることから、進学指導が上位層重視にシフトしている可能性。
- 「中間層」の空洞化: 最難関・旧帝大とこれらの主要大学の間に位置するTOCKY大学も減少しており、「二極化」が進んでいる。
都立西高校の2025年度国公立大学への進学実績は、「最難関・旧帝大」とその他の「関東圏主要大学」という二極化が進み、特に「農都外」3校への集中が顕著になっています。一方で、多くの関東圏主要大学では合格者がいないか大幅に減少しており、進学指導の方針変更や生徒の志望傾向の変化が表れていると考えられます。
都立西高校の関東主要国公立大学の現役合格者数推移|2020年~2025年


全体傾向
- U字型の変動: 関東主要国公立大学合格者数は2020年の25人(7.9%)→2022年18人(5.7%)と減少後、2024年30人(7.6%)まで回復し、2025年は23人(7.6%)と微減。
- 比率の安定: 卒業生数が318人から302人へと減少する中、現役合格率は2024-25年に7.6%で安定。実数は減少しても質は維持。
- 入試難度の変化: 最難関・旧帝大とTOCKYが低迷する中で関東主要国公立が健闘しており、入試難度の変化に対応した進路指導の成果。
大学別の経年変化
特徴的な推移を示す大学
- 東京都立大学
- 着実な成長: 2020年4人(1.3%)→2025年8人(2.6%)と右肩上がりの増加。
- 一貫した強化: 6年間で唯一ほぼ毎年増加または維持を続けている。
- 都立高校からの進学ルートとして重視されている可能性。
- 東京農工大学
- 激しい変動: 2020年9人→2023年3人→2024年10人→2025年9人と大きく上下。
- 直近2年は高水準: 2024-25年は比率3.0%で安定し、理系の中核大学として定着。
- 東京外国語大学
- 緩やかな減少: 2021年8人(2.5%)をピークに2025年5人(1.7%)と漸減。
- 言語系志望者の減少または他大学へのシフト。
- 電気通信大学
- 急激な低下: 2024年4人から2025年0人へと急減。
- 理系志望者の東工大(東京科学大学)または東京農工大へのシフト。
一貫して実績のない大学
- 茨城・宇都宮・群馬・横浜市立大: 6年間一貫して0人。
- 東京海洋大学: 同様に6年間0人。
- 埼玉大学: 2024年のみ1人の実績。
地域的特徴とその変化
- 東京一極集中
- 東京都内大学への集中が顕著(東京農工・都立・外語・学芸で大半)。
- 埼玉・茨城・群馬などの近県の国公立大学への進学がほとんどない。
- その他地方国公立の急増
- 2025年は「その他地方国公立」が12人と急増(2024年の6人から倍増)。
- 関東圏から地方国公立への流れが強まっている可能性。
総合的考察
- 「農都外」3校の安定的強さ
- 東京農工大・都立大・外国語大の3校で関東主要国公立大学合格者の大半を占める構図が継続。
- 特に2025年は22人中の農都外で合計22人と圧倒的シェア。
- 国公立全体の回復傾向
- 国公立合計は2023年の106人(34.0%)から2025年は112人(37.1%)へと回復。
- 特に2025年は卒業生数が減少する中での健闘。
- 進学先の二極化と多様化
- 最難関・旧帝大と関東主要国公立の「二極化」が進む一方、
- 「その他地方国公立」の増加は進学先の「多様化」も示唆。
- 進学指導の変化
- 都立大学への進学者増加は都立高校としての特性を反映。
- 地方国公立への進学増加は難関私大との併願戦略の変化も示唆。
- 理系進学の特徴
- 理系は東京農工大学と電気通信大学で対照的な動き。
- 東工大(東京科学大学)と農工大への「理系二極化」が進行。
都立西高校の関東主要国公立大学への進学は、6年間の推移を見ると最難関・旧帝大と補完関係にあり、特に「農都外」3校と地方国公立大学が重要な進学先となっています。関東主要国公立大学全体としては2022年を底に回復傾向にあり、2025年も卒業生減少の中で健闘していると評価できます。
🎓 難関大学を目指す高校生(先取りの中学生)へ
現役合格をつかむには、早い段階から受験対策を始めることが鍵。
以下の予備校・個別指導サービスでは、東大・早慶など難関大を目指す生徒を強力にサポートします。
👉 【現役合格】映像授業で現役合格を目指すなら 東進ハイスクール・東進衛星予備校 ![]()
👉 【東大の力】東大生講師による難関大指導 【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
👉 【東大×個別】学習相談から始める東大生の個別指導 【東大オンライン】 ![]()
👉 【難関対策】難関大志望者に選ばれる通信教育 高校生・大学受験生のためのZ会 ![]()
👉 【1対1】マンツーマンで徹底サポートする個別指導 1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】
![]()
都立西高校の現役生に占める国公立大学群別合格人数比|2020年~2025年


全体傾向と特徴
- 安定した国公立比率:
- 卒業生数が318人(2020年)から302人(2025年)へと5%減少する中、国公立合格比率は36.5%→37.1%と微増。
- 2023年の34.0%を底に回復傾向にあり、国公立大学志向の強さが継続。
- 群間のバランス変化:
- 2020年: 東京一科医11.9%、旧帝大8.2%、TOCKY6.9%、関東国公立7.5%、地方国公立1.9%
- 2025年: 東京一科医14.9%、旧帝大6.6%、TOCKY4.0%、関東国公立7.6%、地方国公立4.0%
- 最難関と地方国公立が増加し、中間層(特にTOCKY)が減少する「両極化」現象。
大学群別詳細分析
東京一科医(最難関)
- 大きな波: 2020年38人(11.9%)→2022年54人(17.2%)→2024年35人(11.1%)→2025年45人(14.9%)
- V字回復: 2024年の落ち込みから2025年は大幅回復。卒業生比率では3.8ポイント増(11.1%→14.9%)。
- 全体に占める比率: 国公立合格者全体の40%前後を常に占める中核群。
旧帝大(東大・京大除く)
- U字型推移: 2020年26人(8.2%)→2023年12人(3.8%)→2025年20人(6.6%)
- 回復途上: 2020年水準には達していないが、2年連続回復傾向。
- 群内変化: 北海道大学が一貫して主力校に。
TOCKY(医除く)
- 段階的減少: 2020年22人(6.9%)→2023年22人(7.1%)→2025年12人(4.0%)
- 近年の急落: 2023年以降急減。2025年は2023年比で約半減。
- 群内の偏り: 横浜国立大、筑波大、千葉大に集中し、神戸大は0。
関東国公立(医除く)
- 変動の大きさ: 2022年18人(5.7%)→2024年30人(9.5%)→2025年23人(7.6%)
- 2024年のピーク: 2024年は特異的に高く、2025年は若干減少するも高水準維持。
- 「農都外」への集中: 東京農工大、都立大、外国語大で大半を占める構造。
地方国公立(医除く)
- 着実な成長: 2020年6人(1.9%)→2022年10人(3.2%)→2025年12人(4.0%)
- 2025年の躍進: 2024年6人から2025年12人へと倍増。過去最高を更新。
- 選択肢の多様化: 地方国公立への進学ルートが確立されつつある。
総合考察
- 進学指導の変化
- 最難関大学と地方国公立に重点を置く二極化戦略が明確に。
- 関東国公立大学は安定したセーフティネットとして機能。
- TOCKY大学の位置づけが低下。
- 2025年の特徴的な動き
- 最難関復活: 2024年からの大幅回復が目立つ。
- TOCKY凋落: 唯一減少を続けている群。
- 地方国公立躍進: 比率で見ると2倍以上に増加。
- 全体でのバランス: 各群がより明確な役割分担。
- 経年変化の特徴
- 2020-2022年: 最難関増加・旧帝大減少の「最難関集中期」
- 2022-2024年: 最難関減少・関東国公立増加の「中堅重視期」
- 2024-2025年: 最難関回復・地方国公立増加の「両極化期」
- 志望校選択の多様化
- 東京一極集中からの脱却傾向が見られる。
- 北海道大学や九州大学など地方旧帝大、地方国公立への進学増加。
- 進路選択における「選択と集中」が進み、中間層が減少。
都立西高校の国公立大学合格実績は、2020年から2025年にかけて量的には安定しつつも、質的には大きく変化しています。特に2025年は「最難関回復」と「地方国公立躍進」という特徴的な両極化が進み、進学指導の方向性転換を示唆しています。全体としては、卒業生数減少の中での健闘と評価できるでしょう。
【2025年度】都立西高校の最難関私立大学(早慶上理+医学部)合格者分析
【2025年度】最難関私立大学合格者数と現役合格者前年比
| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 88人 | (+17人) | 57人 | 145人 |
| 慶應義塾大学 | 51人 | (+15人) | 31人 | 82人 |
| 上智大学 | 30人 | (▲9人) | 73人 | 103人 |
| 東京理科大学 | 56人 | (+5人) | 55人 | 111人 |
| 私立大学医学部 | 2人 | (▲4人) | 12人 | 14人 |
| 合計(医学部重複除く) | 227人 | (+24人) | 228人 | 455人 |
大学別の傾向と特徴
早稲田大学
- 圧倒的な躍進: 現役88人(前年比+17人)と大幅増加。現役合格者数が浪人を上回る珍しい状況。
- 絶対的な強さ: 合計145人は他大学を圧倒し、西高の早稲田への合格力を示している。
- 私学トップ:現役合格者数、合計合格者数ともに私立大学中トップの実績。
慶應義塾大学
- 大幅な成長: 現役51人(前年比+15人)と前年から約42%増という驚異的な伸び。
- バランスの良さ: 現役と浪人の比率が51:31と現役優位の健全な構造。
- 早慶強化: 早稲田とともに合格者を大幅に増やし、早慶合格に向けた指導の成果が顕著。
東京理科大学
- 安定した実績: 現役56人(前年比+5人)と着実に増加。
- 現浪均衡: 現役56人、浪人55人とほぼ同数で、多様な進学パターンを支援。
- 理系の柱: 国公立理系と並ぶ重要な理系進学先として機能。
上智大学
- 現役合格の苦戦: 現役30人(前年比△9人)と大幅に減少。
- 浪人圧倒的多数: 浪人73人と現役の2.4倍という特異な構造。
- 再挑戦の選択肢: 一度浪人しての上智合格という進路パターンが顕著。
私立大学医学部
- 厳しい結果: 現役2人(前年比△4人)と低迷。
- 浪人依存: 浪人12人が合格者の大半を占める典型的な「浪人型」。
- 医学部の難関度: 私立医学部への現役合格の難しさを反映。
全体的な傾向と特徴
- 私立最難関の躍進: 現役合格者計227人(前年比+24人)と大幅増加。国公立の回復と併せ、全体的な上位進学実績の向上。
- 早慶理躍進・上智医苦戦: 早稲田、慶應、理科大の3校では前年比合計+37人の増加、上智と私立医学部では合計△13人の減少という対照的な動き。
- 現役と浪人の比率: 全体では現役227人と浪人228人がほぼ拮抗。大学別では早慶理科大が現役優位・上智私立医学部が浪人優位という特徴。
- 現役合格力の強化: 特に早稲田・慶應への現役合格者数の大幅増加は、進学指導体制の充実を示唆。
- 進路選択の分化: 上智大学と私立医学部については「浪人してでも志望校に」という傾向が顕著で、進路選択の多様化を反映。
- 私立・国公立のバランス: 国公立最難関・旧帝大の45人+22人=67人に対し、私立最難関の現役227人と、約3.4倍の規模。私立中心の進学構造が継続。
都立西高校の2025年度私立最難関大学合格実績は、特に早稲田・慶應への現役合格者増加が際立ち、国公立の回復傾向と合わせて最難関大学全体での躍進が見られます。一方で上智大学と私立医学部では現役合格に課題があり、大学・学部による差異が明確になっています。全体としては現役455人という圧倒的な合格者数が示すように、私立最難関大学への進学実績は学校の強みとなっています。
都立西高校の最難関私立大学(早慶上理+医学部)の現役合格者数推移|2020年~2025年


全体的な傾向と特徴
- 安定した合格総数
- 現役合格者数は2022年の265人をピークに一時減少後、2023-2025年は227人で安定。
- 卒業生に占める比率は2023年50.1%をピークに2024年41.4%まで低下後、2025年は47.7%と回復。
- 私立大学全体の延べ合格数は2022年の608人から2025年は476人へと減少傾向。
- 現役比率の改善
- 私立最難関大学への現役合格者が私立大学合格総数に占める比率は2020年41.4%→2025年47.7%と上昇。
- 質的向上を示す指標として注目される。
大学別の経年変化
早稲田大学
- 波形を描く推移: 2020年58人(13.2%)→2022年98人(16.1%)→2024年71人(13.0%)→2025年88人(18.5%)
- 比率の最高値: 2025年の18.5%は6年間で最高の比率を記録。
- V字回復: 2024年から2025年にかけて17人増加し、比率も5.5ポイント上昇。
慶應義塾大学
- 不安定な推移: 2021年57人(9.8%)→2024年36人(6.6%)→2025年51人(10.7%)
- 2025年の回復: 2024年から15人増、比率も4.1ポイント上昇と大幅回復。
- 初期水準への回帰: 2020年の10.0%と同水準まで回復。
上智大学
- 中間層としての安定性: 27人〜42人の間で推移。
- 直近の停滞: 2024年39人(7.1%)→2025年30人(6.3%)と減少。
- 早慶との差: 早慶が回復する一方で上智は停滞傾向。
東京理科大学
- 最も安定した実績: 6年間を通じて48〜57人の安定した現役合格者数。
- 比率の向上: 2025年の11.8%は6年間で最高値。
- 理系進学の堅調さ: 私立理系大学への安定した進学実績を示す。
私立大学医学部
- 厳しい変動: 2022年12人(2.0%)をピークに大幅減少。
- 2025年の低迷: 2人(0.4%)と過去6年間で最低。
- 医学部全体の課題: 国公立医学部と同様に現役合格者数が低迷。
経年分析の特徴点
- 2022年の全体ピーク
- 2022年は265人と現役合格者数のピーク。特に早稲田(98人)が好調。
- 以降は総数では減少するも比率は維持・向上。
- 2023年の比率ピーク
- 私立大学全体の合格数が大幅減(608人→453人)の中、最難関比率は50.1%と最高。
- 質的向上が顕著な年。
- 2024年の停滞と2025年の回復
- 2024年は早慶が低迷するも上智が健闘。
- 2025年は早慶が大幅回復し、上智・医学部が低迷という対照的な動き。
- 大学間の相関性
- 早慶は同様の動きを示す傾向。
- 理科大は独自の安定した推移。
- 上智は2022年をピークに緩やかな減少傾向。
- 私立大学全体の縮小
- 延べ合格数は2022年の608人から2025年は476人へと約22%減少。
- 国公立志向の高まりや進路指導の変化を示唆。
総合考察
都立西高校の私立最難関大学合格実績は、量的には安定期に入りつつも質的には向上傾向にあります。特に2025年は早慶の回復により最難関比率が47.7%と高水準を記録し、私立大学全体の合格者数が減少する中で、より選択と集中が進んでいることを示しています。大学別では早稲田の躍進と理科大の安定が目立ち、上智と医学部の低迷が課題として浮かび上がっています。
国公立大学の分析と合わせると、2025年は「最難関回復の年」と位置づけられ、早慶と東大・京大など最上位校への合格実績が向上していることが特筆すべき点です。
🎓 難関大学を目指す高校生(先取りの中学生)へ
現役合格をつかむには、早い段階から受験対策を始めることが鍵。
以下の予備校・個別指導サービスでは、東大・早慶など難関大を目指す生徒を強力にサポートします。
👉 【現役合格】映像授業で現役合格を目指すなら 東進ハイスクール・東進衛星予備校 ![]()
👉 【東大の力】東大生講師による難関大指導 【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
👉 【東大×個別】学習相談から始める東大生の個別指導 【東大オンライン】 ![]()
👉 【難関対策】難関大志望者に選ばれる通信教育 高校生・大学受験生のためのZ会 ![]()
👉 【1対1】マンツーマンで徹底サポートする個別指導 1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】
![]()
【2025年度】都立西高校の難関私立大学(GMARCH)合格者分析
【2025年度】難関私立大学(GMARCH)合格者数と現役合格者前年比
| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |
|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 3人 | (▲3人) | 11人 | 14人 |
| 明治大学 | 95人 | (+4人) | 92人 | 187人 |
| 青山学院大学 | 5人 | (▲5人) | 15人 | 20人 |
| 立教大学 | 22人 | (▲2人) | 45人 | 67人 |
| 中央大学 | 16人 | (▲22人) | 41人 | 57人 |
| 法政大学 | 17人 | (▲14人) | 34人 | 51人 |
| 合計 | 158人 | (▲42人) | 238人 | 396人 |
大学別の特徴と傾向
明治大学
- 唯一の増加校: 現役95人(前年比+4人)と唯一前年を上回る実績。
- 圧倒的な存在感: 現役合格者数がGMARCH全体の60%を占める圧倒的な主力校。
- 現浪バランス: 現役95人と浪人92人とほぼ同数の合格者を出し、多様な進学ルートを提供。
立教大学
- 健闘する実績: 現役22人(前年比△2人)と微減ながらも、明治大学に次ぐ2位の位置を維持。
- 浪人優位: 浪人45人が現役の約2倍と、再挑戦の場としての性格が強い。
- 都心の文系私大: 池袋という立地と学部構成から文系志望者の選択肢として機能。
法政大学
- 大幅減少: 現役17人(前年比△14人)と急減。前年から約45%減という厳しい結果。
- 浪人の多さ: 浪人34人が現役の2倍と、こちらも再チャレンジの場としての性格が強い。
- 明治大学へのシフト: 法政志望者が明治にシフトしている可能性も。
中央大学
- 激減: 現役16人(前年比△22人)と最大の減少幅。前年から約58%減と極めて厳しい状況。
- 浪人圧倒: 浪人41人が現役の2.5倍以上という極端な構造。
- 立地変化の影響: 多摩キャンパスから都心への移転過程による志望動向の変化も考えられる。
青山学院大学
- 低調: 現役5人(前年比△5人)と半減。
- 浪人集中: 浪人15人が現役の3倍という極端な比率。
- 大学のポジショニング: 渋谷という立地の優位性が活かしきれていない可能性。
学習院大学
- 最低水準: 現役3人(前年比△3人)と半減。GMARCH中で最も少ない合格者数。
- 伝統校の苦戦: 伝統ある大学ながら、西高生からの人気は最も低い状況。
- 浪人の多さ: 浪人11人が現役の3.7倍という最も極端な比率。
全体的な傾向と特徴
- 全体的な大幅減少: 現役158人(前年比△42人)と約21%減。直近の私立最難関大学の回復とは対照的な動き。
- 現浪比の不均衡: 現役158人に対し浪人238人と、浪人が約1.5倍という構造。「浪人してGMARCH」という進路パターンが顕著。
- 明治大学への一極集中: 明治大学95人が他5大学の合計63人を大きく上回る極端な偏り。GMARCH内での序列が明確に。
- 大半の大学で大幅減少: 明治以外の5大学全てで前年比マイナス、特に中央・法政の減少が顕著。
- 難関私大との対比: 早慶上理が合計227人(前年比±0人)と堅調な中、GMARCHは158人(前年比△42人)と苦戦。難関私大へのシフトが進行。
- 中位大学の空洞化: 難関大学(早慶上理)と明治大学への二極化が進み、中位のGMARCH校(立教・中央・法政・青山・学習院)が苦戦。
都立西高校の2025年度GMARCH合格実績は、明治大学のみ健闘する一方で他大学は大幅減という「明治一強」の構図が鮮明になりました。全体としては現役合格者数の大幅減少と極端な浪人依存という傾向が見られ、早慶上理や最難関国公立大学へのシフトが進む中で、GMARCH(特に明治以外)の位置づけが相対的に低下していると言えるでしょう。
都立西高校の難関私立大学(GMARCH)の現役合格者数推移|2020年~2025年


全体的な傾向と特徴
- 変動する合格者数
- 大きな波: 2020年154人→2022年202人→2023年160人→2024年200人→2025年158人
- 2021-22年と2024年に多く、2020年、2023年、2025年に少ない傾向。
- 私立大学全体に占める比率は33〜35%で比較的安定。
- 合格総数の減少
- 私立大学延べ合格数自体が2022年608人から2025年476人へと大幅減少。
- GMARCH全体も2022年202人から2025年158人へと約22%減少。
大学別の経年変化
明治大学
- 圧倒的な成長: 2020年62人(14.1%)→2025年95人(20.0%)と一貫して上昇。
- 比率の大幅増加: 私立大学合格全体に占める比率が6年間で約6ポイント上昇。
- GMARCH内でのシェア拡大: 2020年にGMARCH合格全体の約40%→2025年は約60%と圧倒的シェア。
中央大学
- 大幅な変動と急落: 2020年37人(8.4%)→2021年39人(6.7%)→2025年16人(3.4%)
- 特に2024-25年の急減: 2024年38人から2025年16人へと22人減(約58%減)という顕著な落ち込み。
- 都心移転の影響: 多摩から都心キャンパスへの移転過程での志望動向の変化。
立教大学
- 緩やかな減少: 2020年29人(6.6%)→2022年34人(5.6%)→2025年22人(4.6%)
- 比較的安定: 他校に比べて急激な変動が少なく、明治に次ぐ位置を維持。
- GMARCH内での地位向上: 2025年は明治に次ぐ2位の位置を確立。
法政大学
- 変動しつつ減少: 2020年17人(3.9%)→2024年31人(3.6%)→2025年17人(3.6%)
- 2024年の一時的増加: 2024年のみ31人と突出、翌年は半減。
- 元の水準への回帰: 2025年は2020年と同水準の17人に。
青山学院大学
- 大きな波と低迷: 2020年5人(1.1%)→2021年25人(4.3%)→2025年5人(1.1%)
- 2021年の突出: 2021年のみ25人と5倍に急増した後、元の水準に戻る。
- 不安定な推移: 6年間で最も変動が大きい大学。
学習院大学
- 一貫した低位: 3〜10人の間で推移し、常にGMARCH最下位。
- 2022年の突出: 2022年のみ10人(1.6%)と例外的に多い年があるが、基本的に低調。
- 伝統校の限界: 伝統ある大学だが、西高生の志望は低調。
経年分析の特徴点
- 明治大学の一人勝ち
- 2020年: 明治62人、他5校合計92人(明治シェア40%)
- 2025年: 明治95人、他5校合計63人(明治シェア60%)
- GMARCH内での「明治一強」構造が年々強化。
- 明治以外の凋落
- 2021-22年: 明治以外の5校合計で114-120人の水準
- 2025年: 明治以外の5校合計で63人と約半減
- 特に青山学院と中央大学の減少が顕著。
- 私立大学全体の縮小と影響:
- 私立大学延べ合格数減少の中でもGMARCH比率は維持
- 大学間格差が拡大し、明治のみが健闘。
- 2021-22年と2024-25年の対照的動き:
- 2021-22年: 全般的に合格者数が多い「GMARCH好調期」
- 2024-25年: 明治一校のみが好調で他は低迷する「明治一強期」
- 特に2025年は明治以外の5校が軒並み低迷。
総合考察
都立西高校のGMARCH合格実績は、量的には2020年水準に戻りつつも、質的には「明治一強」という顕著な偏りが進行しています。明治大学は安定して実績を伸ばし私立大学合格者全体の20%を占める一方、他のGMARCH大学は軒並み苦戦しており、特に中央大学と青山学院大学の急落が目立ちます。
この傾向は、早慶上理などの最難関私立大学と明治大学への「二極集中」が進む一方で、中位のGMARCH校の位置づけが相対的に低下していることを示しています。難関国公立大学の回復と合わせて考えると、西高の進学構造は「最難関国公立・最難関私立・明治大学」という三本柱に収斂しつつあると言えるでしょう。
都立西高校現役生の私立大学延べ合格数に占める私立大学群別合格人数比|2020年~2025年


ⓘ成成明学國武、四工大+東農、日東駒専はホームページ似て記載がなかったため0人表記としています。
私立大学全体の構成変化
大学群別比率の推移
- 最難関私立(早慶上理)の安定した優位性
- 早稲田・慶應: 2020年23.2%→2025年29.2%と大幅増加。2023-25年の間に19.5%→29.2%と急回復。
- 上智・東京理科: 2020年17.0%→2025年18.1%と安定した比率を維持。
- 合計で2025年は47.3%と、私立大学合格者の約半数を占める圧倒的存在。
- GMARCHの堅調さ
- 一貫して33-36%の比率を維持。
- 2024年36.5%をピークに2025年は33.2%と若干低下。
- 実数では2022年202人→2025年158人と減少も、全体比率では安定。
- 私立医学部の縮小
- 2022年2.0%をピークに2025年は0.4%と大幅減少。
- 医学部志望者の動向変化を示唆。
- その他私立大学の変動
- 2020-22年は約23%で安定→2023年急減14.6%→2024年急増26.5%→2025年再減19.1%と大きな変動。
- 合格戦略の変化や年度による志望動向の違いを反映。
延べ合格数の推移
- 波形を描く総数: 2020年440人→2022年608人→2023年453人→2025年476人
- ピークと底: 最多は2022年608人、最少は2020年440人。
- 2025年の位置づけ: 476人は中間的水準だが、卒業生数減少を考慮すると健闘といえる。
経年比較から見る特徴
- 最難関大学比率の向上
- 早慶上理医の比率: 2020年41.6%→2025年47.7%と着実に上昇。
- 最難関国公立大学の回復と連動して、難関校への合格力が強まる傾向。
- 明治大学の突出と中堅私大の二極化
- 明治大学だけで2025年は20.0%と突出。
- 他のGMARCH校は減少傾向にあり、「明治一強」の構図が鮮明に。
- 2025年度の特徴
- 早慶比率の大幅回復(19.5%→29.2%)
- 医学部合格者の激減(1.1%→0.4%)
- その他私立大学の減少(26.5%→19.1%)
- 全体として「上位集中型」の合格実績。
- 棒グラフの経年変化
- 早稲田大学(濃い青)部分が2024年に縮小後、2025年に再拡大。
- GMARCH部分(黄色)は2023年に拡大後、2025年に縮小。
- グラフ上部の「その他」(灰色)部分は2023年に急拡大後、縮小傾向。
- 私立大学選択の特徴
- 「早慶上理」と「明治大学」と「それ以外」という明確な三層構造。
- 中位~下位の私立大学への進学がほぼ皆無という特異な進学構造。
- 難関大学に合格できなかった場合の選択が「その他私立大学」に集中。
総合考察
都立西高校の私立大学合格実績は、全体としては「最難関大学シフト」が明確になっています。特に2025年は早慶の比率が大幅に回復し、GMARCHは明治大学が突出する一方で他大学は軒並み減少するという「二極化」が進行しています。
また、国公立大学と私立大学の合格状況を総合すると、「最難関国公立・早慶上理・明治大学」を頂点とした「上位集中型」の進学構造が強まっており、中堅私大が極端に少ないという特徴が顕著です。これは都立西高校の進学指導が「トップ層」の育成に重点を置いていることの表れと考えられます。
東大京大・早慶の回復と明治一強:西高2025年度進学の特色

現役生の延べ合格者数に占める大学群比の円グラフを見ると、2025年度の都立西高校現役生の進学実績は、以下のような特徴的な構造を示しています。
- 難関大学への高い集中度
- 難関大学(東京一科医、旧帝大、早慶上理、GMARCH等)が全体の約84.2%を占める
- 特にGMARCH(27%)と早慶(24%)で全体の半数以上
- 私立大学と国公立大学のバランス
- 私立大学が優位(早慶24%、GMARCH27%、上智・理科14%で計65%)
- 国公立大学は全体の約19%(東京一科医8%、旧帝大3%、TOCKY2%、関東国公立4%、地方国公立2%)
- 中間層の薄さ
- TOCKYなどの中堅国公立大学が2%と極めて少ない
- 難関大学以外の私立大学(成成明学國武や日東駒専など)が不在
2020-2025年の経年変化から見る特徴と傾向
国公立大学の動向
- 最難関国公立の回復
- 東京一科医大学は2024年の低迷から回復し、2025年は45人(14.9%)と健闘
- 特に東大・京大など最上位層の回復が顕著
- 旧帝大の安定回復:
- 2023年の底(12人)から2年連続で回復し、2025年は20人(6.6%)
- 特に北海道大学(11人)が好調
- TOCKYの長期低迷
- 2020年22人(6.9%)から2025年12人(4.0%)へと長期的に減少
- 横浜国立大学、筑波大学の落ち込みが顕著
- 関東主要国公立と地方国公立の健闘
- 関東主要国公立は東京農工大、都立大学を中心に安定
- 地方国公立は2025年に倍増(6人→12人)し、新たな進学先として台頭
私立大学の動向
- 早慶の顕著な回復
- 2024年の低迷から2025年は大幅回復(早稲田88人、慶應51人)
- 現役合格率は29.2%と過去6年で最高水準
- 明治大学の圧倒的強さ
- 2025年は95人(20.0%)と私立大学中最多
- GMARCH内での「明治一強」体制が鮮明に
- GMARCH内の二極化
- 明治大学だけが伸長する一方、中央大学(16人)などは大幅減少
- 上位と下位の格差が拡大
- 医学部の低迷
- 私立医学部は2人(0.4%)と過去最低
- 医学部志望者の動向に変化
総合的な考察
都立西高校の2025年度進学実績は、「難関大学集中型」の特徴がより鮮明になっています。約84%の現役生が難関大学に合格し、特に最難関国公立大学と早慶上理、明治大学への合格者が顕著に増加しています。
一方で、中間層の大学(TOCKY、中央・法政・青山学院等)への合格者は減少傾向にあり、「最上位層重視」の進学指導が行われていることが窺えます。また、地方国公立大学への進学増加など、進路選択の多様化も進んでいます。
全体としては、卒業生数がやや減少(318人→302人)しているにもかかわらず国公立大学合格率37.1%、難関私立大学合格率47.7%という高水準を維持しており、特に最上位層の育成に成功していると評価できます。早慶上理と東大・京大・医学部という「トップ層」、明治大学と旧帝大・農工大等の「準トップ層」、そして「その他」という三層構造が明確になり、上位校への集中度が高い進学実績となっています。
合格実績に刺激を受けたあなたへ。次に必要なのは“質の高い勉強”です
難関大学への合格実績を見て、「自分もいつかは…」と感じた方も多いのではないでしょうか。
でも、ただ勉強量を増やすだけでは、合格に近づけないのもまた事実。
必要なのは、限られた時間の中で“本当に意味のある勉強”を続けることです。
Z会の通信教育は、思考力・記述力を育てる質の高い教材に加え、プロによる添削指導で、志望校合格までの学習をしっかりとサポート。
難関大合格を目指すあなたにこそふさわしい、自宅でできる学びがあります。
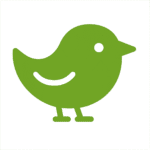 トリトリ
トリトリ部活も文化祭も終わって、これからは志望校合格に向けてラストスパートの季節だよ!
秋は、学力を伸ばす絶好のタイミング。
Z会の通信教育〈高校受験コース〉なら、考えて「紙に書く」学びを通して、難関高校合格レベルへと実力を高められます。
苦手やレベルに合わせた個別プログラムで、定期テスト対策から入試対策までしっかりサポート。
今なら『英語Writingワーク』(学年別)と『自主学習の継続を後押しする保護者のサポートBOOK』をプレゼント中!
忙しい秋だからこそ、親子で「これからの学び」を見直すチャンスです。
\ 資料請求で2つの特典をプレゼント! /


<参照元>
ページ内の大学合格実績は各高校のホームページやパンフレットを参照しています。しかしながら、参照したタイミングによっては速報データであったり、年度をまたぎ変更となっている場合もありますので、正確なデータは各都立高校の最新データをご確認ください。
・西高校公式サイト https://www.metro.ed.jp/nishi-h/



