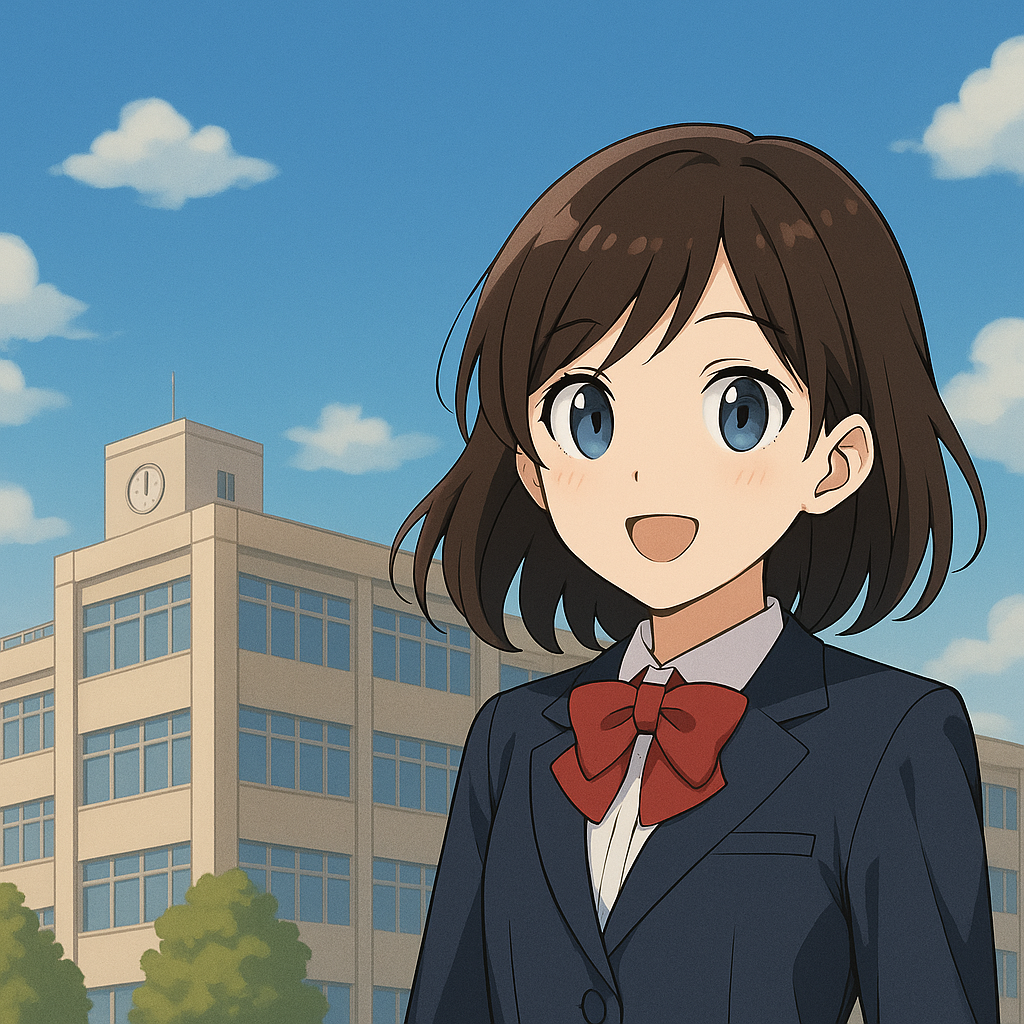東京都の高校入試では、「共通問題校」と「自校作成校」という2つの入試形態があります。共通問題校は都教育委員会が作成する統一問題を使用するのに対し、自校作成校は各校が独自の入試問題を作成します。自校作成校は各校の特色や教育方針に合わせた問題が出題されるため、受験生には共通問題校とは異なる準備と対策が求められます。
都立入試において「自校作成校」とは何か?
自校作成校は、都立高校の中でも主に上位校に多く見られます。これらの学校では、各校の教育方針や求める生徒像に合わせた独自の入試問題を作成し、より適切な生徒選抜を目指しています。
理科・社会に関してはどの高校も共通問題を採用していますが、英語・国語・数学の3教科において自校作成問題を採用している高校が11校あります。
自校作成問題の特徴
- 独自の教育方針に基づく問題作成
- 高度な学力と思考力の測定
- 各校の特色を反映した出題傾向
- 記述式問題の重視
- 発展的な学習内容の出題
自校作成問題を取り入れている進学指導重点校(7校)
- 日比谷高校(千代田区)
- 西高校(杉並区)
- 戸山高校(新宿区)
- 八王子東高校(八王子市)
- 国立高校(国立市)
- 青山高校(渋谷区)
- 立川高校(立川市)
自校作成問題を取り入れているその他の高校(4校)
進学重視型単位制高校(3校)
- 新宿高校(新宿区)
- 国分寺高校(国分寺市)
- 墨田川高校(墨田学)
その他高校(英語のみ独自作成問題)
- 国際高校(目黒区)

なぜ入試問題を自校で作成するのか?
自校作成校が独自の入試問題を作成する理由は、まず第一に、各校の教育方針を入試に反映させる必要性があることです。各校は特色ある教育プログラムを持っており、それを実践できる生徒を選抜することが重要です。独自の教育目標に適合する生徒を確保し、入学後の教育効果を高めるためにも、学校独自の問題作成が必要とされています。また、特色ある教育プログラムへの適性を正確に評価するためには、その学校ならではの出題が欠かせません。
第二に、多様な能力を適切に評価するという観点があります。共通問題だけでは測りきれない思考力や判断力を測定したい、あるいは表現力や論理的思考力をより詳細に評価したいという意図があります。各学校が独自に求める資質や能力を確認するためには、それに適した問題を自校で作成する必要があるのです。
第三に、より質の高い生徒選抜を実現するという目的があります。学校の特色に合った生徒を確実に確保するとともに、入学後の学習に必要な基礎力を的確に判断することが求められます。そのためには、より精密な選抜方法が必要となり、自校作成による入試問題がその役割を果たしています。
このように、自校作成校による独自の問題作成は、各校の教育方針の実現と、より適切な生徒選抜を可能にする重要な手段となっているのです。
「自校作成校」の問題と共通問題の違いは?
自校作成問題と共通問題には、難易度、出題形式、出題範囲の3つの面で大きな違いが見られます。
まず、難易度の面では、自校作成問題は共通問題と比べて総じて難度が高くなっています。単なる知識の確認だけでなく、発展的な内容や応用問題が数多く出題され、より深い思考力が要求されます。受験生は基礎的な学力に加えて、応用力や問題解決能力が試されることになります。
次に、出題形式においても特徴的な違いがあります。自校作成問題では記述式問題の比重が大きく、複数の教科や分野の知識を組み合わせて解答する必要のある問題が多く見られます。また、単に答えを導き出すだけでなく、思考のプロセスそのものを問う問題も出題されるため、論理的な思考力と表現力の両方が必要となります。
さらに、出題範囲にも大きな違いがあります。自校作成問題では教科書の発展的な内容が含まれることが多く、また時事問題や現代社会の課題なども積極的に取り上げられます。加えて、各校の特色や教育方針に関連した独自の題材が使用されることも特徴です。
このように、自校作成問題は共通問題と比べてより高度で総合的な学力が問われる傾向にあり、受験生には十分な準備と対策が求められます。
「自校作成校」の問題の難易度はどのくらい?
自校作成問題の難易度がどの程度高いのか、具体的な数値で見てみましょう。
進学研究会が実施するV模擬試験のデータを分析すると、興味深い結果が見えてきます。例えば、共通問題校である竹早高校・小山台高校と、自校作成校である八王子東高校を比較してみましょう。これらの学校は、V模擬試験における偏差値が62~63とほぼ同じ水準で、共通テストでの想定得点率も90~91%で80%が合格するという見立てとなっています。
しかし、実際の入試における得点率には大きな差が生じています。自校作成校である八王子東高校の入試データを参照すると、ここ数年の受検者の入学試験の国数英3科目平均点は170~180点(約60%程度)となっています。つまり、共通テストで9割の得点を取れる実力を持つと想定される生徒でも、自校作成問題では6割程度の得点にとどまるということです。
この数値の差は、自校作成問題の難易度の高さを如実に示しています。同じ学力層の生徒であっても、自校作成問題に直面すると大幅に得点率が下がる傾向があり、その対策には特別な準備が必要となることがわかります。
自校作成校問題への対策方法
自校作成校の受験を成功させるためには、効果的な対策が不可欠です。具体的には、過去問分析、記述力の強化、学力の充実という3つの側面からの準備が重要となります。
まず、入念な過去問分析に取り組む必要があります。出題パターンを詳しく把握し、各設問の意図を正確に理解することが重要です。また、採点基準を研究し、時間配分を検討するとともに、解答の構成方法についても綿密に分析する必要があります。これらの分析を通じて、試験の全体像を把握し、効率的な解答戦略を立てることができます。
次に、記述力の強化も重要な課題です。論理的な文章構成力を養成し、的確な表現力を向上させることが求められます。特に、根拠を明確にした解答の練習を重ね、文章の簡潔性と正確性を追求していく必要があります。また、限られた時間内で質の高い解答を書き上げるために、記述の速度向上も欠かせません。
さらに、基礎的な学力の充実も重要です。教科書内容を完全に習得した上で、発展的な学習に取り組み、応用力を養成していく必要があります。また、複数の教科や分野を横断する知識を獲得し、時事問題への理解を深めることも大切です。
これらの対策を総合的に行うことで、自校作成問題特有の高度な要求に応える力を身につけることができます。計画的かつ継続的な学習を通じて、確実に実力を養成していくことが合格への近道となるでしょう。
自校作成校への挑戦と効果的な対策のポイント
都立高校入試における自校作成校と共通問題校の違いについて見てきました。自校作成校は、各校の教育方針や特色を反映した独自の入試問題を作成することで、より適切な生徒選抜を目指しています。
その特徴は、共通問題と比べて明らかに高い難易度、記述式重視の出題形式、そして発展的な内容を含む広い出題範囲にあります。実際、V模擬試験のデータを見ても、同じ学力層の生徒でも自校作成問題では大幅に得点率が下がることが分かります。
そのため、自校作成校の受験には特別な準備が必要です。入念な過去問分析を行い、記述力を強化し、発展的な学習に取り組むなど、総合的な対策が求められます。単なる暗記や反復練習だけでなく、思考力・表現力を高める学習が重要となります。
自校作成校の受験は確かに難しい挑戦となりますが、志望校の特色をよく理解し、計画的な準備を進めることで、十分に合格可能性を高めることができます。受験生の皆さんは、自身の学力を客観的に評価しながら、志望校に合わせた効果的な受験勉強を進めていってください。
難関校を目指すなら、自宅学習にも”本物の教材”を
「この高校に入りたい」――そう思ったとき、気になるのはやはり“受験への準備”。
自分のペースで本格的な受験対策がしたい中学生や、塾に通わずに質の高い学習を進めたいご家庭におすすめなのが【Z会の通信教育】です。
難関校対策に対応したハイレベルな教材と、記述力を伸ばす添削指導。
通信教育でありながら、学習習慣から答案力までしっかり鍛える仕組みが整っています。
本気で上位校を目指すなら、Z会という選択があります。
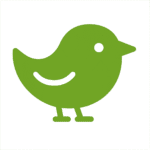 トリトリ
トリトリ部活も文化祭もひと段落。これからは志望校合格に向かってラストスパートをかける時期が来たよ!
秋は、学力を伸ばす絶好のタイミング。
Z会の通信教育〈高校受験コース〉なら、考えて「紙に書く」学びを通して、難関高校合格レベルへと実力を高められます。
苦手やレベルに合わせた個別プログラムで、定期テスト対策から入試対策までしっかりサポート。
今なら『英語Writingワーク』(学年別)と『自主学習の継続を後押しする保護者のサポートBOOK』をプレゼント中!
忙しい秋だからこそ、親子で「これからの学び」を見直すチャンスです。
\ 資料請求で2つの特典をプレゼント! /