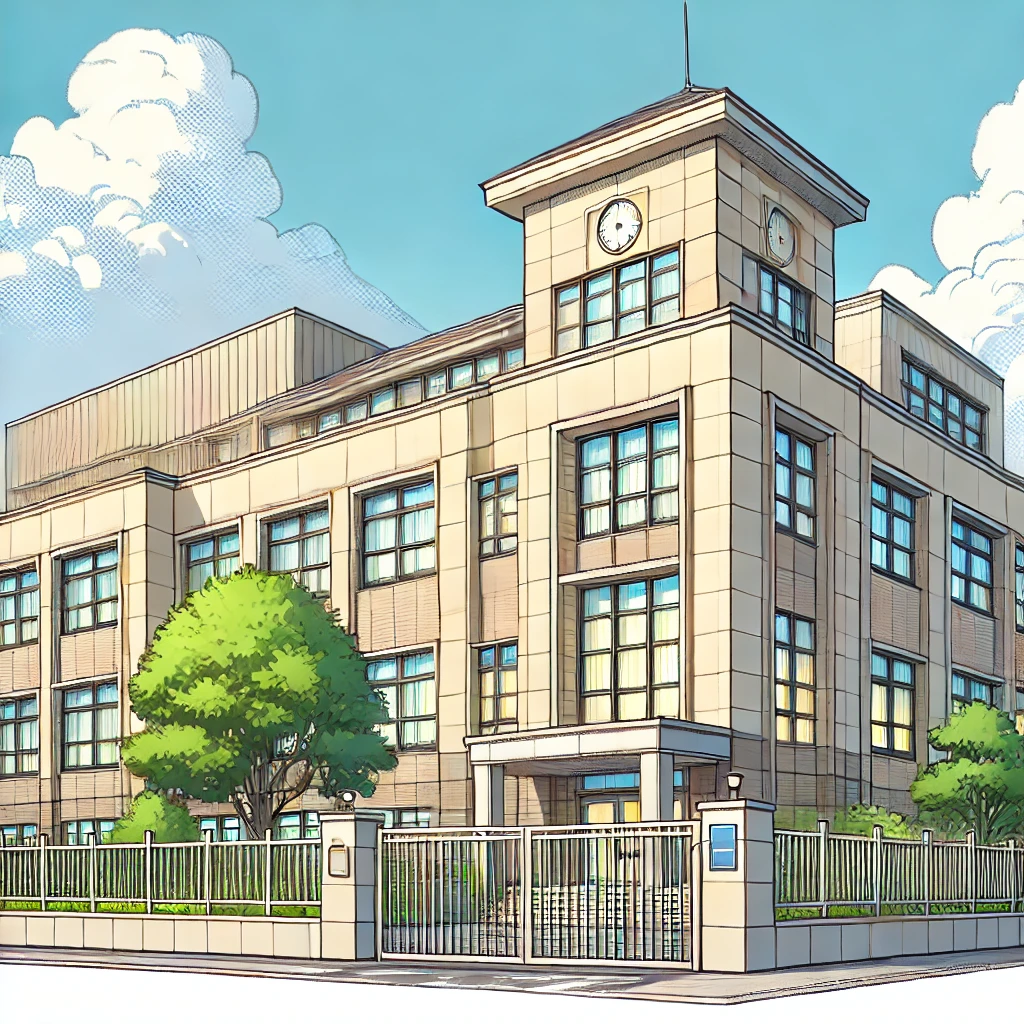東京都小金井市に位置する都立小金井北高校は、1980年の開校以来、「創造」「自律」「努力」を教育目標に掲げ、次代の日本を支えるリーダーの育成を目指してきました。2010年からは東京都教育委員会より「進学指導推進校」の指定を受け、さらに2016年からは「英語教育推進校」「理数研究校」としても指定されるなど、文理両面での教育の充実を図っています。また、年間20回の土曜授業の実施や、入試問題を分析した教材を用いた授業、平日の早朝や放課後の補習など、現役合格を重視した進学指導体制を確立しています。
2019年に創立40周年を迎え、2020年にはオーストラリアのウヌーナハイスクールと姉妹校協定を結ぶなど、グローバルな視点を持つ人材育成にも力を入れています。
本記事では、都立小金井北高校の偏差値や入試倍率、進学実績、校風、部活動、学校行事など、受験生や保護者の方が気になる情報を詳しく解説します。小金井北高校への進学を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
都立小金井北高校の入試倍率と偏差値
入学難易度(偏差値)
小金井北高校は東京都から指定された進学指導推進校の1つであり東京都内の都立高校の中では入試難易度は上位に位置します。進学指導推進校として、難関大学を目指す生徒が多く集まり、入学時点から高い学力が求められます。
- みんなの高校情報:64(東京76位、都立20位)
- 市進教育グループ(80%合格基準):61(都立21位)
- V模擬(60%合格基準):59(東京98位、都立18位)
入試方式
都立高校ですから、推薦入試と一般入試の2つの入試方式があります。2025年度は昨年度は推薦入試が1月26日(土)と1月27日(日)、一般入試が2月21日(金)になります。
<参考情報>詳細はこちらの東京都教育委員会のサイトをご確認ください
都立高校の一般入試では、学力検査点と調査書点の合計(1000点)に英語スピーキングテスト[ESAT-J]の結果(20点)を加えた総合得点(1020点満点)順に選抜されます。面接や実技を実施する学校では、それらの得点も加えた総合成績順に選抜されます。
入試倍率推移
スクロールできます
| 校長会調査時倍率 | 応募倍率(推薦) | 応募倍率(一般) | 最終応募倍率(一般) | 受検倍率(一般) | 合格倍率(一般) |
|---|
| 2025年 | 1.44倍 | 1.96倍 | 1.51倍 | 1.49倍 | 1.41倍 | 1.39倍 |
| 2024年 | 1.65倍 | 2.63倍 | 1.79倍 | 1.68倍 | 1.57倍 | 1.55倍 |
| 2023年 | 1.41倍 | 1.67倍 | 1.41倍 | 1.41倍 | 1.28倍 | 1.27倍 |
小金井北高校の入試倍率は、2023年から2024年にかけて大きく上昇した後、2025年には再び低下するというV字型のパターンを示しています。
2024年は全ての入試区分で倍率が上昇し、特に推薦倍率は2023年の1.67倍から2024年には2.63倍へと約57%も上昇しました。一般応募倍率も1.41倍から1.79倍へと増加し、合格倍率も1.27倍から1.55倍へと上昇しています。この年は小金井北高校への関心が特に高まった年と言えます。
2025年には、全ての区分で倍率が低下していますが、2023年よりは高い水準を維持しています。推薦倍率は2.63倍から1.96倍へと低下しましたが、2023年の1.67倍よりは高い状態です。同様に、一般応募倍率も1.79倍から1.51倍へと低下していますが、2023年の1.41倍より高くなっています。
校長会調査時倍率の推移(1.41倍→1.65倍→1.44倍)も同様のV字パターンを示しており、2025年は2024年に比べて初期段階での関心がやや低下したものの、2023年と同程度の水準に戻っています。
合格倍率の推移(1.27倍→1.55倍→1.39倍)からも、入試競争率が2024年に高まった後、2025年には若干緩和されたものの、2023年よりは競争が激しい状態が続いていることがわかります。
全体として、小金井北高校は2024年に一時的に人気が高まり、2025年には若干低下したものの、2023年と比較すると依然として人気が維持されていると言えるでしょう。この倍率変動は、学校の評判の変化や入試環境の変化を反映していると考えられます。
都立高校入試では「共通問題」と呼ばれる全校共通の筆記試験が実施されます。
この高校を本気で目指すなら、まずはその出題傾向を知ることが合格への近道です。
2019年~2025年(昨年度)の全教科の問題を掲載し、すべての問題にわかりやすい解説つき。
各教科の出題傾向と対策、公立高校合格のめやす、選抜のしくみ、入試情勢など、受験に役立つ情報が1冊にまとめられています。
※リスニング音源は出版社ホームページで聴くことができます。
👉【2026年度入試対応】都立高校共通問題の過去問はこちら
¥1,320 (2026/01/09 19:56時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
👉【2026年度入試対応】併願校探しや優遇基準の確認はこちら
¥2,970 (2026/01/09 19:56時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
都立小金井北高校の歴史と伝統
1979年11月に都立砂川高校内に開設準備事務所が設置され、同年12月に東京都立小金井北高校として設立されました。1980年1月には武蔵野北高校内に一時移転し、翌1981年1月に現在の地に新校舎が完成。同年11月には運動場も完成し、1982年6月に開校記念式典が挙行されました。
校名の由来は、小金井市で唯一の普通科都立高校であることから、1950年~1958年の間存在した東京都立小金井工業高等学校との混同を避けるため「北」が付けられました。同じ頃に開校した東京都立武蔵野北高等学校、東京都立調布北高等学校も他校との混同を防ぐために「北」が付けられており、3校合わせて「サンキタ」と呼ばれることもあります。
学校の伝統を象徴する校章は、周辺の桜にちなんで桜の花びらを配し、校名の頭文字「小」を組み込んで図案化されています。三枚の花びらは教育目標の「創造」「自律」「努力」を表すとともに、生徒・保護者・教職員を象徴し、周囲の円は「円満」を表しています。なお、この桜はソメイヨシノではなく、小金井市のシンボルであるヤマザクラがモチーフとなっています。
都立小金井北高校の立地と最寄り駅、周辺環境
学校は東京都小金井市緑町四丁目に位置し、JR中央線東小金井駅から徒歩11分という好立地にあります。また、武蔵小金井駅からも徒歩15分とアクセスが良好です。バス路線も充実しており、西武新宿線や西武池袋線からもアクセス可能です。
| 住所 | 東京都小金井市緑町4丁目1番1号 |
|---|
| 最寄り駅 | ①JR中央線「東小金井」駅 徒歩11分
②JR中央線「武蔵小金井」駅 徒歩15分 |
|---|