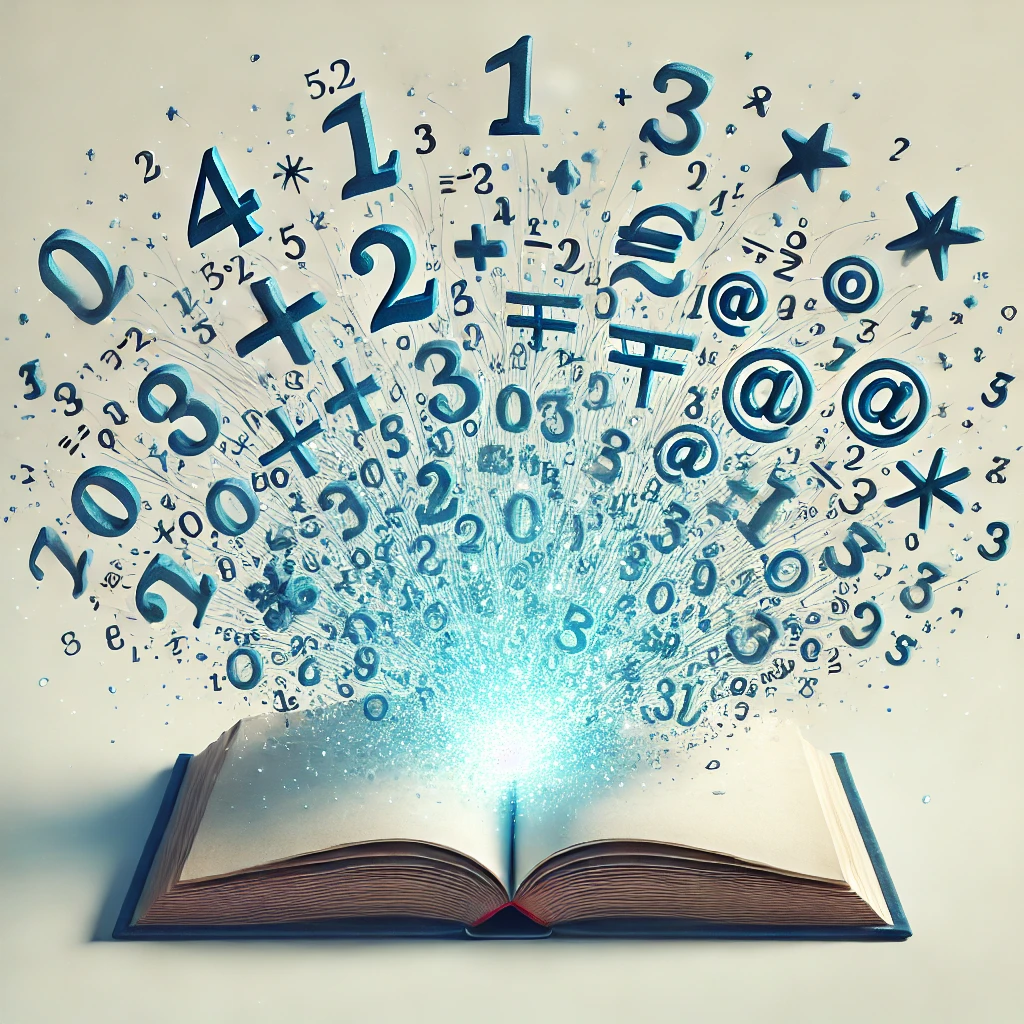中学生のみなさんの内申点は、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」という3つの観点から総合的に評価されます。テストの点数はもちろん大切ですが、普段の授業でどれだけ頑張っているか、提出物はきちんと出しているかなども、とても重要な評価の要素となります。この記事では、それぞれの観点でどんなところが評価されるのか、そして内申点を上げるための具体的なアドバイスを紹介していきます。
高校受験における内申点の重要性
東京都の高校受験において、内申点は合否を左右する重要な要素です。特に、都立高校の推薦入試・一般入試、私立高校の併願優遇・推薦入試など、さまざまな場面で影響を及ぼします。
都立高校の推薦入試における内申点の重要性
都立高校の推薦入試では、内申点、面接、作文または小論文などを総合的に評価します。内申点は総合成績のうち最大50%までの比重と定められており、多くの高校でこの上限が適用されています。そのため、つまり、内申点が高いほど合格のチャンスが大きくなるということです。
都立高校の一般入試における内申点の重要性
都立高校の一般入試では、学力検査と内申点(調査書点)を7:3の比率で合否が判断されます。具体的には、総合得点1020点満点のうち、学力検査が700点、内申点が300点、英語スピーキングテスト(ESAT-J)が20点となります。
都立高校一般入試における内申点の計算方法
- 内申点(通知表):9教科×5段階評価=45点満点
- 換算内申:65点満点に換算
- 入試時の内申点:300点満点に換算
つまり、通知表上の内申点(45点満点)が、最終的には300点満点に換算されることになります。
素内申1点の価値
通知表の内申点1点(45点満点中)が持つ価値を計算すると、
- 45点 → 65点に換算
1点あたりの増加分:国数英理社は等倍、実技4教科は2倍 - 65点 → 300点 に換算
1点あたりの増加分:300 ÷ 65 = 約4.62点
つまり、換算内申点が1点上がると、入試時の300点満点換算では、約4.62点増えることになります。国数英理社は等倍、実技4教科は2倍となっていますので、主要5教科で素内申が1上がれば300点満点換算で約4.62点、実技4教科は2倍ですので、約9.24点上がることになります。
学力試験の影響との比較
学力試験は国数英理社各100点の500点満点の得点を700点に換算します。
- 1点あたりの増加分:700 ÷ 500 = 1.4点
すなわち、学力試験で1点上げるのと比べて、内申点(45点満点)を1上げると、約3.3倍(4.62 ÷ 1.4)の影響があることになります。言い換えると、主要5教科(国数英理社)の素内申1の上昇は学力検査での約3.3点分、実技4教科の素内申1の上昇は学力検査で約6.6点分を上乗せしているに等しいと言うことです。
私立高校の推薦入試における内申点の重要性
私立高校の推薦入試では、多くの学校が内申点の基準を設けています。例えば「内申点が○○点以上ないと受験できません」というようなものです。ですので、自分が行きたい学校の内申基準をしっかり確認して、日頃の学習や学校生活で良い評価をもらえるように頑張ることが大切です。
私立高校入試の併願優遇における内申点の重要性
私立高校には「併願優遇」という制度があります。これは、内申点が学校の決めた基準より高ければ、当日の試験を受けるだけで合格できたり、試験の点数に数十点プラスしてもらえたりする制度です。志望校の内申基準をちゃんと確認して、それを超えられるように頑張ることが重要です。
\家庭学習の質を高めたい方へ/
自宅学習で成果を出すには、勉強の「やり方」だけでなく「教材選び」も重要です。
スタディサプリ、Z会など、自宅学習でも使える人気の学習サービスを比較した記事や、部活と勉強を両立した先輩たちの声もぜひ参考にしてみてください。
👉 スタサプは中学生におすすめ?評判・料金・活用法を解説
👉 Z会タブレットコースの特徴と口コミ|難関校対策にも対応
👉 Z会とスタサプどっちがいい?中学生向け徹底比較
👉 ”オンライン家庭教師”コースもある個別指導のWAMってどんなサービス?
👉 【文科省調査】中学生の勉強時間はどのくらい?平均と目標の差とは
👉 部活と勉強は両立できる?先輩たちの工夫と学習法を紹介
内申点の基礎知識を理解しよう
内申点は「観点別学習状況の評価」という仕組みに基づいて決定されます。各教科の単元ごとの評価は「A」「B」「C」の3段階で記され、明確な基準に従って評価されます。この評価の仕組みを理解することが、効果的な内申点アップの第一歩となります。
「観点別学習状況の評価」とは何か?評価の仕組みを解説
「観点別学習状況の評価」は、以下の3つの観点から総合的に行われます。
知識・技能
- 各教科で学んだ知識や技能がどれだけ身についているか
- 学んだことを他の場面でも使えるか
- 基本的な内容をどれだけ理解し、使いこなせているか
学んだ知識や技能を適切に活用できるか、また日常生活や他教科での応用ができるかも評価されます。たとえば、理科で学んだ知識を社会科の環境問題に活用するなど、横断的な学びも重視されます。
思考・判断・表現
- 問題を解決するために必要な考える力
- 知識を使って問題を解決する力
- 自分の考えをうまく伝える力
知識を活用し、課題を解決するために必要な思考力や表現力を身につけているかを評価します。具体的には、授業中の発表やディスカッションへの参加が重要な指標となります。
主体的に学習に取り組む態度
- 学習への意欲と、自分で学習を調整する力
- 課題に興味を持ち、最後まで取り組む姿勢
- 自分の学習状況を把握し、改善しようとする努力
自分の学習状況を把握し、目標を持って努力する姿勢を評価します。例えば、授業で積極的に発言したり、提出物を丁寧に仕上げたり、学習の記録をしっかりつけたりすることが評価されます。
観点別学習状況の評価と評定の関係
中学校では、各教科での評価が最終的に「評定」という形で成績表に反映されます。評価は上記の3観点に基づいて行われ、各単元ごとに、A(十分満足できる)、B(おおむね満足できる)、C(努力を要する)がつけられます。それらを総合して、学期や年度の1〜5の評定にまとめられます。たとえば、文部科学省の指針では以下の基準が示されています。
- 観点がすべてAの場合:評定は「4以上」となる(3、2、1にはならない)
- 観点がすべてBの場合:評定は「3」となる(5、4、2、1にはならない)
- 観点がすべてCの場合:評定は「2以下」となる(5、4、3にはならない)
観点別学習状況の評価Aについては、Bに近いAもあり各観点がすべてAでも必ずしも「5」になりません。同じように評価のCについてもBに近いCもあるため、各観点がすべてCでも、必ずしも「1」になりません。
ただし、各観点での詳細な実現状況や努力の様子も考慮されるため、必ずしも観点別評価が全て一致する必要はありません。努力が認められれば、観点の評価が多少ばらつきがあっても高い評定がつく場合があります。
観点別学習状況の評価の具体的な評価指標
この評価は、次のような具体的な方法で行われます。
ペーパーテストによる評価
- 定期テスト
- 単元テスト
- 小テスト
観察・対話による評価
- 授業中の発言
- グループ活動での様子
- 学習態度
提出物による評価
- ノート
- レポート
- 作品
定期テスト対策で確実に内申点を上げる
定期テストは「知識・技能」の評価で大切な要素です。ただし、単に点数が取れるだけでなく、考える力や表現する力も評価のポイントになります。東京都教育委員会が公表している資料(児童・生徒の学習評価)をもとに効果的なテスト対策の方法を考えてみます。
テスト前の効果的な学習計画の立て方
評価方法に基づいた効果的な学習計画を立てることが重要です。具体的には
知識・技能の確認
- 教科書や学習指導要領で示された目標をチェック
- 基礎的な知識がどれくらい身についているかを確認
- 技能がどれくらい使えるようになっているかを確認
思考力・判断力を養う学習
- 問題の解き方を考える練習
- 知識を使って応用問題に挑戦
- 自分の考えを筋道立てて説明する練習
特に重要なのは、「主体的に学習に取り組む態度」を示すことです。これには、
- 自分で学習計画を立てて管理する
- 予習・復習を毎日続ける
- 分からないところは積極的に質問する
などが含まれます。
テスト後の振り返りと成績アップのポイント
テスト後の振り返りは、「主体的に学習に取り組む態度」を示す重要な機会です。
自己評価の実施
- 目標はどれくらい達成できたか
- 学習方法は効果があったか
- 改善が必要なところはどこか
学習記録の活用
- 学習ノートを見直す
- 間違えた問題をしっかり分析する
- 次の学習計画に活かす
この振り返りを通じて、
- 知識・技能がどれくらい身についたか
- 考える力や表現する力がどれくらい伸びたか
- 学習への取り組み方はどうだったか
を確認し、次の学習につなげることが大切です。
💻 自分に合った勉強スタイルを見つけよう
塾・通信教育・家庭教師など、学び方はさまざま。
それぞれの特徴を知って、自分に合う方法を選ぶことが成績アップの近道です。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】
![]()
👉 【難関対策】難関校対策に定評のある通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【1対1】マンツーマンの個別指導で弱点克服 1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】 ![]()
👉 【東大の力】東大生講師から学べるオンライン指導 【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
👉 【内申UP】対面で安心して教わりたい人は 家庭教師のノーバス ![]()
授業態度ではここに気をつけよう!
授業中の評価は、「観点別学習状況の評価」として組織的に行われます。教育委員会の資料を見ると、知識だけでなく、考える力や学習に取り組む態度まで、いろいろな面から評価されることが分かります。
知識・技能の観点
- 各教科で学んだ内容をどれだけ理解しているか
- 学んだ知識を他の場面でも使えるか
- 基本的な技能がどれだけ身についているか
思考・判断・表現の観点
- 課題を解決するためにどう考えるか
- 適切な判断ができるか
- 自分の考えをうまく表現できるか
主体的に学習に取り組む態度の観点
- 授業に積極的に参加しているか
- 課題に最後まで取り組んでいるか
- 自分の学習をより良くしようと努力しているか
特に重要なのは、これらの能力を日々の授業の中で計画的に示していくことです。
発言・発表で評価を上げるコツ
評価方法の一つである「観察・対話による評価」では、以下のような点が重視されます。
主体的な学習態度の表現
- 積極的に質問や発言をする
- グループ活動で協力する
- みんなで意見を出し合い、話し合いに参加する
思考・判断・表現の実践
- 筋道立てて意見を言う
- 他の人の意見に対して建設的な意見を返す
- 学んだ知識を使って発言する
ノートの取り方と提出物の質を高める方法
提出物は「パフォーマンス評価」の重要な要素として扱われます。
ノート作成のポイント
- 授業の内容を正確に記録する
- 自分の考えや疑問点も書き込む
- 学習の振り返りもしっかり書く
提出物の評価基準
- 基礎的な知識がちゃんと身についているか
- どのように考えたのかが分かるか
- 表現が適切か
- 期限をしっかり守っているか
これらの評価は、「妥当性」「信頼性」の観点から、教師間で共通理解のもと行われます。
教科ごとの内申点アップ戦略
内申点を上げるには、教科ごとの評価基準を理解して、それに合わせた対策を立てることが大切です。各教科で評価されるポイントを押さえて、具体的な取り組みを実行していきましょう。主要5教科と実技4教科に分けて説明します。
主要5教科の内申点アップ戦略
1. 国語
ポイント
- 漢字や文法の基礎力
- 考えを文章で表現する力
- 読解問題を正確に解く力
対策
- 漢字と文法を完璧にする
漢字や文法の問題は、覚えればきちんと点が取れる分野です。テスト前には問題集でたくさん練習して、全問正解を目指しましょう。 - 記述練習を積む
「○○について自分の考えを書きなさい」という問題は高得点が狙えます。模範解答を参考に、自分の答えを見直す習慣をつけましょう。 - 音読を行う
音読は読解力や言葉の力を高めます。教科書の文章を声に出して読むことで、文章の組み立てが分かりやすくなります。
2. 数学
ポイント
- 基礎問題を確実に解く
- 応用問題に対応する力
- 答案の途中式や計算過程を丁寧に書く
対策
- 公式を使いこなす
計算ミスを防ぐため、公式をただ覚えるだけでなく、実際にどのように使うのかを理解しましょう。 - 間違えた問題を復習する
一度間違えた問題は繰り返し解き直し、「なぜ間違えたのか」を明確にします。同じミスを防ぐことで得点アップが期待できます。 - 途中式をしっかり書く
正答にたどり着かなくても、途中式が書かれていれば部分点がもらえることがあります。計算過程を省略せず、丁寧に書く習慣をつけましょう。
3. 英語
ポイント
- 単語と文法の力
- リスニングの力
- 英作文を正確に書く力
対策
- 単語と文法の徹底暗記
英語力の基礎は単語と文法です。毎日少しずつ暗記を進め、教科書で扱うすべての単語や文法を理解しましょう。 - リスニング練習を増やす
教科書の音声やリスニング教材を活用し、耳で英語を覚えます。何度も聞いて慣れることで、リスニング問題の得点が上がります。 - 基本文型で英作文を練習
難しい表現に挑戦する必要はありません。「主語+動詞+目的語」などの基本文型を使い、ミスを減らした正確な英作文を目指します。
4. 理科
ポイント
- 実験や観察の記録と考察
- 用語や原理の理解
- 計算問題を正確に解く力
対策
- 実験結果の記録を丁寧に
実験や観察の記録は評価の対象になることがあります。データを正確に記録し、分かりやすく論理的な考察を書く練習をしましょう。 - 用語の暗記と原理の理解
理科の用語や公式を暗記するだけでなく、その背景にある仕組みや原理を理解することが大切です。例えば、「光合成のプロセス」などを自分の言葉でしっかり説明できるようになっているといいですね。 - 計算問題を重点的に復習する
計算問題は確実に点が取れる分野です。公式を覚えて、実際に問題を繰り返し解くことで得点力を高めます。
5. 社会
ポイント
- 歴史や地理、時事問題の知識
- 出来事の原因と影響の理解
- 記述問題を論理的に書く力
対策
- 年号や地名の暗記
歴史では重要な年号や出来事を、地理では地名や特徴をしっかり覚えます。自分で小テストを作って練習するのも効果的です。 - 背景を理解する
歴史や地理の出来事について、「なぜそうなったのか」「どんな影響があったのか」を考えると、記憶に残りやすくなります。 - 記述力を鍛える
社会の記述問題では、「結論→理由→具体例」の順で書くと説得力が増します。例えば、「○○は××だから重要です。その具体例として△△があります」という形で書く練習をしましょう。
実技4教科の内申点アップ戦略
1. 音楽
ポイント
- 歌や演奏の表現力
- 楽譜や音楽の理論の理解
対策
- 課題曲を徹底練習
課題曲を何度も歌い、正しい音程とリズムを意識して練習します。ピアノ伴奏がある場合は、それに合わせる練習も忘れずにしましょう。 - 楽譜の理解を深める
音符や記号の意味を理解して、演奏に活かします。楽譜が読めるようになると、自然と先生からの評価も高くなります。
2. 美術
ポイント
- 作品の完成度とオリジナリティ
- 制作過程の丁寧さ
対策
- 下書きを丁寧に行う
作品の出来は下書きで大きく変わります。時間をかけて、構図やバランスを調整しましょう。 - 先生のアドバイスを取り入れる
途中経過を見せて、先生からのアドバイスをもとに、求められていることを理解し、改善を重ねましょう。
3. 保健体育
ポイント
- 運動への取り組む姿勢
- 基本的な技術の習得
対策
- 全力で取り組む
運動が得意でなくても大丈夫です。練習や試合に一生懸命取り組むことで、「主体的に学習に取り組む態度」として評価されます。 - ルールを理解する
スポーツのルールや作戦を理解することで、練習や試合でより良い動きができるようになります。
4. 技術・家庭科
ポイント
- 課題や作品の出来栄え
- 手順の正確さと努力
対策
- 家庭科では丁寧さを意識
縫い物や料理の盛り付けなど、仕上がりの丁寧さが大切です。また、レシピや手順をしっかり守ることで評価が上がります。 - 技術では計画的に作業を進める
ものづくりでは、計画を立てて、順序通りに作業することで完成度が上がります。設計図やデザインの段階から丁寧に取り組みましょう。
各教科の評価ポイントを意識し、日々の取り組みを改善することで、内申点アップを目指しましょう!
日常生活での内申点対策
東京都教育委員会公表の資料からは、評価は単なる学習成績だけでなく、「主体的に学習に取り組む態度」が重視されていることが分かります。
部活動での態度と内申点の関係
部活動は「主体的に学習に取り組む態度」を評価する重要な機会です。
ポイント
- 毎日続ける努力
- チームワークと協力する心
- 課題に取り組む姿勢
具体的な取り組み方
- 毎日の練習に真剣に参加する
- 後輩の面倒を見たり、教えたりする
- 大会や発表会で成果を出す
学校行事・委員会活動の活用法
学校行事や委員会活動は「思考・判断・表現」の力を示す絶好の機会です。積極的に関わっていきましょう。
知識・技能の活用
- 企画や運営で実践的な力を見せる
- コミュニケーション能力を発揮する
- 問題を解決する力を見せる
主体的な取り組み
- リーダーシップを発揮する
- 新しいアイデアを提案する
- 責任を持って行動する
基本的な生活習慣の見直し
評価の「信頼性」を高めるためには、日常的な取り組みが重要です。
生活リズムの確立
- 規則正しい睡眠習慣をつける
- 計画的に学習時間を確保する
- 健康管理をしっかりする
学習環境の整備
- 整理整頓を習慣にする
- 集中して勉強できる場所を作る
- 学習道具をきちんと管理する
特に重要なのは、これらの取り組みを通じて、
- 自分で管理する力を高める
- 学習への意欲を保つ
- 目標に向かって計画的に取り組む
を示すことです。
先生たちは、これらの日々の取り組みを総合的に評価しているということを意識して行動することが大切です。
評価を下げやすい要注意ポイント
評価を上げることだけでなく、自分の評価を下げてしまう行動にも注意が必要です。以下のポイントに気をつけましょう。
ペーパーテストでの注意点
- 基礎的な知識がしっかり身についているか確認する
- 考える力を問う問題にしっかり取り組む
- 自分の考えを書く問題を大切にする
日常の学習活動での注意点
- 提出物は丁寧に仕上げ、期限を守る
- 授業中の態度を良好に保つ
- グループ活動には積極的に参加する
内申点アップのための長期的な取り組み
東京都の資料で示された評価の観点と方法を踏まえ、長期的な視点での内申点アップ戦略を考えてみます。
学年別の内申点対策スケジュール
評価の一貫性と信頼性を意識した、学年ごとの取り組みが重要です。
1年生での対策
基礎的な学習態度の確立
- 3つの評価観点を理解する
- 学習記録をつける習慣をつける
- 基本的な学習方法を身につける
評価方法への対応力を養う
- テストの取り組み方を身につける
- 提出物の質を上げる
- 授業に積極的に参加する
2年生での対策
評価の観点を意識した学習
- 知識・技能をしっかり身につける
- 考える力・判断する力を強くする
- 主体的な学習態度を深める
多面的な評価機会の活用
- 定期テストで成果を出す
- 授業中の発表や討論に参加する
- 課題研究やレポートに取り組む
最後まで諦めない!内申点アップのモチベーション維持法
主体的に学習に取り組む態度の観点から見ると、内申点アップには、以下のような段階的な取り組みが効果的です。
まず、定期的に自己評価を続けることが大切です。毎日の学習の様子をしっかり確認して、「この部分はできるようになったな」「ここはもっと頑張らないと」といった具合に、自分の課題や改善点をはっきりさせていきます。また、自分で決めた目標にどのくらい近づけたかを確認することで、より効果的な学習につなげることができます。
次に、計画的な学習管理が欠かせません。「今週は英語のテストがあるから、この部分を重点的に」といった具合に、具体的な学習計画を立てて実行することが基本です。さらに、定期的に「この勉強方法は合っているかな?」と振り返りをして、必要であれば計画を見直したり、新しい勉強法を取り入れたりすることで、着実に力をつけることができます。
そして、評価を上げるための具体的な取り組みも忘れずに。各教科で「先生はどんなところを見ているのかな?」と考え、目標を立てましょう。例えば、数学なら「計算の途中式もしっかり書く」、国語なら「考えの理由付けを丁寧に書く」といった具合です。このような目標に向かって毎日コツコツ努力し、その成果を授業や提出物でしっかり見せることで、評価アップにつながります。
このように、知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度という3つの観点を意識しながら、計画的に続けて頑張ることが、内申点アップへの確実な道なのです。先生たちは、みなさんの日々の努力をしっかり見ています。一歩一歩、着実に前へ進んでいきましょう。
憧れの高校に入りたい。でも、勉強に不安があるあなたへ
放課後はハードな練習、週末は試合や遠征。
部活のに全力を注ぐ毎日を送りながら、「塾に通う時間がない」「勉強が後回しになってしまう」と悩んでいる生徒も少なくありません。
でも、勉強だって本気でがんばりたい。
そんな部活生に心強い味方となるのが、オンライン個別指導の【そら塾】です。
部活や学校の課題で忙しい中高生が、最短で成績を上げることに特化した個別指導サービス。通信教材や家庭教師が合わなかった人や、これから本気で勉強を始めたい人にもおすすめです。
部活と勉強、どちらも全力で取り組みたいあなたへ、今注目の学習サービスです。
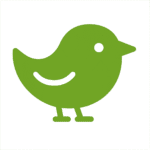 トリトリ
トリトリ部活に定期テストに忙しい中学生でも大丈夫!。オンライン個別指導の【そら塾】なら、あなたの都合に合わせてスケジュールが組めるよ!
🏫 忙しい中高生専用!内申点アップのための個別戦略
通塾不要の完全オンライン個別指導なので、帰宅が遅い日や学校行事が忙しい時期でも安心です。
そら塾なら、あなたのスケジュールに合わせた学習計画と、内申点アップに直結する専門指導を無料で体験できます。
<参考データ>
児童・生徒の学習評価(評価・評定)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/advancement/evaluation