令和7年度東京都立高等学校入学者選抜合格発表
東京都教育委員会より「令和7年度東京都立高等学校入学者選抜合格発表」がリリースされました。
令和7年度東京都立高等学校入学者選抜合格発表
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/03/2025030301
2025年度(令和7年度)の東京都立高等学校入学者選抜の合格状況は以下のようになりました。
全日制高校の合格状況
- 募集人員:29,976人
- 受検人員:35,877人
- 合格人員:28,188人
- 実質倍率:1.27倍
普通科全体の合格状況
- 募集人員:23,937人
- 受検人員:29,856人
- 合格人員:22,973人
- 実質倍率:1.30倍
専門学科全体の合格状況
- 募集人員:4,413人
- 受検人員:4,094人
- 合格人員:3,603人
- 実質倍率:1.14倍
総合学科の合格状況
- 募集人員:1,626人
- 受検人員:1,927人
- 合格人員:1,612人
- 実質倍率:1.20倍
定時制課程単位制(チャレンジスクール等)の合格状況
- 募集人員:1,490人
- 受検人員:1,972人
- 合格人員:1,428人
- 実質倍率:1.38倍
前年度比では全体的に倍率が下がっており、全日制合計の実質倍率は昨年の1.35倍から1.27倍に減少しています。
2025年度都立高校一般入試(学力検査)の合格状況一覧(普通科+α)
23区都心部の高校の一般入試の合格倍率(実質倍率)一覧

都心部の高校全体では、多くの学校で前年と比較して合格倍率が下がる傾向が見られました。特に顕著だったのは新宿高校(0.42ポイント減)と向丘高校(0.45ポイント減)と、大幅に倍率が低下しています。
一方で、伝統校である日比谷高校は受検者396人、合格者272人で合格倍率1.46倍と前年比0.13ポイント増加しました。同様に戸山高校も合格倍率1.69倍と前年から0.14ポイント上昇しています。これらの学校は競争率が高まる傾向にあります。
時系列で見ると、日比谷高校は校長会調査時の1.42倍から最終応募時には2.01倍まで上昇し、最終的な合格倍率は1.46倍となりました。この大きな変動は受験生の志望校変更(国立・私立の最難関高校の合格のため受検を辞退)が活発に行われたことを示しています。
また、広尾高校は合格者数が前年より28人増加し、合格倍率は1.46倍と前年から0.33ポイント減少しました。豊島高校は願書受付時の倍率が2.23倍と都心部では最も高く、人気が集中したことがうかがえます。
受検時の倍率と最終合格倍率を比較すると、三田高校(受検時1.60倍→合格倍率1.57倍)や戸山高校(受検時1.74倍→合格倍率1.69倍)など、ほぼ同水準で推移した学校が多く、大きな混乱はなかったようです。
総じて、都心部の高校では一部の伝統校で競争率が高まる一方、多くの学校では前年より緩和される傾向が見られました。
23区東部の高校の一般入試の合格倍率(実質倍率)一覧

23区東部の都立高校入試データを分析すると、全体的に前年と比較して受検者数が減少し、合格倍率も低下している傾向が見られます。
葛西南高校や忍岡高校、足立新田高校などは合格倍率が1.00倍となり、実質的な競争がなかった状況です。特に葛西南高校は受検者数が前年から89人も減少し、願書受付時点で既に倍率0.53倍と定員割れの状態でした。
上野高校は合格倍率1.75倍と東部地区では高い水準を維持しており、願書受付時には2.02倍まで上昇していました。江戸川高校も合格倍率1.42倍と一定の人気を保っています。
時系列変化が顕著だった学校としては深川高校が挙げられ、校長会調査時の1.75倍から最終応募時には1.82倍と上昇し、合格倍率は1.61倍となりました。
また、本所高校や城東高校、墨田川高校は前年より合格倍率が大きく低下しており、それぞれ0.49ポイント減、0.40ポイント減、0.15ポイント減となっています。足立東高校も前年と比べて0.31ポイント減と大幅に競争率が緩和されました。
総じて、23区東部の高校では一部の人気校を除いて競争率の緩和傾向が顕著であり、地域による志願動向の差も見られました。
23区西部の高校の一般入試の合格倍率(実質倍率)一覧

23区西部の都立高校入試データを分析すると、学校間で競争率に大きな格差が生じていることが明らかです。
最も特徴的なのは豊多摩高校で、受検者数が478人と前年より71人増加し、合格倍率も1.87倍と前年から0.27ポイント上昇しています。特に願書受付時には2.27倍という高倍率を記録し、西部地区で最も人気が集中していました。
同様に高い競争率を示したのは芦花高校で、合格倍率1.81倍となっています。時系列で見ると、校長会調査時の1.72倍から願書受付時には2.07倍まで上昇し、受検者の志望校集中が顕著でした。
北園高校も合格倍率1.68倍と比較的高く、願書受付時には1.90倍まで上昇していました。石神井高校も合格倍率1.65倍と安定した人気を維持しています。
一方で、八潮高校、大森高校、田柄高校、光丘高校などは合格倍率1.00倍と競争がなく、定員ぴったりの状況でした。特に大森高校は願書受付時点で0.44倍と大幅な定員割れの状態でした。
目黒高校は前年比0.44ポイント減と大きく合格倍率が低下し、1.12倍となりました。同様に国際高校(一般)も前年から0.48倍減少し、1.46倍となっています。
興味深い動向として、杉並区の松原高校は合格倍率が前年から0.22倍上昇し、1.23倍となりました。願書受付時の1.18倍から最終応募時には1.48倍まで上昇しており、志願動向の変化が見られました。
総じて、23区西部では一部の人気校に志願者が集中する一方で、多くの学校では前年と比較して競争率が緩和される傾向が見られました。
多摩地区北部の高校の一般入試の合格倍率(実質倍率)一覧

多摩地区北部の都立高校入試データを分析すると、特に立川市の高校で顕著な競争率の上昇が見られました。
最も特徴的なのは立川高校の創造理数科で、合格倍率が3.97倍と前年から1.67倍も急上昇しています。時系列で見ると、校長会調査時の2.05倍から最終応募時には4.51倍まで急激に上昇し、多摩地区全体で最も高い競争率となりました。立川高校の普通科も併願を想定すると合格倍率がおそらく1.87倍となり、前年から0.36ポイント上昇。立川高校全体で人気が高まっていることが分かります。
対照的に、府中高校は合格倍率が前年から0.51ポイント大幅に低下し、1.25倍となりました。また府中西高校も合格倍率1.00倍と競争なしの状況です。
調布市の神代高校は合格倍率1.82倍と前年から0.19ポイント上昇し、北部地区では立川高校に次ぐ高い競争率となっています。特に校長会調査時の1.95倍から願書受付時には2.09倍まで上昇し、人気の高さが表れています。
国分寺高校も合格倍率1.51倍と前年から0.22ポイント上昇しており、最終応募時には1.67倍の倍率を記録しました。同様に狛江高校も合格倍率1.64倍と前年から0.19ポイント上昇し、願書受付時には1.85倍という高い倍率になっています。
一方で、小平高校の外国語コースは合格倍率が前年から0.58ポイント大幅に低下し、1.09倍となりました。同様に多摩科学技術高校も前年から0.41ポイント低下し、競争のない1.00倍となっています。
地域による志願動向の差も顕著で、立川市、調布市、狛江市の高校は比較的人気が高い一方、府中市、小金井市、小平市の高校は全体的に競争率が低下しています。
総じて、多摩地区北部では一部の人気校(立川高校、神代高校、狛江高校など)に志願者が集中する傾向が強まっており、学校間の競争率格差が拡大しています。特に立川高校創造理数科の願書受付時4.57倍という最終応募時の倍率は、東京都全体でも突出して高い水準となっています。
多摩地区南部・西部、島しょ部の高校の一般入試の合格倍率(実質倍率)一覧

多摩地区南部・西部および島しょ部の都立高校入試データを分析すると、全体的に競争率が低く、多くの学校で定員割れや合格倍率1.00倍の状況が見られます。
特徴的なのは、八王子市の八王子東高校で、受検者数356人と前年比36人増加し、合格倍率1.38倍と安定した人気を維持しています。時系列で見ると、最終応募時には1.52倍まで上昇していました。
町田市の成瀬高校も合格倍率1.32倍と前年から0.25ポイント上昇しており、最終応募時には1.41倍と比較的高い競争率を示しています。同じく町田市の小川高校も合格倍率1.16倍と前年比0.04ポイント減にとどまり、一定の人気を保っています。
日野市の日野高校は志願者が減少したものの、合格倍率1.35倍と比較的高い水準を維持しており、願書受付時には1.47倍まで上昇していました。同市の南平高校も合格倍率1.35倍と前年から0.12ポイント減少したものの、一定の人気を保っています。
一方で、多くの学校で合格倍率1.00倍の状況が見られます。片倉高校の造形美術コース、松が谷高校の外国語コース、翔陽高校、野津田高校、永山高校、多摩高校、羽村高校、秋留台高校、五日市高校、八丈高校などが該当します。これらの学校では実質的な競争がなかったことを示しています。
特に顕著なのは、志願者数の大幅な減少です。日野高校は前年から69人減、日野台高校は53人減、永山高校は70人減、秋留台高校は66人減と大きく志願者を減らしています。また、多くの学校で願書受付時点から定員割れの状況が見られ、例えば五日市高校では0.45倍、八丈高校では0.36倍と深刻な定員割れとなっています。
南部・西部地域では学校間の格差も大きく、八王子東高校や日野高校などの一部の学校に志願者が集中する一方、多くの学校では志願者確保に苦戦している状況が浮き彫りになっています。
また、競走倍率の変動が少ない点も特徴的で、校長会調査時から受検時まで大きな変動がない学校が多く、志望校変更が少なかったことを示しています。
総じて、多摩地区南部・西部、島しょ部では一部の伝統校を除いて全体的に競争率が低く、多くの学校で志願者確保が課題となっていることが明らかです。
進学指導重点校・特別推進校・推進校の受検状況(募集人員・受検人員・受検倍率)



進学指導指定校の入試データを分析すると、全体的に高い競争倍率を維持していますが、学校間で差が見られます。
最も高い競争率を示したのは立川高校の創造理数科で、合格倍率3.97倍と突出しており、願書受付時には4.57倍という驚異的な数値を記録しました。続いて理数科と併願可能な立川高校の普通科(1.87倍)、豊多摩高校(1.87倍)が高い競争率となっています。
日比谷高校は合格倍率1.46倍で前年から0.13ポイント上昇し、戸山高校も合格倍率1.69倍と人気を維持しています。
対照的に、城東高校は前年から0.40ポイント大幅に倍率が低下し1.41倍に、新宿高校も0.42ポイント減少し1.69倍になりました。西高校も前年から0.15ポイント低下し1.27倍となっています。
青山高校(1.68倍)、小山台高校(1.34倍)、駒場高校(1.76倍)、国立高校(1.38倍)なども安定した競争率を維持しています。
時系列データを見ると、多くの進学指導指定校で校長会調査時から最終応募時にかけて倍率が上昇しており、難関国立・私立高校との兼ね合いや志望校変更による集中傾向が見られます。
全体として、都心部や多摩地区の一部進学指導指定校に志願者が集中する傾向が顕著であり、特に立川高校の人気が突出しています。
🏫 高校生活をより充実させるために、今から学びの準備を
校風や特色を調べながら「この学校に入りたい」と思ったら、勉強のペースづくりを始めるチャンス。
以下の学習サービスを活用すれば、授業理解・内申対策・基礎力アップを自宅で進めることができます。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】![]()
👉 【費用重視】月額1,815円~効率的に予習・復習できる動画教材なら スタサプ ![]()
👉 【難関対策】難関校志望者にも信頼される通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【内申UP】内申・定期テスト対策を家庭でサポート 家庭教師のノーバス ![]()
👉 【体験無料】実際の教師による安心サポートなら 家庭教師ファースト ![]()
👉 【東大の力】日比谷・西・国立など難関都立を目指すなら現役東大生の家庭教師数最大規模【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
私立高校の実質無償化の影響か、二極化進む都立高校人気
2025年度の都立高校入試では全体的に倍率が低下する中、立川高校が創造理数科・普通科ともに突出した人気を示しました。23区内では日比谷高校、戸山高校、豊多摩高校などの伝統校が安定した人気を維持しています。
2024年度からスタートした私立高校の実質無償化の影響が顕著に表れており、都立高校全体の倍率低下につながったと考えられます。特に中位レベルの高校で倍率低下が目立ち、競争率が大幅に緩和されました。私立高校専願志向が強まったことで、都立中位校への志願者が減少した可能性があります。
一方で、日比谷高校や立川高校、戸山高校など進学実績の高い上位校には依然として多くの受験生が集まり、倍率も維持または上昇しています。進学実績を重視する層は都立トップ校への志向を強めており、私立無料化の中でも競争力を保っていることがわかります。
地域別では23区都心部と多摩地区北部の一部校で高い競争率が見られる一方、多摩南部・西部や島しょ部では八王子東高校(1.38倍)を除いて全体的に低調でした。特に五日市高校(0.47倍)や八丈高校(0.41倍)など願書受付時点から定員割れの学校が続出しており、学校間・地域間格差が顕著です。
時系列で見ると、校長会調査時から最終応募時、受験時にかけて倍率が変動しており、志望校変更が活発に行われたことがわかります。特に進学実績の高い高校では最終応募時に倍率が上昇する傾向があり、受験生の「勝ち組校」志向が強まっていることがうかがえます。
普通科(1.30倍)と比較して専門学科(1.14倍)の人気は低調ですが、科学技術系の学科では競争率が高い傾向にあります。少子化と私立無料化の二重の影響を受け、都立高校入試における二極化現象がさらに進んでいるといえるでしょう。
この高校に入りたい。でも、勉強に不安があるあなたへ
校風や教育内容に魅力を感じても、多くの生徒は、
「このままの勉強法で内申点は足りるのか…」「いつ、誰に苦手科目を相談すればいいのか…」
という切実な不安を抱えています。
そんな不安を抱える中高生のために生まれたのが、オンライン個別指導の【そら塾】です。
自宅にいながら、プロの先生があなたのスケジュールとレベルに合わせて1対1で徹底指導。
部活や学校の課題で忙しい中高生が、最短で成績を上げることに特化した個別指導サービス。集団塾が合わなかった人や、これから本気で勉強を始めたい人にもおすすめです。
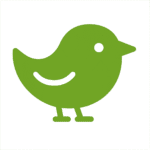 トリトリ
トリトリ「そら塾は、夜遅くなってもOK!苦手科目に特化した計画を無料で立ててくれるから、時間の不安が解消できるよ!」
🏫 忙しい中高生専用!内申点アップのための個別戦略
通塾不要の完全オンライン個別指導なので、帰宅が遅い日や学校行事が忙しい時期でも安心です。
そら塾なら、あなたのスケジュールに合わせた学習計画と、内申点アップに直結する専門指導を無料で体験できます。
<参照元>
ページ内のデータは東京都教育委員会発表資料・各高校のホームページやパンフレットを参照しています。しかしながら、参照したタイミングによっては速報データであったり、年度をまたぎ修正・変更となっている場合もありますので、正確なデータは東京都教育委員会、各都立高校の最新データをご確認ください。

