都立高校の受験を控えた中学生やその保護者の方にとって、内申点は大きな関心事の一つです。「どのくらいの内申点が必要か」「自分の地域の平均点はどうなのか」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。この記事では、東京都教育委員会の最新データを基に、内申点の仕組みから効果的な対策までを詳しく解説します。
内申点の基本的な仕組みを理解しよう
絶対評価方式による内申点
平成14年度から、内申点は「目標に準拠した評価(絶対評価)」で付けられるようになりました。これは従来の相対評価から変更され、生徒一人一人の学習到達度を学習指導要領の目標に照らして評価する方式です。
東京都の最新データ(都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年(令和5年12月31日現在)の評定状況の調査結果について)によると、9教科全体での評定状況は以下のようになっています。
- 評定5(十分満足できるもののうち、特に程度の高いもの):12.4%
- 評定4(十分満足できる):23.3%
- 評定3(おおむね満足できる):46.6%
- 評定2(努力を要する):13.5%
- 評定1(一層努力を要する):4.2%
ただしこの分布は各教科の分布を平均した数値であり、教科ごとに評価は独立しているわけですから、オール5の生徒が12.4%いるという説明ではないことに注意する必要があります。
教科別の平均内申点を詳しく見る
先ほどの分布データを評点に置き換えてみると、教科ごとに特徴的な傾向が見られます。東京都全体で、都立入試の学科試験科目である国数理社英の5教科では、
- 国語:3.26
- 数学:3.18
- 理科:3.23
- 社会:3.25
- 英語:3.22
という平均値を示しています。一方、実技4教科では若干高めの評定傾向が見られ、
- 音楽:3.32
- 美術:3.33
- 保健体育:3.30
- 技術・家庭:3.29
となっています。これは、実技教科では授業への取り組み姿勢や意欲も重要な評価要素となっているためと考えられます。
いずれにせよ、すべての教科で平均評点が3.0を超えているわけですから、9教科27(オール3)では平均より低くなります。教科ごとの平均評点を足して、国数英理社の5教科で16.13、実技4教科で13.23、9教科で29.37を超えていると平均より高いことになってきます。
\家庭学習の質を高めたい方へ/
自宅学習で成果を出すには、勉強の「やり方」だけでなく「教材選び」も重要です。
スタディサプリ、Z会など、自宅学習でも使える人気の学習サービスを比較した記事や、部活と勉強を両立した先輩たちの声もぜひ参考にしてみてください。
👉 スタサプは中学生におすすめ?評判・料金・活用法を解説
👉 Z会タブレットコースの特徴と口コミ|難関校対策にも対応
👉 Z会とスタサプどっちがいい?中学生向け徹底比較
👉 ”オンライン家庭教師”コースもある個別指導のWAMってどんなサービス?
👉 【文科省調査】中学生の勉強時間はどのくらい?平均と目標の差とは
👉 部活と勉強は両立できる?先輩たちの工夫と学習法を紹介
地域別の内申点から見える特徴
先ほどのデータは「都内の621 校(中等教育学校、義務教育学校を含む)のうち、調査対象人員が40人以下の学校等を除いた575校を対象」としており、学校名は特定できないようになっていますが、市区町村ごとにデータがまとめられています。
地域別の特徴的な傾向
東京都の区市別データを詳しく分析すると、いくつかの興味深い特徴が浮かび上がってきます。区市別に各教科ごとに平均評点を算出し、5教科、実技4教科、9教科合計でトップ10を抽出してみました。

5教科(国・数・社・理・英)の平均値分析
全体平均が16.13点である中、以下の特徴が見られます、
<上位3地域が17点台を記録>
- 千代田区(17.22点)
- 文京区(17.18点)
- 小金井市(17.06点)
<注目すべき特徴>
- 学校数の多少(千代田区2校、世田谷区29校)に関わらず、安定した平均値を維持
- 文教地区として知られる地域が上位に位置する傾向
これらのデータから、単なる学校数ではなく、地域の教育環境や指導体制の充実度が評定平均に影響を与えていると考えられます。

実技4教科(音・美・体・技家)の傾向
全体平均が13.23点である中、以下の特徴が見られます。
<上位地域の状況>
- 国分寺市が14.30点で最も高い
- 千代田区(14.22点)
- 文京区(13.89点)が続く
- 上位2地域は14点台を記録
<特徴的な点>
- 学校数に関係なく(国分寺市5校、町田市19校)、安定した評定平均を維持
- 5教科の上位地域が、実技でも比較的上位に位置する傾向
このデータからは、実技教科においても教育環境の充実度が評定に影響を与えている可能性が示唆されます。また、主要5教科と実技4教科で、上位地域に一定の共通性が見られます。

5教科(国・数・英・理・社)+実技4教科(音・美・体・技家)の傾向
上記の5教科と実技4教科すべての合計データこのデータは、東京都の各区市における9教科(主要5教科+実技4教科)の評定平均値を示しています。全体平均が29.37点である中、以下の特徴が見られます。
<上位地域の状況>
- 千代田区が31.45点で最も高い
- 国分寺市(31.28点)
- 文京区(31.06点)が続く
- 上位3地域のみが31点台を記録
<特徴的な点>
- 上位10地域はすべて50点台を維持
- 主要5教科、実技4教科でも上位だった地域が、総合でも上位に位置する
このデータから、教科によらず一貫して高い評定平均を維持している地域があることがわかります。特に千代田区、国分寺市、文京区は、すべての区分で上位に位置しており、バランスの取れた教育環境が整っていることが示唆されます。
【PR】志望校合格のために!塾選びなら塾選
データから読み取れる教育環境の特徴
学校数と平均値の関係
興味深いのは、学校数の少ない地域(千代田区:2校、国分寺市:5校)で高い平均値が見られる点です。これは、
- きめ細かな指導が可能な環境
- 教員の目が行き届きやすい規模
- 学校間の連携が取りやすい
といった要因が考えられます。
地域の教育基盤との関連
上位に位置する地域には、以下のような共通点が見られます。
- 教育関連施設(大学、図書館等)が充実している
- 文教地区としての歴史がある
- 地域全体での教育支援体制が整っている
学校規模による分析
町田市など比較的学校数の多い地域(19校)でも、安定した平均値を維持しています。これは、
- 統一された教育方針の効果
- 学校間の情報共有や連携
- 地域全体での教育サポート体制
の成果と考えられます。
今後の展望と課題
このデータから、以下のような示唆が得られます。
- 教育環境の重要性
単に学校数や地域の規模だけでなく、教育環境の質が重要な要素となっています。特に、千代田区や文京区などの例は、充実した教育インフラの効果を示唆しています。 - 地域間格差への対応
データには一定の地域間格差が見られますが、これは必ずしも教育の質の差を直接的に示すものではありません。各地域の特性を活かした教育支援の取り組みが重要となっています。
💻 自分に合った勉強スタイルを見つけよう
塾・通信教育・家庭教師など、学び方はさまざま。
それぞれの特徴を知って、自分に合う方法を選ぶことが成績アップの近道です。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】
![]()
👉 【難関対策】難関校対策に定評のある通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【1対1】マンツーマンの個別指導で弱点克服 1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】 ![]()
👉 【東大の力】東大生講師から学べるオンライン指導 【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
👉 【内申UP】対面で安心して教わりたい人は 家庭教師のノーバス ![]()
内申点における評価のポイントと学習アプローチ
日々の授業での重要ポイント
内申点の評価において最も重要なのは、日々の授業への取り組み姿勢です。単に授業を受けるだけでなく、積極的な発言や質問、グループ活動への参加が評価の対象となります。
特に注目すべき評価ポイント
- 授業中の発言や質問の質と量
- ノートの取り方と内容の充実度
- 提出物の期限遵守と完成度
教科別の効果的な学習方法
主要5教科の学習アプローチ
国語(平均3.26)
日々の積み重ねが重要な教科です。以下のような取り組みが効果的です。
- 読解力向上のための継続的な読書習慣
- 文章構成を意識した要約練習
- 漢字や語彙の日常的な学習
- 授業での音読や発表への積極的な参加
数学(平均3.18)
基礎力の定着が重要です。段階的な学習を心がけましょう。
- 基本的な計算問題の反復練習
- 解法の手順を言葉で説明する習慣づけ
- 類題を数多くこなすことによる応用力の養成
- 学習内容の確実な理解と定着
英語(平均3.22)
4技能をバランスよく伸ばすことが大切です。
- 毎日の音読による発音とリズムの習得
- 基本文法の確実な理解と定着
- 単語・熟語の継続的な学習
- スピーキング・リスニング練習の習慣化
理科(平均3.23)
実験や観察を通じた理解が重要です。
- 実験・観察での積極的な参加と記録
- 理科用語の正確な理解と使用
- 日常生活との関連づけ
- 図表やグラフの読み取り練習
社会(平均3.25)
幅広い知識と理解が求められます。
- 地図や資料の積極的な活用
- 時事問題への関心と理解
- 年表を活用した歴史的つながりの把握
- 用語の意味理解と正確な使用
実技4教科の学習アプローチ
音楽(平均3.32)
実技と理論の両面からの取り組みが重要です。
- 基礎的な演奏技術の練習
- 音楽理論の理解
- 鑑賞活動での積極的な参加
- 表現活動への意欲的な取り組み
美術(平均3.33)
創造性と技術の両面を意識して。
- 基本的な技法の習得
- 創造的な表現への挑戦
- 作品鑑賞を通じた理解の深化
- 道具の適切な使用と管理
保健体育(平均3.30)
実技と保健の学習をバランスよく。
- 基礎体力の向上
- 各種運動技能の習得
- 保健分野での知識理解
- チームワークを意識した活動
技術・家庭(平均3.29)
実践的な学習を重視。
- 安全な作業手順の理解と実践
- 基礎的な技能の確実な習得
- 実習での積極的な取り組み
- 生活との関連づけ
学習の基本姿勢
どの教科にも共通する重要なポイントは、
- 予習・復習の習慣化
- 授業での積極的な参加
- ノートの丁寧な作成
- 提出物の期限厳守
- 疑問点の早期解消
になります。これらの取り組みを通じて、バランスの取れた学力向上を目指しましょう。評定平均のデータが示すように、各教科にはそれぞれの特性があります。その特性を理解し、適切な学習方法を選択することで、より効果的な学習が可能となります。
定期テストと提出物から内申点を考える
定期テスト対策の重要性
定期テストの結果は、内申点に大きな影響を与える重要な要素です。教科の理解度を測る客観的な指標として重視されるため、計画的な準備が欠かせません。
効果的なテスト対策としては、まずテスト2週間前から復習を始めることが理想的です。この時期から計画を立てることで、焦らず余裕を持って学習を進められます。特に苦手分野については早めに取り組み、教科書やノートを見直しながら、基礎からしっかりと理解を深めていきましょう。また、学校の過去問題は出題傾向を把握する上で貴重な資料となります。
提出物の管理と評価のポイント
提出物の評価は、生徒の学習態度や意欲を測る重要な指標となっています。評価のポイントは以下の3点です。
- 期限を必ず守る
提出期限の厳守は、時間管理能力と責任感の表れとして評価されます。早め早めの取り組みを心がけましょう。 - 内容を充実させる
単に提出すればよいというわけではありません。課題の意図を理解し、自分なりの工夫や考えを加えることで、より高い評価につながります。 - 提出前のチェック
誤字脱字のチェックはもちろん、課題の要件を満たしているか、説明が分かりやすいかなど、提出前の見直しが重要です。
特別活動と部活動の両立
学校行事への積極的な参加
特別活動も評価の重要な要素となります。
- 生徒会活動 :リーダーシップの育成、 企画力・実行力の向上、 協調性の醸成
- 学校行事 :体育祭・文化祭での役割遂行、 クラス活動への貢献、 集団での課題解決能力の向上
部活動と学習の効果的な両立
部活動と学習の両立は、時間管理能力の向上にもつながります。
- 時間の使い方 :朝学習の活用、休み時間の効率的な使用、部活動前後の学習時間確保
- 効率的な学習方法 :集中力を高める工夫 、短時間での復習習慣 、優先順位の付け方
効果的な内申点対策で目指す成長と学力定着
内申点の向上を目指すとき、最も大切なのは確実な学力の定着です。評定という数値にとらわれすぎるのではなく、日々の学習を通じて着実に力をつけていくことが重要です。
具体的な取り組みのポイントとして、第一に授業は学力向上の基本となります。単に教室にいるだけでなく、発言や質問を通じて積極的に参加することで、理解が深まります。また、提出物は学習態度を示す重要な要素です。丁寧に取り組み、期限を守ることで、学習内容の定着にもつながります。
定期テストは学習の成果を示す機会です。計画的な準備により、安定した結果を残すことができます。特別活動への参加も、協調性やリーダーシップを育む貴重な機会となります。
焦らず着実に、自分のペースで学力を伸ばしていくことが大切です。日々の積み重ねが、結果として適切な評価につながっていきます。学校生活全体を通じて、知識だけでなく、学ぶ力そのものを育てていきましょう。
このような総合的な取り組みを通じて、高校進学後にも活きる確かな力を身につけることができます。それこそが、内申点対策の本質的な意義といえるでしょう。
この高校に入りたい。でも、勉強に不安があるあなたへ
放課後はハードな練習、週末は試合や遠征。
部活のに全力を注ぐ毎日を送りながら、「塾に通う時間がない」「勉強が後回しになってしまう」と悩んでいる生徒も少なくありません。
でも、勉強だって本気でがんばりたい。
そんな部活生に心強い味方となるのが、オンライン個別指導の【そら塾】です。
部活や学校の課題で忙しい中高生が、最短で成績を上げることに特化した個別指導サービス。通信教材や家庭教師が合わなかった人や、これから本気で勉強を始めたい人にもおすすめです。
部活と勉強、どちらも全力で取り組みたいあなたへ、今注目の学習サービスです。
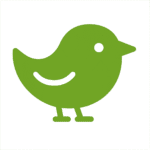 トリトリ
トリトリ部活に定期テストに忙しい中学生でも大丈夫!。オンライン個別指導の【そら塾】なら、あなたの都合に合わせてスケジュールが組めるよ!
🏫 忙しい中高生専用!内申点アップのための個別戦略
通塾不要の完全オンライン個別指導なので、帰宅が遅い日や学校行事が忙しい時期でも安心です。
そら塾なら、あなたのスケジュールに合わせた学習計画と、内申点アップに直結する専門指導を無料で体験できます。
<参考データ>
都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年(令和5年12月31日現在)の評定状況の調査結果について
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2024/03/2024032806

