都立高校入試において、注目を集める「倍率」。都立高校の入試では、12月の校長会調査(翌年1月発表)から3月の最終合格発表まで、実に5回もの異なる時期に倍率が発表されます。
一般に「倍率」として報道される数値も、実は発表される時期によって大きく異なります。校長会調査時点での私立志望も含めた第一志望調査の倍率なのか、願書提出時の応募倍率なのか、それとも志願変更後の最終応募倍率なのか。さらには実際の受検倍率や最終的な合格倍率まで、その数値の持つ意味は様々です。
例えば、ある学校の校長会調査時の倍率が高くても、私立高校の合格発表後に大きく下がることもあれば、逆に志願変更で倍率が上昇するケースもあります。このような倍率の変動を理解し、的確に読み解くことは、都立受験の戦略を立てる上で重要なポイントとなります。
本記事では、校長会調査から合格発表までの倍率の推移を詳しく分析。各校の特徴や傾向を明らかにすることで、これから受験に臨む中学生とその保護者の皆様に、より実践的な情報をお届けします。
都立高校の入試倍率の種類を理解しよう
都立高校入試における倍率には、発表される時期によって5種類があります。それぞれの倍率が持つ意味を理解することで、より戦略的な受験計画を立てることができます。
①校長会調査時の倍率(12月中旬調査時点_1月初旬発表)
12月に各中学校で実施され、1月上旬に発表されるこの調査は、入試シーズンの最初の重要な指標となります。生徒は担任の先生との面談を経て、その時点での第一志望校を申告します。この倍率の特徴は、
- 生徒の理想的な進路希望を反映している
- まだ模試などの判定を十分に考慮していない生徒も多い
- 校内での進路指導がまだ完全には反映されていないこともある
- 私立高校の併願を考えている生徒の動向が不確定
- 12月以降の成績の変化により、志望校が変更される可能性が高い
推薦入試の出願時期まで1か月、学力検査での出願時期まではまだ2ヶ月あり、この間に多くの変動要因があるため、参考程度の数値として捉えることが賢明です。
②応募倍率(都立入試の入学願書提出時点|推薦:1月下旬、学力検査:2月上旬)
応募倍率は、入試の種類によって異なる時期に発表されます。
<推薦入試の応募倍率>
推薦入試では1月上旬~中旬の願書受付後、1/26~1/27の入試実施の約1週間前(1月下旬)に推薦応募の倍率が発表されます。推薦入試の応募倍率は、一般的に学力検査よりも高倍率となる傾向(普通科の場合、学力検査が1.5倍前後に対し、推薦入試は3倍前後)にあります。高倍率となるのは、以下のような理由によるものです。
- 推薦枠は各高校の定員の1~2割程度と少なく、推薦入試に不合格でも学力検査を受験できる(2度チャレンジできる)ため、倍率が高くなりやすい
- 部活動や特別活動、資格取得などの実績を評価する選抜方法である
- 面接や小論文など、学力以外の要素も重視される
<学力検査の応募倍率>
1月下旬から2月上旬の入学願書受付開始直後に発表される倍率です。この段階での特徴は、
- 第一志望として本気で考えている生徒の動向が反映される
- 私立高校の合格発表前であるため、まだ流動的
- 併願優遇制度を利用する私立高校合格者の進路決定が未確定
- 各高校の人気度を測る初期の実質的な指標となる
- 学校によっては志願変更時に大きく数値が変動する可能性がある
推薦入試と学力検査、それぞれの応募倍率の違いを理解することは、受験戦略を立てる上で重要です。推薦入試は倍率が高くても学力検査に再度チャレンジが可能という特徴があり、自分の強みを活かせる機会として積極的に検討する価値があります。一方で、学力検査は相対的に倍率が低く、より多くの受験生に機会が開かれています。
これらの倍率は、その後の志願変更期間で変動する可能性があるため、あくまでも参考値として捉え、柔軟な受験計画を立てることが賢明です。
③最終応募倍率(入学願書取下げ・再提出時点_2月中旬)
前述の応募倍率をみて、入学願書の取下げ・再提出した志願変更期間後の最終的な志願状況を示す倍率です。実際の受験での競争率に近い指標となります。
- 私立高校合格者のおおよそ進路決定後の数値となる
- 志願変更による志望校の調整が完了している
- 受験生の最終的な志望状況を反映している
- 各校の実質的な人気度を最もよく表す指標となる
- 当日の欠席者数は予測できないため、若干の変動要因が残る
この倍率は、実際の入試での競争率を予測する上で最も信頼できる指標の一つとなります。
④受検倍率(学力検査時点_2月下旬)
実際に入学者選抜検査を受験した生徒数に基づく倍率です。インフルエンザなどによる欠席者や、私立高校への入学を決めた生徒の受験辞退などが反映されます。
実際に入学者選抜検査を受けた人数から算出される倍率です。この倍率の特徴としては、下記のような特徴があります。
- インフルエンザなどによる欠席者を除外した実数
- 私立高校に合格し、都立を受験しないことを決めた生徒も除外
- 実質的な競争率を最も正確に表す
- 合否判定の参考となる最も重要な指標
- 学校ごとの実際の競争の激しさを如実に反映
この倍率は、最終応募倍率とあまり変わらない高校もあれば、大きく変動する高校もあります。実際の入試における競争の実態を最も正確に示す数値として、重要な意味を持ちます。
⑤合格倍率(合格者発表時点_3月上旬)
最終的な合格発表時に確定する倍率です。この最終倍率の特徴は下記のようになります。
- その年の入試における真の競争率を示す
- 次年度の受験生の参考となる重要なデータとなる
- 学校の選抜度を示す客観的な指標として使用される
- 実際の入学者数とは若干異なる可能性がある
この倍率は、その高校の実質的な難易度を示す指標として、次年度以降の受験生の参考データとなります。実質的な競争率を示す合格発表時点での最終的な倍率です。私立や国立高校に進学、すなわち都立高校の合格を辞退する可能性を考慮して定員よりやや多めに合格とする高校も存在し、数値も受験倍率より高めとなる傾向にあります。
都立高校の入試倍率の活用と注意点
上述してきた倍率は、それぞれが異なる時期と状況を反映しており、単独で見るのではなく、総合的に判断することが重要です。特に注意すべき点として、
- 時期による変動を理解する
入試の進行に伴い、倍率は大きく変動する可能性があります。早い段階での倍率にとらわれすぎないことが重要です。 - 過去のデータとの比較
単年度の倍率だけでなく、過去数年間の推移を確認することで、より正確な傾向を把握できます。 - 学校の特性を考慮
普通科、専門学科、単位制など、学校の特性によって倍率の持つ意味が異なることがあります。 - 地域性の影響
学校の立地による地域性も倍率に大きな影響を与えます。通学圏内の中学生数の変動なども考慮する必要があります。 - 社会情勢の影響
経済状況や教育政策の変更により、公立志向が強まったり弱まったりすることで、倍率が変動することがあります。2025年度であれば、私立高校の実質無償化などの影響で校長会調査の倍率が大きく下がっています。
倍率は指標の一つ、自分らしい進路選択のために
1月初旬に発表される「校長会調査」は最初の意向調査として、1月下旬の「推薦入試応募倍率」は限られた定員での競争率として、2月上旬の「学力検査応募倍率」は本格的な受験動向の指標として、それぞれ重要な役割を果たします。その後、志願変更を経て「最終応募倍率」が確定し、実際の試験を経て「受検倍率」「合格倍率」が明らかになっていきます。
これらの倍率は、入試の進行とともに徐々に実態に近づいていく指標といえます。しかし、どの倍率も「参考値」として捉えることが重要です。なぜなら、倍率は競争率を示す数値ではありますが、個々の受験生の学力や適性、そして各高校の教育内容や特色を表すものではないからです。
受験生の皆さんには、これらの倍率を志望校選択の「参考データ」の一つとして活用しながら、自分の目標や将来の展望に基づいて進路を選択することをお勧めします。倍率に一喜一憂するのではなく、自分の学力を着実に伸ばし、志望校についての理解を深めていくことが、成功への近道となるでしょう。
最後に、都立高校入試は推薦入試と学力検査という2つのチャンスがあります。それぞれの特徴や倍率の傾向を理解した上で、自分に合った受験方式を選択し、計画的に準備を進めていくことが大切です。教師や家族としっかり相談しながら、自分らしい進路選択を実現してください。
この高校に入りたい。でも、勉強に不安があるあなたへ
校風や教育内容に魅力を感じても、多くの生徒は、
「このままの勉強法で内申点は足りるのか…」「いつ、誰に苦手科目を相談すればいいのか…」
という切実な不安を抱えています。
そんな不安を抱える中高生のために生まれたのが、オンライン個別指導の【そら塾】です。
自宅にいながら、プロの先生があなたのスケジュールとレベルに合わせて1対1で徹底指導。
部活や学校の課題で忙しい中高生が、最短で成績を上げることに特化した個別指導サービス。集団塾が合わなかった人や、これから本気で勉強を始めたい人にもおすすめです。
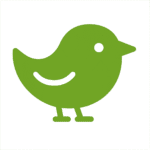 トリトリ
トリトリ「そら塾は、夜遅くなってもOK!苦手科目に特化した計画を無料で立ててくれるから、時間の不安が解消できるよ!」
🏫 忙しい中高生専用!内申点アップのための個別戦略
通塾不要の完全オンライン個別指導なので、帰宅が遅い日や学校行事が忙しい時期でも安心です。
そら塾なら、あなたのスケジュールに合わせた学習計画と、内申点アップに直結する専門指導を無料で体験できます。

