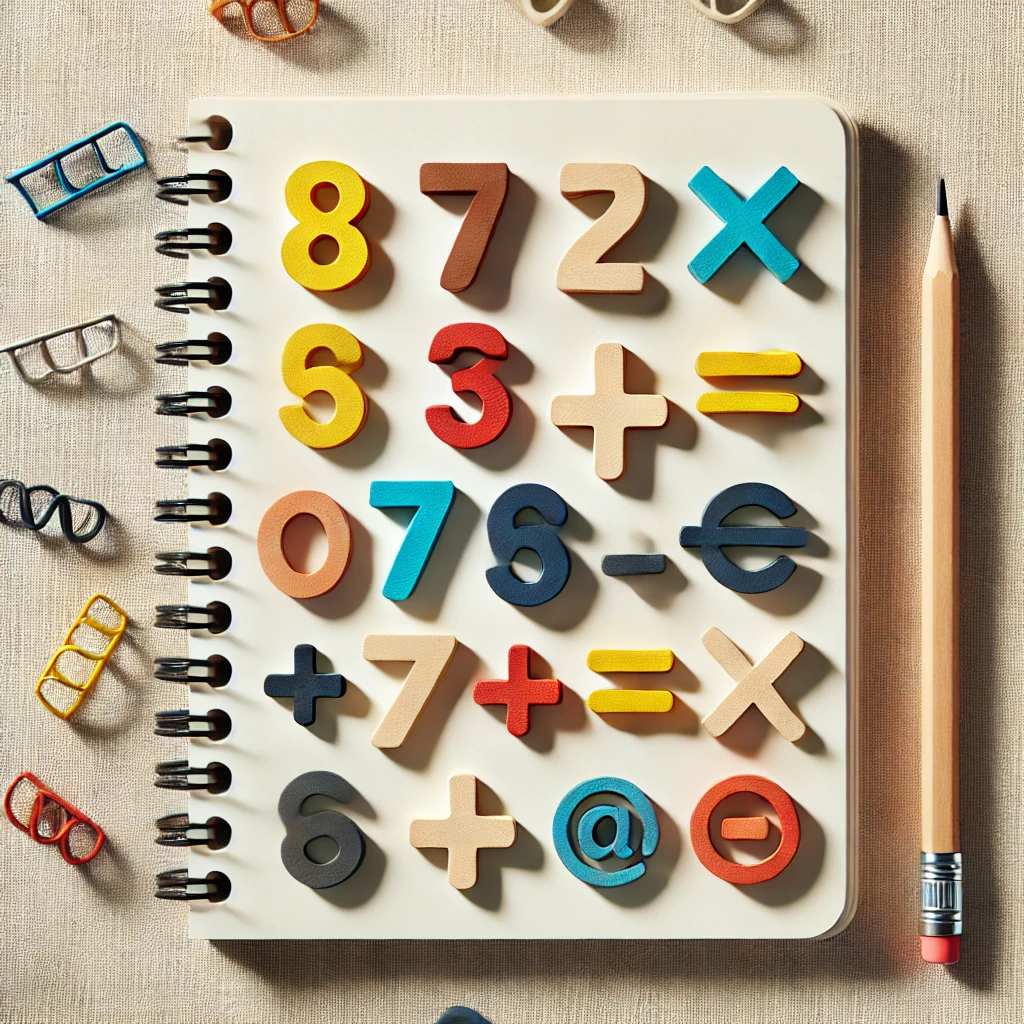高校受験を控える中学生や保護者の皆さんは、「併願優遇」という言葉を耳にすることがあるでしょう。特に東京都の私立高校受験では重要な制度ですが、受験学年になって初めて聞くことになるご家庭も多いでしょう。本記事では、併願優遇制度の基本から具体的な活用法まで、分かりやすく解説します。第一志望の都立高校と私立高校を効率よく併願するための戦略を身につけましょう。
併願優遇制度の基本知識
併願優遇制度は、受験生の不安を軽減し、より効率的な受験計画を立てるための重要な仕組みです。この制度を活用することで、「安全校」を確保しつつ第一志望の高校を目指すことができます。ここでは併願優遇の基本的な概念から、他の受験形態との違いまで詳しく解説していきます。
併願優遇制度とは何か
併願優遇制度とは、私立高校が定める基準を満たした生徒に対して、一般入試の際に優遇措置を提供する制度です。この制度の最大の特徴は、志望する高校(主に第一志望の都立高校)が不合格になった場合に、必ずその私立高校に入学することを条件としている点です。つまり、私立高校側は「都立高校が不合格なら必ず本校に来てください」という約束のもとで、入試における優遇を提供します(一部、志望順位に関わらず優遇する私立高校もあります)。
具体的な優遇内容は学校によって異なりますが、多くの場合は入試得点への加点や、内申点基準を満たしていれば、試験を受ければ合格とするなどの形で提供されます。この制度を利用するためには、各私立高校が設定している内申点の基準を満たしている必要があります。また、英検や漢検などの資格取得や部活動での実績など、学校独自の加点項目によって基準を満たすこともできる場合があります。メインとなる基準は内申点であり、ほとんどの場合、中学3年生の1学期(場合によっては2学期)までの成績が評価対象となります。
🏫 高校生活をより充実させるために、今から学びの準備を
校風や特色を調べながら「この学校に入りたい」と思ったら、勉強のペースづくりを始めるチャンス。
以下の学習サービスを活用すれば、授業理解・内申対策・基礎力アップを自宅で進めることができます。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】![]()
👉 【費用重視】月額1,815円~効率的に予習・復習できる動画教材なら スタサプ ![]()
👉 【難関対策】難関校志望者にも信頼される通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【内申UP】内申・定期テスト対策を家庭でサポート 家庭教師のノーバス ![]()
👉 【体験無料】実際の教師による安心サポートなら 家庭教師ファースト ![]()
👉 【東大の力】日比谷・西・国立など難関都立を目指すなら現役東大生の家庭教師数最大規模【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
併願優遇受験と一般受験(オープン)の違い
併願優遇と一般受験には、合格基準や受験のプロセスにいくつかの重要な違いがあります。以下の表で主な違いを比較してみましょう。
| 項目 | 併願優遇受験 | 一般受験(オープン) |
|---|---|---|
| 合格基準 | 主に内申点を基準に、合格がほぼ確約となったり、入試当日の試験の合格点の基準が下がったりする | 入試当日の試験結果のみで判断されることが多い |
| 出願手続き | 願書提出前に、個別相談会への参加や事前相談が必要 | 願書の提出のみで受験可能 |
| 入学義務 | 第一志望校(公立)が不合格の場合、必ず入学する義務がある ※志望順位に関わらず併願優遇を行う高校も少ないながら存在 | 合格しても入学するかどうかは自由に選択できる |
| メリット | 合格の可能性が高くなる | 複数の学校から選べる自由度がある |
| デメリット | 他の私立高校との併願が制限される場合がある | 合格の保証がない |
一般受験は、入試当日の試験結果のみで合否が決まる形式で、内申点が合否に影響しない場合が多いのに対し、併願優遇は内申点が重要な基準となります。また、併願優遇を利用するためには、個別相談への参加や、東京の場合は中学校の担任教師を通じた事前の入試相談が必要です。
入学の義務についても大きな違いがあります。一般受験の場合、複数の学校に合格したとしても、自分の意思で入学する学校を選ぶことができます。しかし併願優遇の場合は、第一志望の公立高校が不合格になった場合、必ずその私立高校に入学する義務があります(※志望順位に関わらず併願優遇を行う高校も少ないながら存在します)。
併願優遇と併願推薦・確約制度の違い
東京都の併願優遇制度と、近隣県で実施されている類似制度には、名称や仕組みに違いがあります。東京都在住でも、他県の私立高校を受験するケースが増えていますので、以下の表で各地域の制度を比較してみましょう。
| 地域 | 制度名称 | 特徴 |
|---|---|---|
| 東京都 | 併願優遇 | 内申点基準を満たせば優遇措置を受けられる。一部の学校では当日の試験結果も影響する |
| 埼玉県 | 併願推薦・確約制度 | 北辰テストの成績や内申点で「確約」が与えられる。公式な制度ではなく「暗黙の了解」 |
| 千葉県 | 併願推薦 | 内申点などの基準を満たせば合格が約束される |
| 神奈川県 | 併願確約 | 内申点等の基準を満たせば合格が決まる。ほとんどの学校で入試当日の点数に関わらず合格確約 |
埼玉県や千葉県では「併願推薦」という制度があります。これは東京都の併願優遇と似ていますが、埼玉県の場合は北辰テストの成績や内申点によって「確約」が与えられるという特徴があります。この埼玉県の私立高校の「確約」は公式な制度ではなく、東京の高校のように中学校の先生と私立高校での入試相談は行われません。中学生とその保護者が個別相談の際に「この成績なら安心して受験できます」といった形で伝えられます。
神奈川県では「併願確約」と呼ばれ、高校が定めた内申点等の基準を満たせば合格が決まります。東京都の併願優遇との大きな違いは、神奈川県の場合はほとんどの学校で入試当日の点数に関わらず合格が確約されるのに対し、東京都では一部の学校で当日の試験結果も合否に影響する場合がある点です。
これらの制度は共通して、公立高校を第一志望とする生徒が私立高校を「押さえ」として確保できるという利点があります。
東京都の私立高校における併願優遇制度の仕組み
東京都の私立高校では、多くの学校が併願優遇制度を設けています。この制度は学校ごとに細かな違いがあるため、自分に合った学校を選ぶためには、それぞれの仕組みを理解する必要があります。ここでは東京都の私立高校における併願優遇制度の基本的な仕組みと加点システムについて解説します。
併願優遇制度の加点システムについて
併願優遇制度における加点システムは、大きく分けて「内申点への加点」と「入試得点への加点」の2種類があります。以下の表で主な加点項目と一般的な加点例を示します。
内申点への加点は、英検や漢検などの検定試験の資格取得や、部活動での成績、皆勤賞などの実績に応じて行われます。このような加点により、本来の内申点では基準に達していなくても、併願優遇を利用できるようになる可能性があります。
入試得点への加点は、内申点基準を満たしている生徒や同一高校の複数回の受験に対し、入試当日の得点に一定の点数を加えるシステムです。例えば、帝京大学高校や東京農業大学第一高校、錦城高校などでは、内申基準を満たした生徒に一定の加点を行っています。この場合、加点後の得点で合否が判定されるため、通常の一般入試よりも合格しやすくなります。
加点システムを最大限に活用するには、早い段階から準備を進めることが重要です。特に英検や漢検などの検定試験は、中学校入学後から積極的に取り組むことで、3年生になったときに併願優遇を有利に進められます。また、部活動でも継続的に努力し、成績を残すことが加点につながります。
各学校によって加点の基準や方法は異なるため、志望校の説明会や個別相談に参加して、詳細な情報を収集することをおすすめします。
併願優遇制度のメリットとデメリット
併願優遇制度には様々なメリットがありますが、同時に注意すべき点やデメリットも存在します。この制度を活用する際には、メリットとデメリットの両面を理解した上で、自分の受験戦略に組み込むことが重要です。ここでは併願優遇制度のメリット、有利な点、そして注意点について詳しく説明します。
都立高校との併願におけるメリット
併願優遇制度の最大のメリットは、第一志望の都立高校を目指しながらも、「押さえ校」を確保できることです。以下の表で主なメリットをまとめてみました。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 心理的な安心感 | 「どこにも合格できない」という不安を解消し、自信を持って第一志望校の勉強に集中できる |
| 進学先の確保 | 都立高校が不合格でも進学先に困ることがない |
| 受験の効率化 | 複数の私立高校を受験する必要がなくなり、受験費用や労力を節約できる |
| 精神的負担の軽減 | 都立高校の入試結果を待つ間の不安や緊張が軽減される |
まず、このシステムを利用することで、よほどのこと(試験当日に会場に行かないなど)がない限り、私立高校にはほぼ確実に合格できます。これにより「どこにも合格できない」という不安を解消し、より自信を持って第一志望校の勉強に集中できるようになります。特に都立高校の入試は競争率が高く、優秀な成績でも不合格になるケースがあるため、このような「保険」を用意しておくことは大きな安心につながります。
また、都立高校が不合格になった場合でも、進学先に困ることがないため、受験後の精神的な負担も軽減されます。たとえば、都立高校の入試結果が出るまでの期間は、多くの受験生にとって不安と緊張の日々ですが、併願優遇制度を利用していれば「第一志望に不合格でもこの学校には入れる」という安心感を持つことができます。
さらに、この制度を利用することで、複数の私立高校を受験する必要がなくなり、受験にかかる費用や労力を節約することも可能です。通常、「滑り止め」として複数の私立高校を受験する場合、それぞれに受験料がかかりますが、併願優遇を利用すれば1校のみの受験で済むため、経済的な負担も軽減できます。
受験戦略における有利な点
併願優遇制度を活用することで、受験戦略全体を最適化できる様々な有利な点があります。以下の表でそのポイントをまとめました。
| 戦略的メリット | 詳細 |
|---|---|
| 合格のハードルが下がる | 入試得点への加点や合格基準の引き下げにより、合格しやすくなる |
| 学習の集中 | 第一志望の都立高校・私立高校の勉強に集中できる |
| 受験スケジュールの簡略化 | 受験校数を減らすことで、日程調整や移動の負担が軽減される |
| 志望校のレベルアップ | 通常なら手が届かないレベルの私立高校を「押さえ校」として確保できる可能性がある |
まず、併願優遇制度を利用すると、一般入試よりも合格しやすくなるという大きな利点があります。多くの私立高校では、併願優遇を利用する生徒に対して入試得点への加点や合格基準の引き下げなどの優遇措置を提供しています。例えば、一般入試では届かないレベルの学校でも、併願優遇を利用することで合格できる可能性が高まります。
また、併願優遇を利用することで、第一志望の都立高校の勉強に集中できるという戦略的メリットもあります。受験勉強は時間との戦いですが、複数の私立高校の対策に時間を割く必要がなくなれば、その分を都立高校の対策に充てることができます。特に都立高校と私立高校では入試科目や出題傾向が異なることも多いため、集中できる対象を絞ることは効率的な学習につながります。
さらに、受験当日のスケジュール管理も容易になります。通常複数の私立高校を受験する場合、日程が重なったり、移動時間の確保が必要だったりと、物理的・精神的な負担が大きくなりがちです。併願優遇を利用すれば、受験校数を減らすことができるため、このような負担を軽減できます。
併願優遇制度利用時の注意点とリスク
併願優遇制度には多くのメリットがありますが、同時に注意すべき点やリスクも存在します。以下の表で主な注意点をまとめました。
| 注意点・リスク | 詳細 |
|---|---|
| 私立第一志望条件 | 「本校が私立第一志望であること」が条件の場合、他の私立高校に合格しても入学できない |
| 合格の不確実性 | 優遇内容が「入試得点への加点のみ」の場合、当日の試験結果次第では不合格の可能性がある |
| 個別相談の必要性 | 多くの学校で個別相談への参加が必須となり、早期の予約が必要 |
| 基準の変動 | 併願優遇の基準や条件は毎年変動する可能性があるため、最新情報の確認が不可欠 |
最も重要な注意点は、併願優遇の条件に「本校が私立第一志望であること」が含まれる場合があるということです。これは言い換えれば、「都立高校に不合格であれば必ず本校に入学する」という約束のもとで優遇を受けるということです。したがって、他の私立高校をオープン入試で受けて合格したとしても、都立高校が不合格の場合は併願優遇校への入学が優先されます。
また、優遇の内容が「入試得点への加点のみ」である場合は、当日の試験結果次第では不合格になる可能性もあります。例えば、300点満点中30点の加点があったとしても、試験で120点しか取れなければ、加点後でも合格ラインに達しない可能性があります。このような学校を選ぶ場合は、当日の試験でも一定の点数を取る必要があることを念頭に置き、試験対策をしっかり行う必要があります。
さらに、併願優遇を利用する場合、個別相談への参加が必須となる学校も多いです。これらの相談は主に9月から11月にかけて行われるため、この時期に予定を確保しておく必要があります。特に人気校の場合、相談の予約が早期に埋まってしまうことがあるため、早めに公式サイトで情報を確認し、事前申し込みをすることが重要です。
これらの注意点を踏まえた上で、自分の学力や志望校の特性に合わせて、併願優遇制度を活用するかどうかを慎重に判断しましょう。
併願優遇制度の具体的な利用方法
併願優遇制度を効果的に活用するためには、出願手続きの流れや情報収集の方法を理解しておくことが重要です。ここでは、併願優遇制度を利用するための具体的なステップと、必要な情報を効率よく集めるためのポイントを解説します。
併願優遇制度の出願手続き
併願優遇制度を利用するための出願手続きは、通常の一般入試とは異なるステップを踏む必要があります。以下の表で時系列に沿った手続きの流れを示します。
| 時期 | 手続き内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 7月下旬〜8月 | 学校説明会への参加 | 併願優遇制度の概要や学校の特色について情報収集 |
| 9月〜11月 | 個別相談への参加 | 自分の成績で併願優遇が利用できるか確認。予約制の場合が多い |
| 12月初旬 | 担任への併願優遇希望の伝達 | 進路面談で希望を伝え、中学校と高校の入試相談に反映させる |
| 12月中 | 中学校と高校の入試相談 | 担任と高校間で生徒の優遇可否を確認 |
| 1月下旬 | 単願推薦入試 | 単願推薦を選択した場合の入試日 |
| 2月中旬 | 併願優遇での一般入試 | 併願優遇を利用しての一般入試日 |
まず、7月下旬から11月にかけて、志望する私立高校の学校説明会や個別相談に参加します。特に個別相談は、併願優遇制度を利用する上で重要な機会です。学校によっては個別相談への参加が併願優遇の絶対条件となっている場合もあります。夏休み期間中の7月下旬から8月は学校説明会、9月から11月は個別相談がピークシーズンとなります。
次に、12月の進路面談で担任に併願優遇制度の利用希望を伝えます。この時点で、併願優遇を利用したい私立高校を決定しておく必要があります。担任への連絡後、12月中に中学校の担任と私立高校の間で入試相談が実施され、併願優遇を希望している生徒の優遇可否が確認されます。
そして、1月下旬もしくは2月中旬頃に併願優遇制度を利用して入試を受けます。単願推薦の場合は1月下旬、併願優遇をもっての一般入試の場合は2月中旬が試験日となることが多いです。
併願優遇があるからといって試験を軽視するのは禁物です。あくまで試験会場では真剣に取り組む姿勢が大切です。これは落ちる可能性があるかどうか以前に、「押さえ校という立場を受け入れてくれる」「今後入学する可能性がある」高校に対する最低限の礼儀でもあるため、しっかりと準備して入試に臨みましょう。
併願優遇の説明会と情報収集のポイント
併願優遇制度を効果的に活用するためには、正確で最新の情報を収集することが不可欠です。以下の表で情報収集のポイントをまとめました。
| 情報収集の場 | 確認すべきポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 学校公式サイト | ・説明会・個別相談の日程 ・併願優遇の基本情報 | 定期的にチェックし、予約開始日を逃さない |
| 学校説明会 | ・併願優遇の概要 ・学校の特色と教育方針 | 複数の学校に参加し、比較検討の材料を集める |
| 個別相談 | ・内申基準の詳細 ・加点対象となる資格や実績 ・他私立高校との併願可否 ・入試当日の得点の影響 | 質問リストを事前に準備し、効率的に情報収集 |
| 塾や予備校 | ・併願優遇の傾向や実績 ・不明点の補足情報 | 学校公式の情報と照らし合わせて確認 |
まず、各私立高校の公式サイトをこまめにチェックすることが基本です。多くの学校では、説明会や個別相談の日程、併願優遇の基準などの情報を公式サイトで公開しています。特に人気校の場合、個別相談の予約が早期に埋まってしまうことがあるため、情報が更新されたらすぐに確認し、予約を入れることが重要です。
学校説明会では、併願優遇制度の概要や学校の特色について幅広く情報を得ることができます。この段階では、自分の興味や適性に合った学校をいくつかピックアップしておくとよいでしょう。説明会に参加する際は、併願優遇の基準や加点システムについて具体的にメモを取り、後で比較検討できるようにしておくことをおすすめします。
個別相談は、併願優遇制度を利用する上で特に重要な機会です。ここでは、自分の内申点や検定資格などの情報を持参し、実際に併願優遇の基準を満たせるかどうかを確認します。また、「部活動等で優秀な成果を上げている生徒」という基準について、具体的にどのようなレベルの成果が必要なのかなど、文面では読み取り切れない詳細を直接質問することができます。
個別相談では、複数の質問を効率よく行うために、事前に質問リストを準備しておくことをおすすめします。相談時間は限られていることが多いため、最も重要な質問から順に聞いていくようにしましょう。
なお、個別相談は何校参加してもかまいません。併願優遇制度を利用する可能性がある学校はすべて出席しておくことで、より多くの選択肢の中から最適な学校を選ぶことができます。
💻 自分に合った勉強スタイルを見つけよう
塾・通信教育・家庭教師など、学び方はさまざま。
それぞれの特徴を知って、自分に合う方法を選ぶことが成績アップの近道です。
👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】
![]()
👉 【難関対策】難関校対策に定評のある通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()
👉 【1対1】マンツーマンの個別指導で弱点克服 1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】 ![]()
👉 【東大の力】東大生講師から学べるオンライン指導 【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()
👉 【内申UP】対面で安心して教わりたい人は 家庭教師のノーバス ![]()
併願優遇制度を活用した受験戦略
併願優遇制度を最大限に活用するためには、自分の学力や志望校に合わせた戦略的な計画が必要です。ここでは、内申点に応じた私立高校の選び方、効果的な併願パターン、そして万が一の場合の対策について解説します。
内申点に応じた私立高校の選び方
併願優遇制度を利用する際、最も重要なのは自分の内申点に合った私立高校を選ぶことです。以下の表で内申点別の選び方のポイントをまとめました。
| 内申点レベル | 選び方のポイント | おすすめの戦略 |
|---|---|---|
| 高い(9教科40以上) | 偏差値の高い私立高校も視野に | 都立トップ校と同レベルの私立名門校を併願優遇で押さえる |
| 中程度(9教科35〜39) | 内申加点項目を活用 | 検定や部活実績で加点を得て、レベルの高い学校を狙う |
| やや低め(9教科30〜34) | 加点を最大限活用する学校を選ぶ | 加点制度が充実している学校を重点的に調査 |
| 低い(9教科29以下) | 内申基準の低い学校を探す | 基準が緩やかな学校や専願制度のある学校も検討 |
まず、自分の内申点を正確に把握することから始めましょう。併願優遇の基準となるのは主に中学3年生の2学期までの成績ですが、2年生の成績や3年生1学期の成績も参考にすることで、2学期の内申点をある程度予測することができます。
次に、自分の内申点で併願優遇が利用できる学校をリストアップします。多くの私立高校は公式サイトや募集要項で併願優遇の内申基準を公開していますので、それらを参考にしましょう。
ただし、内申点だけでなく、検定資格や部活動の実績による加点も考慮する必要があります。例えば、英検3級を持っていれば内申点に1点加点、準2級なら2点加点といった形で優遇される学校も多いです。自分が持っている資格や実績をすべて洗い出し、それによってどの程度の加点が期待できるかを確認しておくことが重要です。
内申点が比較的低い場合は、加点制度を最大限に活用できる学校を選ぶことが重要です。例えば、内申点が9教科で32だとしても、英検準2級(+2点)と部活動での都大会出場(+2点)があれば実質36となり、基準が「9教科35以上」の学校でも併願優遇を利用できる可能性があります。
具体的な選び方としては、「第一志望の都立高校よりもやや偏差値が低いレベル」の私立高校を選ぶのが一般的です。これにより、都立高校に不合格になった場合でも、一定水準の教育環境を確保することができます。
都立高校と私立高校の併願パターン
併願優遇制度を活用した効果的な受験戦略を立てるためには、都立高校と私立高校の併願パターンを理解し、自分に適したプランを選ぶことが重要です。
代表的な併願パターンを以下の表にまとめました。それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、自分に最適な組み合わせを選びましょう。
| 併願パターン | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| パターン1 | 第一志望都立高校 +併願優遇私立高校 | ・受験校数が少なく集中できる ・費用が抑えられる | ・選択肢が限られる |
| パターン2 | 第一志望都立高校 +併願優遇私立高校 +オープン入試私立高校 | ・より多くの選択肢を確保できる | ・受験準備の負担増 ・費用増加 ・条件によっては不可能 |
| パターン3 | 第一志望都立高校 +複数の併願優遇私立高校 | ・私立高校の選択肢が増える | ・条件によっては不可能 ・手続きが複雑 |
| パターン4 | 第一志望私立高校 +併願優遇私立高校 | ・受験校数が少なく集中できる | ・都立第一志望よりも選択肢が限られる ・条件によっては不可能 |
| パターン5 | 第一志望私立高校 +併願優遇私立高校 +オープン入試私立高校 | ・より多くの私立高校の選択肢を確保できる | ・都立第一志望よりも選択肢が限られる ・受験準備の負担増 ・費用増加 ・条件によっては不可能 |
最も一般的な併願パターンは、「第一志望の都立高校+併願優遇の私立高校」というシンプルな組み合わせです。例えば、第一志望が都立西高校で、併願優遇として日本大学第二高校を選ぶといった形です。このパターンのメリットは、受験校数が少なく、第一志望校の対策に集中できる点にあります。また、受験にかかる費用も抑えられます。
より多くの選択肢を確保したい場合は、「第一志望の都立高校+併願優遇の私立高校+オープン入試の私立高校」というパターンも考えられます。この場合、併願優遇の条件に「私立第一志望であること」が含まれていないことを確認する必要があります。このパターンのメリットは、より多くの選択肢があることですが、受験校数が増えることによる負担や費用の増加がデメリットとなります。
併願パターンを選ぶ際は、自分の学力レベルと目標のバランスを考慮することが重要です。学力に自信がある場合は、第一志望の都立高校により多くの時間を割き、併願優遇はあくまで「保険」として位置づけるとよいでしょう。一方、学力に不安がある場合は、併願優遇で合格可能性の高い私立高校を選び、万全を期すことも大切です。
実際の併願例として、「都立文京高校+併願優遇で淑徳巣鴨高校」「都立武蔵野北高校+錦城高校」のようなパターンがあります。この場合、第一志望である都立文京高校や都立武蔵野北高校に不合格になっても、同じく進学実績の良い淑徳巣鴨高校や錦城高校に進学できるため、教育環境の連続性を保つことができます。
また、経済的な観点からも併願パターンを検討することも大切です。私立高校は都立高校と比べて学費が高くなりますが、併願優遇で入学する場合、特別奨学金制度を設けている学校もあります。
併願優遇で不合格になった場合の対策
併願優遇制度を利用しても不合格になるケースはまれですが、可能性はゼロではありません。そのような万が一の事態に備えて、以下の表で対策をまとめました。
| 対策 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 優遇内容の確認 | 「合格確約型」か「加点型」かを確認 | 加点型の場合は入試対策も必要 |
| バックアップ校の用意 | 合格可能性の高いオープン入試校を受験 | 併願条件の確認が必須 |
| 追加募集・二次募集のチェック | 私立高校の追加募集や都立高校の二次募集をチェック | 2月下旬〜3月上旬に実施 |
| 通信制・高等専修学校の検討 | 代替進路を検討 | 柔軟に選択肢を広げる |
| 精神的な準備 | 複数の進路に対する心構えを持つ | 冷静に次の選択肢を考える |
まず、併願優遇を利用する学校を選ぶ際は、優遇の内容をしっかり確認しておきましょう。「合格を確約する」タイプの学校であれば、よほどのことがない限り不合格になることはありませんが、「入試得点に20点加点」のようなタイプの学校では、当日の試験で十分な点数を取る必要があります。後者の場合、過去問などで入試対策をしっかり行い、最低限の得点が取れるよう準備しておくことが大切です。
また、併願優遇で不合格になった場合の「バックアップ校」を用意しておくことも一つの対策です。例えば、併願優遇とは別に、合格可能性が高いオープン入試の私立高校を受験しておくという方法があります。ただし、併願優遇の条件に「私立第一志望であること」が含まれている場合は、他の私立高校との併願が制限されることがあるため、事前に確認が必要です。
万が一すべての受験校が不合格だった場合は、私立高校の追加募集や、都立高校の第二次募集、さらには通信制高校や高等専修学校などの選択肢も考慮に入れておくとよいでしょう。多くの私立高校では、定員に満たない場合に追加募集を行うため、これらの情報をこまめにチェックしておくことが重要です。
最後に、精神的な準備も大切です。受験は必ずしも計画通りに進まないことがあります。不合格という結果も含めて受け入れる心構えを持ち、万が一の場合でも冷静に次の選択肢を考えられるよう、心の準備をしておくことも重要です。
教育相談や進路指導の先生に相談しながら、複数の選択肢を用意しておくことで、どのような結果になっても対応できる準備をしておきましょう。
併願優遇制度の活用事例
併願優遇制度をどのように活用すれば効果的なのか、実際の事例を通して具体的にイメージしてみましょう。ここでは、異なるタイプの生徒の事例を紹介し、それぞれがどのように併願優遇制度を活用して志望校合格を勝ち取ったのかを解説します。
例1:内申点が高く、都立トップ校を目指す生徒のケース
中学3年の夏時点で内申点が9教科で40(5段階評価で平均4.4)と高い成績を持つ太郎さんは、偏差値70の都立トップ校を第一志望としていました。彼は併願優遇制度を活用して、偏差値65の私立名門進学校を「押さえ」としました。
太郎さんはまず7月の学校説明会で私立高校の情報を収集し、10月に個別相談に参加しました。そこで内申点と英検準2級の資格を提示したところ、「十分に基準を満たしています」との回答を得ました。12月の進路面談で担任に併願優遇希望を伝え、中学校と高校の間で入試相談が行われました。
2月、太郎さんは第一志望の都立高校と併願優遇の私立高校を受験しました。都立高校の試験は難しく感じましたが、私立高校では併願優遇があったため、比較的リラックスして受験できました。結果として、都立高校は不合格でしたが、私立高校には無事合格し、進学することになりました。
この事例から学べる教訓は、内申点が高い生徒でも都立トップ校は競争が激しいため、レベルの高い私立高校を併願優遇で押さえておくことの重要性です。また、早期から情報収集を始め、計画的に準備を進めることで、余裕を持って受験に臨めることがわかります。


例2:内申点に不安があるが、資格や部活動で加点を狙う生徒
内申点が9教科で32(平均3.6)とやや低めで、偏差値60の都立高校を目指していた花子さんは、内申点だけでは併願優遇の基準に届かない可能性がありました。しかし、彼女は英検3級、漢検準2級の資格を持ち、部活動でも都大会に出場した実績がありました。
花子さんは9月から複数の私立高校の個別相談に参加し、資格や部活動による加点がどの程度あるのかを確認しました。その結果、第一志望の都立高校と同レベルの私立高校では加点を含めても基準に届きませんでしたが、偏差値55程度の私立高校なら併願優遇が利用できることがわかりました。
12月の進路面談で併願優遇希望を伝え、2月に都立高校と私立高校の試験を受けました。都立高校は惜しくも不合格でしたが、併願優遇で受けた私立高校に合格しました。入学後、花子さんは高校の特色ある英語教育に魅力を感じ、積極的に勉強に取り組みました。
この事例からは、内申点だけでなく資格や部活動による加点を最大限に活用することの重要性がわかります。また、偏差値だけでなく学校の特色も考慮して併願先を選ぶことで、結果的に自分に合った環境を見つけられる可能性があることも示唆しています。
事例3:複数の私立高校との併願を考える生徒
内申点が9教科で36(平均4.0)の健太さんは、偏差値62の都立高校を第一志望としていましたが、より多くの選択肢を確保したいと考えていました。彼は併願優遇を利用できる私立高校を探す際に、「他私立高校との併願が可能」という条件も重視しました。
個別相談では、「他私立高校との併願が可能か」を必ず質問し、複数の選択肢を検討しました。最終的に、偏差値58の私立A高校で併願優遇を利用し、さらに偏差値65の私立B高校をオープン入試で受験するプランを立てました。A高校は「他私立併願可能」と明記されており、B高校は特に併願条件を設けていなかったため、このプランが実行可能だと判断しました。
2月、健太さんは第一志望の都立高校、併願優遇のA高校、オープン入試のB高校を受験しました。結果として、都立高校は不合格、A高校は合格、B高校も予想外に合格しました。「他私立併願可能」の条件だったため、B高校を選択して入学することができました。
この事例からは、併願優遇を利用しつつも、他の私立高校との併願が可能な学校を選ぶことで、より多くの選択肢を確保できることがわかります。ただし、この戦略を取る場合は、各学校の併願条件を正確に理解しておくことが極めて重要です。

併願優遇制度を賢く活用するポイント
東京都の私立高校における併願優遇制度は、受験生にとって大きなメリットをもたらす重要な選択肢です。この制度を効果的に活用することで、受験の不安を軽減し、より戦略的な高校受験が可能になります。以下の表で、併願優遇制度を賢く活用するためのポイントをまとめました。
| ポイント | 具体的な行動 | 理由・効果 |
|---|---|---|
| 基本を正しく理解する | 優遇内容や条件を正確に把握 | 自分に合った学校選びの基盤になる |
| 早期の情報収集 | 7月から説明会・個別相談に参加 | 選択肢を広げ、計画的な準備が可能になる |
| 内申点の最大活用 | 資格取得・部活動に注力 | 加点によって基準到達の可能性が高まる |
| 最適な併願パターン選択 | 学力・志望校に合わせた組み合わせ | 合格の可能性と選択肢のバランスを取れる |
| 試験対策を怠らない | 優遇があっても入試準備は万全に | 加点型の場合や学力定着のために重要 |
まず、併願優遇制度の基本を正しく理解することが出発点となります。この制度は「都立高校が不合格だった場合に入学することを条件に、私立高校が一般入試で優遇してくれる」というものです。優遇の内容は学校によって異なり、入試得点への加点や合格の確約など様々です。自分が希望する高校がどのような優遇を提供しているのかを事前に確認しておきましょう。
次に、早い段階から情報収集を始めることが重要です。7月下旬から始まる学校説明会や、9月から11月にかけての個別相談に積極的に参加し、各学校の併願優遇の基準や条件を正確に把握しましょう。特に個別相談は、自分の成績や資格が基準を満たしているかを直接確認できる貴重な機会です。
また、内申点を最大限に活用するための工夫も大切です。英検や漢検などの資格取得、部活動での実績など、加点対象となる項目に積極的に取り組むことで、併願優遇の可能性を広げることができます。特に中学1・2年生の段階から計画的に取り組むことで、3年生になった時に選択肢が増えるでしょう。
併願パターンを検討する際は、自分の学力や志望校に合わせた最適な組み合わせを考えることが重要です。単純に「第一志望の都立高校+併願優遇の私立高校」というパターンだけでなく、複数の都立高校や他の私立高校との併願も視野に入れて、総合的に判断しましょう。
最後に、併願優遇があるからといって試験対策を怠らないことが大切です。特に優遇内容が「入試得点への加点のみ」である場合は、当日の試験結果も合否に影響します。また、たとえ合格が確約されていても、試験に真剣に取り組む姿勢は高校側への礼儀でもあります。
併願優遇制度は、東京都の高校受験において大きなアドバンテージとなり得ます。この制度の仕組みをよく理解し、計画的に活用することで、受験の不安を軽減し、自分に最適な進学先を見つける手助けとなるでしょう。早期からの情報収集と準備を心がけ、悔いのない高校受験を実現してください。
難関校を目指すなら、自宅学習にも“本物の教材”を
「この高校に入りたい」――そう思ったとき、気になるのはやはり“受験への準備”。
自分のペースで本格的な受験対策がしたい中学生や、塾に通わずに質の高い学習を進めたいご家庭におすすめなのが【Z会の通信教育】です。
難関校対策に対応したハイレベルな教材と、記述力を伸ばす添削指導。
通信教育でありながら、学習習慣から答案力までしっかり鍛える仕組みが整っています。
本気で上位校を目指すなら、Z会という選択があります。
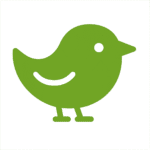 トリトリ
トリトリ部活も文化祭もひと段落。これからは志望校合格に向かってラストスパートをかける時期が来たよ!
秋は、学力を伸ばす絶好のタイミング。
Z会の通信教育〈高校受験コース〉なら、考えて「紙に書く」学びを通して、難関高校合格レベルへと実力を高められます。
苦手やレベルに合わせた個別プログラムで、定期テスト対策から入試対策までしっかりサポート。
今なら『英語Writingワーク』(学年別)と『自主学習の継続を後押しする保護者のサポートBOOK』をプレゼント中!
忙しい秋だからこそ、親子で「これからの学び」を見直すチャンスです。
\ 資料請求で2つの特典をプレゼント! /